交流の広場
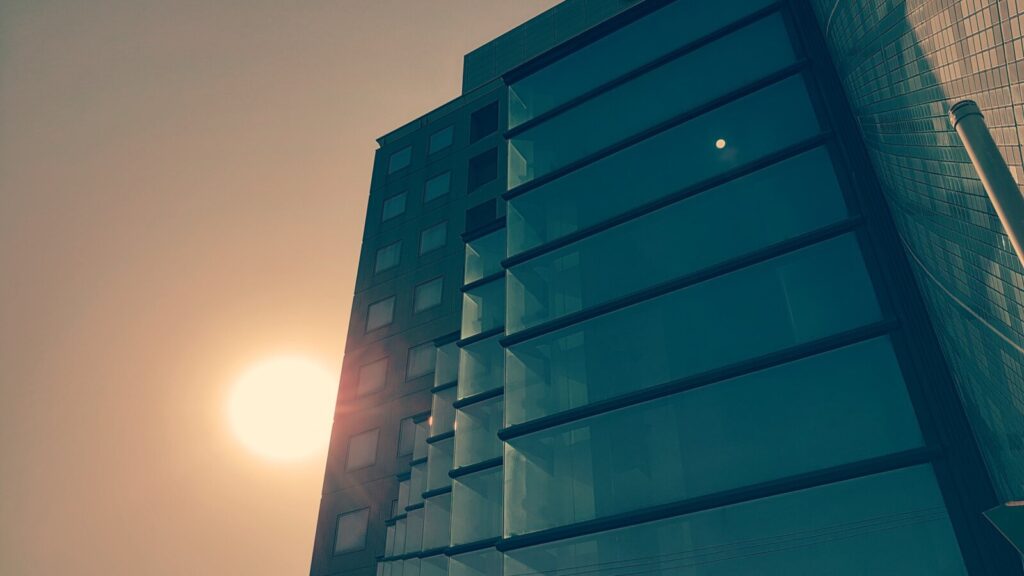
©︎Y.Maezawa
戦後のドイツ哲学と精神医学の関わりをめぐって
コロナ禍の現在から考える
精神科医
菅原一晃
はじめに:政治と学問と精神医学
学問的な見地を政治状況に照らし合わせると、戦後の日本ではマルクス主義が大きな役割を果たしていました。例えば、1980年代の政治状況を見るなら、長い冷静時代の終盤にあたり、レーガン大統領やサッチャー首相、中曽根首相が新自由主義を唱えたこの時代、敵役としてマルクス主義経済学が理論的にも実践的にも生きていました。つまり、なお1970年ごろの学生闘争の残り火を感じられる時代だったといえます。ところが、1990年代に入ると、アメリカ陣営とソ連陣営の冷戦構造の終了と新自由主義の台頭などがあり、マルクスの名前は忘れられて行きました(ただし、最近では斎藤幸平氏の言及などにより再度『資本論』などが注目されています)。
哲学と関連の深い精神医学についていえば、かつてハイデルベルク大学教授で精神科医のブランケンブルクは個別科学と哲学の関係を描いていました。しかし、その視点は現在となっては変質しています。なぜならば、精神医学がそうであるように、哲学自体も現在は変質してしまっているからです。私自身は理論面でも実践面(臨床面)でも個別科学と哲学が弁証法的なもの、つまり相互補完的なものになってほしいと考えていますが、現在は個別科学と哲学との間には何の関係もなくなってしまっているのです。
ここで重要なのは、ブランケンブルクの現象学的人間学的な態度です。ブランケンブルクは人間学的(現象学的)精神病理学の立場であり、日本では木村敏と近い立場ですが、体験することとふるまうことが人間本質から規則的に変化することとして、精神疾患を捉えて理解しようとしました。そして理論と臨床が相互に影響を与え合う、いわゆる弁証法的な態度が前提にあり、多くの事象を実践と理論が相互浸透することで、理論だけではなく、『自然な自明性の喪失』など重要な症例を報告することができたのであろうと思います。
1980年代、哲学・思想的にはマルクス主義が生きており、他方それを批判的に論じる傾向も強く、百花繚乱といえる状況を呈していました。特にフランスを中心としたポストモダン思想がアクチュアルな形で出現し、日本でも『現代思想』誌や『imago』誌などに多くの論説が紹介されていました。また、精神医学においても多くの哲学・精神分析的な論説が引用・援用され、それが説得力をもって精神科医や哲学者、さらにその他多くの人文系学者、教養人に受け入れられていました。いまとなっては考えられないほど魅力的な時代であったと思われます。
これらの前提を踏まえるならば、当時は学問を理論的に論じる傾向、そしてそれが現実的なアクチュアリティをもっていた時代だったと思われますが、わずか20~30年のあいだに何が変わったのでしょうか。私の考えでは三つの要因があります。時代状況の変質、哲学(をはじめとする学問全体)の変質、それに精神医学の変質が、同時多発的、しかもシンクロニックに生じた結果、政治と学問の関係に大きな変化が生じました。最大の衝撃は時代状況の変質から生じ、それ学問の変質、ひいては精神医学の変質をもたらしたという展開になります。
1 時代状況の変質
当時の新自由主義の初期の時代と比較し、明らかに現在は新自由主義が前面に出ており、当時は「一億総中流」と言われた日本が格差の大きな拡大で社会問題となっています。因みに、1979年にイギリスでサッチャー政権、1980年にアメリカでレーガン政権が誕生しました。日本でも1982年に中曽根政権が誕生し、先進国で新自由主義の土台がつくられていきますが、本格的に浸透していったのは1990年代後半から2000年代初頭です。
また、ポピュリズムの台頭及びエリート、教養主義の没落、無価値化があり、右傾化、排外主義化も進んでいます。これらは日本だけの問題ではなく、北米、欧州など先進国と言われた国で広範に認められています。哲学その他の学問は「難しい」「役に立たない」と切って捨てられ、代わって難度を下げ、愛国心を煽るような、そして他者を排斥するようなアジテートが人口に膾炙されています。
この背景としては、冷戦構造の崩壊及びその理論的バックボーンであるマルクス主義の崩壊が大きいと思われます。マルクス主義はカール・マルクスの言説から出発したものであり、人間の労働を疎外と捉えることから、思想、経済、政治など多くの場面や分野に影響を与えました。これらの理論においては「理論」が「経験」に先に立つ、いわば演繹主義的な構造があり、それ故に「理論」自体が重要視され、理論的な思考が大切にされたと思うのです。また、これはカール・ポパーが「反証不能」として批判することですが、共産主義・社会主義が上手くいかない場面では、「共産主義が悪いのではなく中途半端で完成されない途上の形だから」「これが乗り越えられてさらに良いものが生まれる」という弁証法的な言説がマルクス主義ではなされますが、やはり理論中心の産物だからと言えると思います。
それ故、この時代における思考では、「理論をいかに理論で乗り越えるか」ということが大事になり、知的なエリート主義が優先されることとなります。逆に言えば、マルクス主義が崩壊したあとでは、理論をどんなに説いて「実際に儲けなければ」「なんらかの成果がなければ」というように、強迫的に効率や成果を求める言説が蔓延します。
新自由主義はこのような言説と相性が良く、「年功序列は意味がない」「生産効率の悪い部署は切る」と言ってどんどん目に見えないものは捨象する、そのような思想が中心となります。当然のように教養主義は崩壊し、エリートの価値も低下していく。このような違い・変化がここ20~30年でありました。あまり触れたくないことでありますが、日本の政治の混乱、というより、その反知性主義的な面は上記の行きついた先、という感じがしますし、その根本・遠因としてはマルクス主義の、政治および学問的な崩壊が大きいと思います。
2 哲学(をはじめとする学問全体)の変質
上述の時代状況の変化と絡めてもう一点、マルクス主義について述べるならば、当時の更に前時代の思想とされる実存主義の凋落がさらにその遠因と考えられます。マルクス主義には、①時代の分析をするための理論と、②時代を変えるための実践や革命論、つまり社会を分析するというよりは社会を変えるための哲学という二つの側面があったと言えますが、同様に実存主義の哲学が目指すべきものも「社会参加」であり、机上の学問ではなく、哲学の実践として「実存的人間」を目指していました。
フランスのジャン=ポール・サルトルをはじめ、カール・ヤスパースも同様な傾向がありますが、この時代にはハイデッガーも同様に「実存主義」の哲学者として読まれ、社会参加を呼びかける哲学者としての意味がありました。ハイデッガーに関しては本人自身がそのような読まれ方を否定していると思いますが、このように「人間とは何か」を考える本質的な学問の営みとしての哲学は、非常に魅力的であると言えました。
ところが、ポストモダン傾向が強くなると、一般的には現状分析の比重が強くなり、社会参加の面が弱くなります。このことは哲学の「魅力」においては非常に大きいと思われ、「自分の悩みを解決する」「自分はどのように生きるかを考える」という学問としての哲学という面が、実存主義、さらにはマルクス主義の凋落で失われていきます。
私見では、20世紀を代表する哲学「認識論」「現象学」「心の哲学」にまとめあられます。この最後の「心の哲学」や、「認識論」に含まれる分析哲学の存在が、哲学をさらに実践から遠ざけるものにしたと思います。そしてこれらの哲学は哲学の思考する範囲を狭めたという意味があり、分析哲学であれば、文の組成や意味などを分解するような非常に狭い範囲での研究であり、心の哲学も心と身体や心と脳の関係を解読するものの、それが社会や「自分の謎」といったものに広がらない(ように敢えて思考範囲を狭めている)面があります。
先ほど私は社会状況が理論に抗っている、理論など要らないというようになっていることを述べましたが、これらの心の哲学や分析哲学はむしろ「理論的すぎる」ために、やはり門外漢の接近を拒むものとなっています。そしてそれらに並行し、社会を分析するツールとしての学問として特に90年代以降、心理学や社会学が隆盛を迎えます。そのため哲学の存在感が低下するとともに、哲学が自ら分析対象を狭め自閉的になったように思われますが、これは哲学自体にとってあまりにも役不足と言わざるを得ません。また、社会学や心理学では、一時的に「面白い」かもしれませんが、結局のところ理論的分析の不十分さは否めません。
3 精神医学の変質
この変質をもたらした最大の要因は、診断基準としてのDSMの普及とSSRIなどの新しい抗うつ薬(や抗精神病薬)の出現です。このうち本質的なものはDSMの存在であると思います。精神病理学が戦後に様々な理論を引っ提げて華々しく特に日本とドイツで開花しましたが、精神医学に診断基準や何らかの定見があるかないかは、心に病を持つ人間を診察し関与する人間、つまり精神科医にとっては死活問題です。
異論があると思われますが、精神病理学は大きく分けて症候学と分類学に分けられると思います。一つ目の症候学こそ、まさにフランスのエスキロールが成した精神病理学の原点であると思います。記述的精神病理学といってもよいかもしれませんが、患者の病態で何が問題になっているかをきちんと把握し理解するための症候は、臨床をするどの医師にも不可欠でありますし、現代でもその重要性は衰えていません。日本精神神経学会などの学会で、「精神病理学の有用性」を主張するような発表や企画はまさにこの「症候学」を前面に出していると思われます。
二つ目の分類学、あるいは分析的精神病理学は19世紀末のドイツで急速に発展した分野ですが、診断的に患者を診て、それをつなげることに大きく寄与したと思われます。しかしその一方で、各人が各々主張するために診断に対しての「信頼性」が損なわれた面があり、それが「精神科であれば誰でも診断できるツール」としてのDSMの出現を要請したと思われます。
DSMは決して使いやすい診断ツールではないと思いますし、若い先生たちも同様に感じていると思います。何故ならば、このDSMの精神、つまり「病因や病態を保留すること」が近代医学の精神に反しているからです。
近代医学はパスツールらによる病原菌の存在の発見などに端を発したと考えられますが、ここにあるのは病気の原因を特定するという精神です。病気の部位を特定し、病因を特定すること、そしてそれがどのような形で人体に影響するのかという病態を特定することで近代医学は発展してきました。最も顕著なのが感染症学であり、感染部位や原因菌、その炎症の波及過程を明らかにすることで人間の感染症の仕組みがわかり、20世紀に入ってその菌を殺傷するペニシリンなどの抗菌薬が発見や合成されることで、感染症の死亡率は劇的に低下していきました。
精神医学も同様で、病気の部位は不特定(脳と言えそうであるがはっきり言えないという含意が「内因」にはあると思われます)であるものの、例えば統合失調症(Schizophrenie)やうつ病(Depression)がどうやって発症したか、どのような人間関係や家庭環境、社会環境が影響をするかなどを考えたことは、治療的にも有意義であり、また病気の人間を通すことで、根本的な人間理解につながることになったと思われます。
これらの因果関係や成因を排除することで、DSMは多くの統計的なデータを集積してきましたが、精神病理学的な思考を排除したことは結果的に精神医学を魅力のないもの、さらには余計にとっつきにくいものにしたと思います。
私自身、DSMは「診断の答え合せ」のようなことにしか使えないと思っており、例えてみれば、刑事が犯人の顔を特定するのに、モンタージュや似顔絵を描いてから、その後に個々の顔の特徴を照合するようなものです。従来のように診断によってある程度全体的な疾患概念が分からない状態で、DSMのみで診断した場合には、上記の犯人の例えでいえば、「犯人の顔の各部分は正確に描かれているものの、雰囲気が全く異なる」似顔絵やモンタージュが出来上がりますが、これでは犯人逮捕にはつながりません。
同様に、DSMのみにて診断しても、「診断基準は満たすが、実際にはその疾患でない」という診断が出来上がることになります。そういう意味で従来型の精神病理学的な知見というのは重要であると思いますし、病気の本質を絶え間なく探求する意味では「哲学者たらねばならない」のはDSM後も続いていると思います。
4 ドイツの戦後哲学
ブランケンブルクをはじめとした精神病理学の理論が現在でも非常に魅力的に、生き生きとしているのを感じます。逆説的に聞こえるかもしれませんが、これは当時のドイツの哲学が魅力のないものであったことが影響しているのではないかと私は考えております。
第二次世界大戦前のドイツには、フッサール、カッシーラー、ジンメル、マックス・ウエーバー、リッケルト、マンハイム、ハイデッガー、ベンヤミン、さらにヤスパースなどなど、数えきれないくらいの多くの哲学者たちがいました。また理工学系の科学的な研究も世界の最先端を走っていました。それに引きかえ、戦後のドイツ哲学はフランクフルト学派のホルクハイマーやアドルノ、その後輩のハーバーマスやシステム論のルーマンくらいしかいないのではないかと思われます。
その理由ははっきりしており、ナチス時代にユダヤ系を中心とした多くの知識人がアメリカなどに国外亡命や移住したことが大きいと言われています。同様に、理工学や医学の発見や研究の中心もアメリカに移ります。そしてさらにその後の展開として、ナチス時代の反省が強調されたために、ナチスを連想させる思想一般、ロマン主義、保守主義、非合理主義などに分類される可能性のある思想、ニーチェ、ハイデッガー、シュミットなどが危険視され、合理主義や啓蒙主義、民主主義などを示さなければならなくなったことが大きく、ドイツ的な哲学の伝統が失われた面があります。
このようにドイツの哲学が瀕死の状態であったからこそ、ブランケンブルクやヤンツアーリクらは、哲学と精神医学の緊張関係に自覚的であり、さらには自身の理論を極力既存の哲学に縛られない形で生み出す必要に迫られたのではないかと思われます。この点が、戦後ハイデッガーの影響を多かれ少なかれ受け、デリダ、レヴィナス、フーコー、ドゥルーズらを輩出したフランスとの大きな違いと言えると思うのです。
5 現代のドイツ哲学
日本ではドイツがコロナ対策の優等生のように非常に持ち上げられていますが、私自身はそれに対して違和感があります。また、ドイツの哲学者であるマルクス・ガブリエルが日本では「最先端の哲学」としてもてはやされ、コロナ危機などに関しても意見を求めており、日本の視聴者や読者に意見を発しています。しかし、ガブリエルの思想はハーバーマスのような近代的(ヨーロッパ的)理性・主体性をもとにした個人や社会を前提とし、またヨーロッパの社会システムを(近代社会の到達点のように)考えている点で、社会思想として違和感がありますし、日本への意見としてはどうなのかと思うことが多いのです。
「ヨーロッパ的な近代化」はどこまで正当性があるのか、その結果がナチスドイツを産んでしまったのではないかを問い続けたのが第二次世界大戦後のドイツ哲学やフランクフルト学派なわけです。だから、私から見るとマルクス・ガブリエルの社会への意見はあまりにもナイーブに見えるのです。というか、そもそも彼は社会思想などの専門ではない訳で、極度に持ち上げすぎる日本のスタンスはどうなのかと思っています。先日までの「ロックダウン」に関しても、「全世界が中国のようなやり方になってしまった」とガブリエルは言っているわけですが、この視点もどうなのかと疑問に思っていました。
ガブリエルらの発言は「(左派)エリートの議論」に典型的なものと考えます。彼らははっきり言えばコロナウイルスの影響を受けにくく、何かあればあったで意見を求められる立場です。現状をどうにかしないといけないという視点が彼らの議論では乏しく、このようなエリートの発言によって2016年にトランプ大統領が誕生したことや、ドイツでもAfD(ドイツのための選択肢)などの排外的な政党の躍進の下地になったことなどを未だに理解していないのではないかと思われます。
翻って日本では、コロナ危機での格差の拡大が広がるリスクなどの問題もあまり真剣に議論されていません。中小企業などが苦しみ倒産のリスクがあることなどから多くの融資への要望や定額給付金などが問題として上がりましたが、社会全体の方向性に関しての議論は日本ではほとんど聞かれていませんでした。今後の未来の予想、特に格差拡大のリスクの問題などはもっと議論されて良いことでしょう。
あとはドイツ自身がEUに好意的(=懐疑的ではない)という視点も問題を問題として扱われていない気持ち悪さがあります。実際、イタリアでコロナウイルスでの多数の死者が出たことに関しては、2008年の金融危機以降の医療削減が大きかったといわれており、その緊縮を主導したのはまさにドイツなわけですから、ドイツがイタリアに行って医療支援をしていて素晴らしいという論調が出ていたのは、自作自演のマッチポンプなのではとさえ思ったものです。ドイツはEUからとても大きな利益を得ていて、それをフランスの人類学者のエマニエル・トッドなどは批判しているわけですが、この辺りの批判は現在のコロナウイルスを目の前にしても有効だと思います。
いずれにせよ、ドイツについては2015年に大量の移民が入ったことから外国人労働者がとても多く、さらにその移民たちは給料が概して低いため、現地では格差が開くかどうかというのが切実な議論としてあります。これらの議論を踏まえて、日本の現状とすり合わせる必要があると思います。

©︎菅原一晃

©︎菅原一晃
〜昔と変わらぬ風景 ハイデルベルグ〜
(編集:前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。