活動の実績
老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > システム倫理学 > 「正解」なき世界の「バイアス」論 森下直貴

「正解」なき世界の「バイアス」論
コロナ禍の中を人はいかに生きるのか
老成学研究所 代表
森下直貴

©︎Y.Maezawa
「汝自身を知れ」とは、
あなた自身のものの見方の「観点」を知れということだ。
【はじめに】
2020年の初め以来、新型コロナウイルスの感染拡大が世界中で続き、一年後の現在においてもその収束は見えていない。
この間、三密や、PCR検査、集団免疫、ロックダウン、緊急事態宣言、医療崩壊、エクモ、トリアージ、自粛警察など、これまで馴染みのなかった言葉がメディアを通じて垂れ流されてきた。また、ソーシャルディスタンスや、リモート会議、テレワーク、デリバリーなど、今まで経験したことのなかった新しい生活様式広がりつつある。
目下、新型コロナに対する政府の対応や、医療界の取り組み、個々人の行動をめぐって、専門家だけではなくマスメディアのコメンテータに一般国民も加わり、大量の断片的で断定的なリスク情報や見解が撒き散らされている。こうした情報氾濫(インフォデミック)の中で、人々の恐怖心がいたずらに掻き立てられ、新たな垣根や分断、さらには差別や排除まで生じている。
もちろん、多数の個体が集団を構成して生きている以上、混乱と対立は避けられない。しかし、そのことによって分断と差別が作り出されるのは好ましいことではない。
とすれば、コロナ禍で蔓延する混乱と対立を解きほぐすために、私たちはどうすればいいのだろうか。
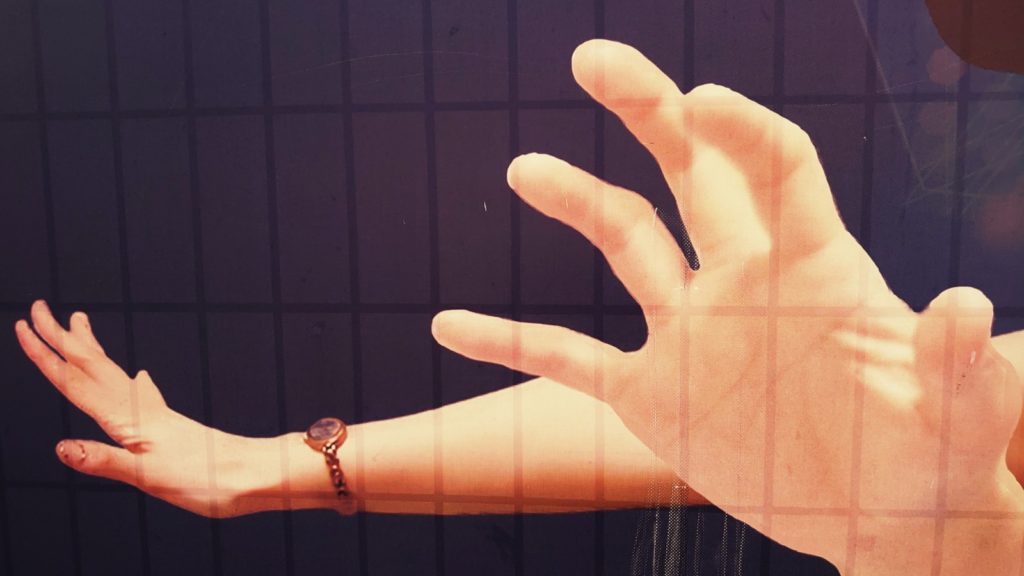
この種の問いに応えるための一つのアプローチが「システム倫理学」である。
ここで提案されるのは、
「論点」「解釈」「観点」「実践目標」という四つのステップを設定し、コミュニケーションの基本枠組み(四次元相関)に基づいて、関係者がステップごとに吟味し合い、全体の一致ではなく各々の自己変容を通じて対立をずらしていくという方法だ。
(拙著『システム倫理学的思考』第5章)
四ステップの中で相互吟味のプロセスを方向づけるのは「実践目標」だ。その共有がプロセス全体の成り行きを左右する。
私見では、新型コロナ対策の「実践目標」は、感染力は強いが死者数の比較的少ない点を考慮する限り、集団免疫を目指し、重症患者の治療に焦点を合わせた、平時にも非常時にも対応可能な医療体制を整備することになる。
この目標が国民に共有されたら(ここが一番の争点なのだが)、次は、公衆衛生の枠組みに準じた「論点」連関に沿って、医療法などの制度の改正から、労働環境の改善、生活様式の見直し等を検討することになる。
とはいえ、これから私が論じたいのは「実践目標」や「論点」や「解釈」ではなく、解釈の相違をもたらす「観点」についてだ。
(拙著『システム倫理学的思考』ではその点の考察が十分ではなかったためここで補足する)

©︎Y.Maezawa
重大なフェイク情報を除けば、混乱と対立は主として見解(解釈)の相違から生じる。そして見解の前提にあるのが観点だ。各人の観点が相違するのは当然であり、むしろ健全なことである。
問題は、観点の相違ではなく、観点が硬直化して見解が固定する結果、自分の見解が正解=正答であり、他の見解は誤解=誤答と考えてしまうことである。
過去一年間の経験から見えてきたのは、コロナ禍のような事態の渦中では、昨日には正解と見えた方針や行動が明日には悪手に転じてしまうことだ。
とはいえ、この何が正解で何が誤解かがあいまいな状況、あるいは、そもそも正答と誤答の区別が意味を持たない事態は、じつは今回の新型コロナパンデミックに限った話ではない。人間の日常世界では各人によって解釈(見解)が異なる以上、それはごくありふれた状況であり事態である。
多義性に満ちた日常世界には、歴史上類似した前例はあるが、固定した正答もなければ誤答もない。
哲学者がコロナ禍の中で貢献できることは、むろん医療者や政治家に比べると限られている。それでも、「正解」への固執から生じる混乱と対立を解きほぐすために、見解(解釈)をめぐる「正と誤」の枠組みを根本から問い直し、組み換えることは、迂遠ではあるが、その数少ない貢献の一つだと言えよう。
以下では、「バイアス」という正解を前提にもつ観念の解明を軸にして考察を進めていく。
(なお、試論であるため典拠指示は省略する)
1) バイアスⅠ 日常的思考の偏向
©︎Y.Maezawa

「バイアスbias」は人間の思考に付き物と言われる。
語源は布目に対して斜めに切ること、つまり斜めの傾きだ。
それは文脈に応じて、本性上の傾向、個人の癖や偏執、先入観・先入見、
色メガネ・偏見・イデオロギー(階級意識)、統計学の系統的誤差のように
訳し分けられる。
©︎Y.Maezawa

このように多種多様のバイアスがあるが、そこには共通した意味合いもある。
何らかの正解があるという前提のことだ。
まずは正解=科学的真理から取り上げよう。
西欧の17世紀以来、数学や物理学をモデルとする科学的思考が登場し、20世紀の前半まで主流となった。
科学的思考が「真理」をめざすとき、その行く手を妨げる誤謬の元がある。それが人間の日常的思考の「偏向」である。これを「バイアスⅠ」と呼ぼう。
典型例はベーコンの「四つのイドラ」(虚像・幻影)に見られる。
(『ノブム・オルガヌム』 要約して示す)
©︎Y.Maezawa

一つ目の種族tribusのイドラは、
人類の感覚や精神に根ざした本性上の傾向である。
近いものは大きく、遠いものは小さく見える錯覚がこの例だ。
二つ目の洞窟soecusのイドラは、
個人的な環境と教育によって形成された性癖、習慣、狭い経験である。
これには井戸の中の蛙という表現がふさわしい。
三つ目の広場(市場)foriのイドラは、
人々が交際する中で言葉の不正確で不適当な使用によって引き起こされる。
噂話の流通がこの例だ。
四つ目の劇場theatriのイドラは、
伝承や学説を権威として無批判に盲信することから生じる。
この例は擬人的なものの見方をするスコラ哲学者だ。
人間は四つのイドラのせいで「こうだと思いこむ」と、それに合致するように現実を作り上げる。たとえそれに反する事例が現れても無視したり軽視したりする。
だから四つのイドラを取り除かなければ真理にたどり着けないわけだ。
統計学で以上の見地を受け継ぐのが頻度主義(無限回試行の確率計算)である。サンプルの選び方や真値からの推定量のズレによって系統的に誤差が生み出される。
これが「バイアス」だ。
日常的思考が「偏向」とされるのは、数学的思考と物理学的(=科学的)思考における「真理」が「正解」として前提されているからだ。曖昧な日常的思考に比べると、それらの真理はたしかに厳密であり精密ではある。だが、その根拠を探っていくと個々の研究者の直観に突き当たる。
科学的真理の場合、仮説に始まり、一定の単純で厳密な条件の下で、データ→関係・規則の発見→解釈の比較検討→テーゼをへて、当初の仮説の証明と検証にいたる一連の手続きがある。この仮説の背後には研究者の理論的関心がある。
ところが、
それが真であることは保証されていない。
他方、数学的真理とは、理念的対象としての数の世界で発見される種々の不変の関係・規則性である。
それらが真であることは構成可能性や、無矛盾性、美といった基準によって保証されている。
ところが、
数学的世界では日常世界を支える物理的条件が
完全に無視されているだけでなく、
基準の選択と正当化が数学者のセンスに委ねられている。
2) バイアスⅡ 日常的思考の傾向
20世紀の半ば、生物学や心理学、歴史学、社会科学が学問の世界で市民権を獲得すると、それまで主流であった数学・物理学モデルの科学的思考が局在化される。
その中で科学的思考と日常的思考の関係が問い直され、人間の日常的思考こそが現実=真実であり、そこからの抽象として科学的真理が成り立つという見方が広がる。
他方、統計学では頻度主義に対してベイズ主義が登場する。
これは事前確率という先入見を踏まえて予測とその修正を繰り返す確率論であるが、この背景には数学における形式主義と直観主義の対立がある。
科学的思考の土台が人間の日常的思考であるなら、日常的思考に見られるのは「偏向=バイアスⅠ」ではなく、「傾向」と言われるべきだろう。しかし、この傾向はあくまでバイアスと呼ばれ続ける。これが「バイアスⅡ」だ。その理由は後回しにし、先にバイアスの具体例を見ておこう。これを豊富に提供するのが行動経済学である。
(大竹文雄・平井啓編著『医療現場の行動経済学』東洋経済新報社、2018年)
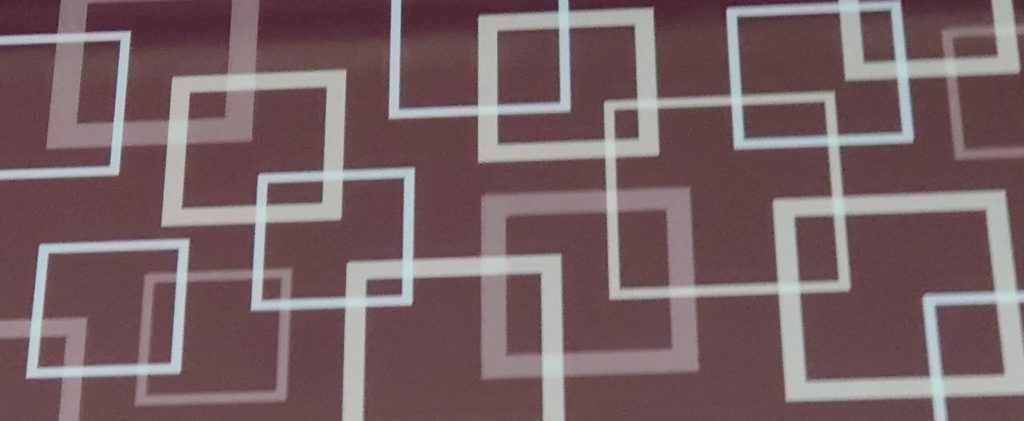
©︎Y.Maezawa
行動経済学は、伝統的な経済学のいう合理的な人間(ホモエコノミックス)像、あるいは利己的な個人観を非現実の抽象とみなし、その代わりに四群の傾向を指摘する。
それが「現状維持バイアス」「現在バイアス」「社会的選好」「限定的合理性とヒューリスティックス」である。
これら四群の傾向の原点(参照点)には自己の安定状態=正常性バイアスがある。
現状維持バイアスは
参照点を自分の現在の状態に置くことから生じる。このバイアスが働くと、確実なものとわずかに確実なものとのあいだで確実なものを選ぶ傾向(確実性効果)や、利得よりも損失を大きく嫌う傾向(損失回避)が発現する。また、同じ内容でも表現方法が異なるだけで意思決定に違いをもたらすフレーミング効果や、すでに所有しているものの価値を高く見積もる保有効果もある。
現在バイアスは
現状維持のうちで現在(時間意識)を参照点においたとき生じる。このバイアスが働くと、将来の利益を小さく見積もり、現在の楽しみを大きく見て優先する傾向(即時的快楽志向)が生じる。また、好まないことは計画しても実行を先延ばしする傾向も同様だ。
社会的選好のバイアスは、
人間が他者の利得に対しても関心を持つことから生じる。ここで社会的とは社交的=共同的という意味だ。
この種の選好には、他者の満足が上がることが自分の満足を高めることになる利他性、他者の親切な行動にお返しをする互恵性、所得や栄誉の分配が依怙贔屓に見られることを嫌う不平等回避がある。
限定的合理性とは
人々が合理的ではなく直感的に判断する傾向であり、ヒューリスティックスとは安易な近道によって意思決定する傾向のことだ。
前者の例は、サンクコスト(過去の埋没費用)へのこだわり、肉体的・精神的な疲労による意志力のにぶり、情報過剰負荷、選択過剰負荷、平均回帰に関する誤解、メンタル・アカウンティング(最初のデフォルトへのこだわり)等である。
後者の例は、利用可能な身近な情報に頼る傾向、似た属性だけから一般的に判断する傾向、最初の情報を参照点にするアンカリング効果(係留効果)、上中下のうち中央を選ぶ極端回避の傾向、同僚や隣人の意見や行動に引きずられる同調傾向だ。
以上の四群の「傾向」は人間の日常的思考の現実=真実である。
しかし、それが現実=真実であるなら、なぜ「バイアス」と表現されるのか。
その理由は、
制度設計者や政策立案者、各種専門家の見解が正解として
想定されているからだ。
経済を対象とする行動経済学だけでなく、これに基づく政策学的な「ナッジ」や「リスクコミュニケーション」の背後にも、人々の単純な日常的思考を正しい方向に誘導する、賢明な専門家や熟慮的市民の思考という前提が見え隠れしている。
3) バイアスⅢ 人間本性の傾性
それにしても、人間の日常的思考における「傾向=バイアスⅡ」はどこから由来するのか。
ベーコンのいう「種族のイドラ」や、行動経済学の原点である「正常性バイアス」に着目すると、その奥に透けて見えるのは人間本性の性向(本能)である。

©︎Y.Maezawa
この具体例はロスリングの『ファクトフルネス』(日経BP社、2019年)に見られる。そこに列挙されている十個の「本能」を要約して示す。
(なお、本能という表現には疑問があるがここで不問にする)
①分断本能:
正義か悪か、白か黒か、自国か他国かのように二項対立を求める。
②ネガティブ本能:
物事のポジティブな面よりもネガティブな面に注目する。
③直線本能:
物事がひたすら増え続けるとみなす。
④恐怖本能:
何らかのリスクを偏執的に怖がる。
⑤過大視本能:
物事の大きさや割合を勘違いしてしまう。
⑥パターン化本能:
ものごとを類型化する。
⑦宿命本能:
物事は未来永劫変わらないし、変わるはずがないとみなす。
⑧単純化本能:
すべての問題は一つ原因から生まれるとか、一つのやり方で解決されると考えてしまう。
⑨犯人探し本能:
何か悪いことが起こったとき単純明快な理由を見つけ、それを誰かの責任として追及する。
⑩焦り本能:
今やらないと取り返しがつかないと考えたり、遠い未来のリスクとなると他人事に感じたりする。
以上の十個の本能はただ並べられているだけだが、私見では二系列に分かれる。すなわち、
「分割」「パターン化」「過大視」「単純化」「犯人探し」の系列 と、
「ネガティブ」「直線」「恐怖」「宿命」「焦り」の系列 である。
このうち、例えば「犯人探し」本能はベーコンのいう擬人的なものの見方に関連し、「ネガティブ」本能は行動経済学の「現状維持バイアス」に対応している。
いずれにせよ、両系列の本能群は外部からの情報を選別するフィルターの役割を果たし、人間の「ドラマティックな見方」を生み出している。
ドラマティックな見方は人間本性の「性向」だ。
しかし、ロスリングによれば、その見方では「事実に基づいた世界」は捉えられない。だから「性向」はバイアスなのだ。これを「バイアスⅢ」と呼ぼう。
世界を事実に基づいて正しく理解するためには、自由か平等かのように一つの対抗軸だけで世界を理解したり、途上国と先進国、または貧乏人と金持ちのように一つの視点から世界を二つのグループに分けたりするのではなく、一人当たりのGDP所得のレベルに基づいて四つに分類する必要がある。
©︎Y.Maezawa

レベル1は一日1〜2ドルの極度の貧困、
レベル2は4〜8ドルの低所得、
レベル3は16ドルの中所得、
レベル4は32ドル以上の高所得
に当たる。
この所得レベルに応じて生活水準が向上する。
水の調達方法、移動手段、調理方法、料理(皿の数)、ベッドを比較すると、
変化の方向はどの社会集団でも驚くほど類似する。
これが「世界の本当の姿」だとロスリングは考える。
ファクトフルネスの思考法にも正解と偏った見方という枠組みが維持されている。
そしてその正解を支えるのが公衆衛生の専門家の観点「生存」である。
それに対してシステム倫理学では、人間の生は「生存」「生活」「人生の三つのレベルから構成されると捉える。
(『システム倫理学的思考』第6章)
この観点からすれば、たとえどんなに生存レベルが重要だとしても、人間の生全体をカバーしない正解は偏っていると言わざるを得ない。
4) バイアスⅣ 生命システムの傾性
©︎Y.Maezawa

以上の三つのバイアス論を比較してみよう。
まず、ベーコンのイドラ論では、
誤謬を生み出す日常的思考の偏向(バイアスⅠ)が四つに分類された。
しかし、その区分の理由は不明であり、直感レベルの把握に止まっていた。
また人間の本性に関しても心理的な錯覚が挙げられただけである。
次の行動経済学では、
日常的思考の傾向(バイアスⅡ)が詳細に列挙され、その原点として自己=正常性バイアスが想定された。
しかし、その正常性バイアスの基盤は解明されなかった。
三つ目の『ファクトフルネス』では、
日常的思考の傾向の基盤が人間本性の性向(バイアスⅢ)に求められ、性向=本能が詳しく説明された。
しかし、そこでも本能の根源はそれ以上究明されず、バイアスの起源は不明のままだった。
それでは、人間本性の性向(バイアスⅢ)の根源とは何か。
私見ではその答えは生命システムに求められる。
環境との関わりの中で外部から内部を区分し、この区分を維持し続けることでシステムが形成される。
内外の区分はシステムの本質であり、内部=自己の維持はシステムの内在的な目的である。
情報の面からいえば、外部の複雑な情報を縮減しつつ、取捨選択することで内部=自己が成り立つ。
とすれば、
生命システムの存立は、それ自体が環境から見たら「傾性」になる。
ここにバイアスの起源がある。
これを「バイアスⅣ」と呼ぼう。
生命システムの「傾性=バイアスⅣ」を根源として人間本性の「性向=バイアスⅢ」が発現する。
例えば、『ファクトフルネス』における「分割本能」の系列はシステムの内外区分の発現であり、他方の「ネガティブ本能」系列はシステムの自己維持の発現といえる。
とはいえ、このような対応づけはおよそ系統的(システマティック)ではない。
人間本性の性向を系統的に把握するには、人間の意味世界の全体を構成する論理に基づいた枠組みが必要だ。
人類は集団の中で対面的なコミュニケーションを通じて進化し、「心」と「社会」の構成を進化させてきた。
人間の世界を成り立たせるのは意味の解釈をやりとりするコミュニケーションであり、これは次の四つのステップを踏みながら、心の中で循環的に進行する。
すなわち、
外部情報を取捨選択する対外的ステップ、
選択した情報を解釈する対内的ステップ、
別の諸解釈と比較する対他的ステップ、
そして総合評価に基づいて意思決定する対自的ステップ
である。
この四ステップの循環プロセスを思考の枠組みに変換すると「四次元相関」の枠組みが現れる。
これが人間の意味世界をつらぬく基本論理だ。
(拙著『システム倫理学的思考』序章、第1章、第2章)
生命システムの自己=傾性(バイアスⅣ)は、人間の意味世界では、四次元相関の枠組みに対応して、自己=自分、自己=他者、自己=集団、自己=理念に分化する。
この分化が進展する中で十個の本能→四つのバイアス群だけでなく、注目されてこなかった数々の性向→傾向群が発現する。
例えば社会的選好でいえば、身びいき傾向とか、我が子に対する母親の無償の愛、ジラールのいう他者の欲望の欲望、呪術的傾向がそうだ。
5)バイアスⅤとバイアスⅥ 観点の偏重とバランスの傾き
©︎Y.Maezawa

「汝自身を知れ」は哲学の原点である。
この意味は何か。
私見では、自分の「観点」の本質と由来を知るということだ。
「観点」の基軸は「生命システムの傾性→人間本性の性向→日常的思考の傾向」である。この基軸は種々の条件によって特殊化される。
例えば、生活環境の中で培われた集団の生活様式と文化、この生活様式と文化を通じて育まれた人々の性格と人格、時代環境、世代意識、性別、年齢、生活水準、教育水準といった諸条件がそうだ。これらが複雑につながり合い、また時間的にループしながら絡み合う中で、一人ひとりの基本的観点(つまり幸福観や人生観などの思想)が形成される。
基本的観点(思想)とは、人生と社会集団における優先順位を決める「価値」基準である。
この価値もまた四次元相関に即して分化する。
すなわち、
対外的次元では 経済領域と個人の自由、
対内的次元では 共同領域と共助、
対他的次元では 公共領域と公正、
対自的次元では 文化領域と人間の存在、
にそれぞれ価値がおかれる。
(『システム倫理学的思考』第5章)
基本的観点は、先の諸条件のもとで、四次元のうちの一次元だけを偏重し、そこから価値の全体を捉えるところに成立する。この偏重によって人々の基本的観点が相違する。観点=価値の偏重を「バイアスⅤ」と呼ぼう。
人生と社会における価値の全体は四次元「相関」のバランスによって支えられる。例えば、経済と自由の次元だけでは集団は維持できない。また、現実の変化に合わせて「相関」のバランスを柔軟に維持しなければ、バランスは偏ったまま固定してしまい、人々は対立するばかりになり、集団は解体する。価値の四次元相関のバランスの傾きを「バイアスⅥ」と呼ぼう。これが正真正銘のバイアスである。
基本的な観点(思想)は現実の状況に応じて特定の観点を生み出す。
そして特定の観点同士の相違から、問題の「実践目標」や「論点」をめぐる見解の違いが生じる。
特定の観点(バイアスⅤ)は、正解を前提にした偏り(バイアス)ではなく、横並びの変異体(バリアント)であるにすぎない。しかし、それが現実の複雑さに柔軟に対応できず、自分の見解を正解とみなして固執するとき、見解が固定するによって四次元相関のバランスが傾くことになる(バイアスⅥ)。
四次元相関のバランスの傾きは、各人が自分の観点を維持しつつも、特定の問題に対する自分の見解をたえず他者の異なる見解と比較する中で、観点の偏重(バイアスⅤ)を弱めて相対化することによって回復される。
そのときバイアスⅥは消え、混乱と対立は解きほぐされるだろう。
最後に、以上の見通しをバイアス1〜Ⅲに適用してみたい。
©︎Y.Maezawa

バイアスⅠは 日常的思考の「偏向」である。
日常的思考はたしかに多義的=曖昧だが、それが偏向(バイアス)とされるのは、科学的・数学的思考の真理を前提にするからである。すでに説明したように、科学的思考の真理は、現実の複雑な条件を単純化し、精密に操作することによって保証される。
他方、数学が扱う理念的な対象の世界は厳密だが、物理的な時空条件を無視するところに成り立つ。だから、日常的思考の見地からすれば、科学的・数学的思考の方が逆に抽象的であり、偏向していると見える。とはいえ、実際は、どちらが正解でどちらが偏向ということではない。両者はそれぞれ一面的な変異なのだ。両者を並べて比較することで現実は多面的に浮かび上がる。
バイアスⅡは 日常的思考の「傾向」である。
©︎Y.Maezawa

傾向=現実=真実がバイアスとされるのは、制度設計者や政策立案者、各種の専門家の専門的思考を前提にするからだ。しかし、専門的思考が正しいことは無条件には保障されない。情報の多寡の差はあるが、事態をすべて見通せる者はいない。
人は観点(イデオロギー)を持つ以上、専門的思考も一面的である。
逆に、日常的思考の常識は長い年月を経て洗練されてきた知恵である。とはいえ、それは非常時には役立たず、パニックを引き起こすことがある。
とすれば、一方が正解で他方が偏り=誤謬ということではない。
両者のあいだで情報を透明化し共有化しつつ、妥協できる実践目標を見出すために話し合いを続けなければならない。
©︎Y.Maezawa

バイアスⅢは 人間本性の「性向(本能)」である。
本能によってドラマティックな見方が生じる。これが公衆衛生の「生存」の観点から「バイアス」とされた。
しかし、人間本性の根源である生命システム自体が傾性(バイアスⅣ)を持つ以上、何らかのバイアスを免れる人間はいない。ファクトフルネスの思考法も一つの見方であり、ドラマティックであるか否かは程度の差でしかない。
とすれば、残された道は一つ、多数の一面的なドラマティックな見方を集めて比較することだ。その中から「正解」ではなく、現実の多面的な見方が生じるだろう。
©︎Y.Maezawa

【おわりに】
ここまで「観点」をめぐって考察してきた。
以上を踏まえて、現実の流動性と複雑性に即した四次元のバランス思考を堅持しつつ、コロナ禍の中を共に生きていくことが望まれる。
論の結びとして、以上の見地を哲学の伝統のうちに位置づけてみよう。
哲学の歴史を広く眺め渡すとき、人々の日常的思考をめぐって大まかに四つの伝統が浮かび上がる。
一つ目の伝統は、
正しい論理学によって日常思考のバイアスを除去すべきだとする。
これが17世紀以降の西洋哲学の主流であり、20世紀の代表は論理実証主義だった。
二つ目の伝統は、
人間の日常的思考を現実=真実とみなし、その豊かさを味わい、それを前提にして対話による相互理解を目指す。
この代表が修辞学や解釈学だ。
三つ目の伝統は、
日常的思考同士の特殊性=バイアスを前提にしつつ、対話によって特殊性を克服して普遍的な境位を目指す。
ヘーゲル主義が典型だ。
四つ目の伝統は、
科学的真理であれ、日常的真実であれ、言語を使用する以上は固定化を免れないとみなし、言語そのものを断つべきだとする。
これが仏教を含めた東洋哲学だ。
システム倫理学はそれらとは一線を画す。
数学的・科学的思考であれ、政策的・専門的思考であれ、日常的思考であれ、形而上学的・宗教的思考であれ、すべては対面的コミュニケーションを舞台とする人間の思考のバリエーションである。
そうである限り、正解対バイアスという枠組みではなく、バリアント同士の比較による四次元相関のバランスの回復という枠組みが要請される。
この四次元バランス思考は、
流動的な現実に対応するために、
衆知を集め、自説を相対化し、
実践的な目標を共有しながら、
共に生き抜いていくことを可能にする。

©︎Y.Maezawa
(編集:前澤 祐貴子)