交流の広場

病と老と死を超克する
文学的ストイシズム
二つの魂の
霊的な交わりに魅せられて
演劇研究家
遠藤幸英
文学的出会い、あるいは霊的人間どうしの出会い
最近のことだが、積読になっていた(『薔薇の名前』や『フーコーの振り子』などで日本の映画ファンや小説愛好者にも知られる)哲学者・作家Umberto Eco著Interpretation and Overinterpretation (1992年、邦訳1993年『読みと深読み』)をようやく読み上げた。これはエーコの単著ではなくエーコによる連続講義(1990年)とそれに続くシンポジウムで三人の論者、Richard Rorty(哲学、比較文学)、Jonathan Culler (文学評論)、Christine Brooke-Rose(小説、文学評論)が寄せた重厚なコメントのコレクションである。
エーコは哲学者のデリダに由来する「デコンストラクション」が文学批評に影響を与えた結果、「深読み (overinterpretation) 」こそが正しい批評的姿勢だと言わんばかりの風潮に対して異議を唱える。とはいえエーコが文芸作品の作者の意図を重視すべしなどというはずもない。<作者の死>は半世紀も前にロラン・バルトによって宣言されたのだから。エーコが示唆するところでは、古代ギリシア以来の西洋思想の伝統に依存するのではないことはいうまでもないが、それを構成要素の一つとして含む人間の膨大な知と言説の体系を考慮せずには作品の解釈(読み)は成り立たない。
しかし、このエーコの主張は常人にはそうやすやすと実践できそうもない。たとえば彼の小説『薔薇の名前』。早い話この小説はあるベネディクト会修道院で連続しておこる奇怪な事件の解決をはかる探偵小説である。だが、過去と現在の言説が縦横に散りばめられていて、それはまるでアルゼンチンの幻想小説の大家ホルヘ・ルイス・ボルヘス (1899–1986) が言葉で紡ぎあげた万巻の書物を所蔵する迷宮図書館である。目が眩んで仕方がない。

私見混じりの前置きはこのくらいにしたい。私が特に興味をもったのはコメンテーターの一人クリスティン・ブルック=ローズChristine Brooke-Rose(1923–2012)が 自身の発言を“Palimpsest history” と名づけたことだ。ご承知のとおり紙が発明される以前は(水草を材料とする)パピルス(古代エジプト文明圏)や羊の皮から作られた羊皮紙(小アジアからヨーロッパに至る地域)が主たる書写材料であった。当然羊皮紙は量産できるわけでないので繰り返し使わなくてはならなかった。新たに記録する場合、羊皮紙の表面を刃物などで削ることで白紙をこしらえたわけである。(元の文字を)「削りとってψαω [psao]」「再度πάλιν [pάlin]使用することから<パリンプセスト>と呼ばれることになったそうだ。この種の古文書は(欧米などの)博物館でよく陳列に供されている。
このパリンプセストという語が私自身の関心事を思い出させた。2年前、世阿弥に代表される能(旧称は猿楽・申楽)が汚れと聖性を両義的に纏っているという趣旨でエッセイをまとめたことがある。能が長年月に渡る自己練磨を通して達成した霊性を帯びた美の背景には出自もあやふやな放浪芸人であるがゆえにかつて負わされていた社会的スティグマstigma(烙印)がかすかに読みとれる。それはまるで書いては消す事を繰り返した羊皮紙にかろうじて残る記述の歴史を連想させる。“The Stigmatized Nô Players and the Dance of the Heavenly Maiden”, The International Journal of Arts Theory and History 15-2, 2020, peer-reviewed: PDF-open access).このエッセイは常時閲覧可能。

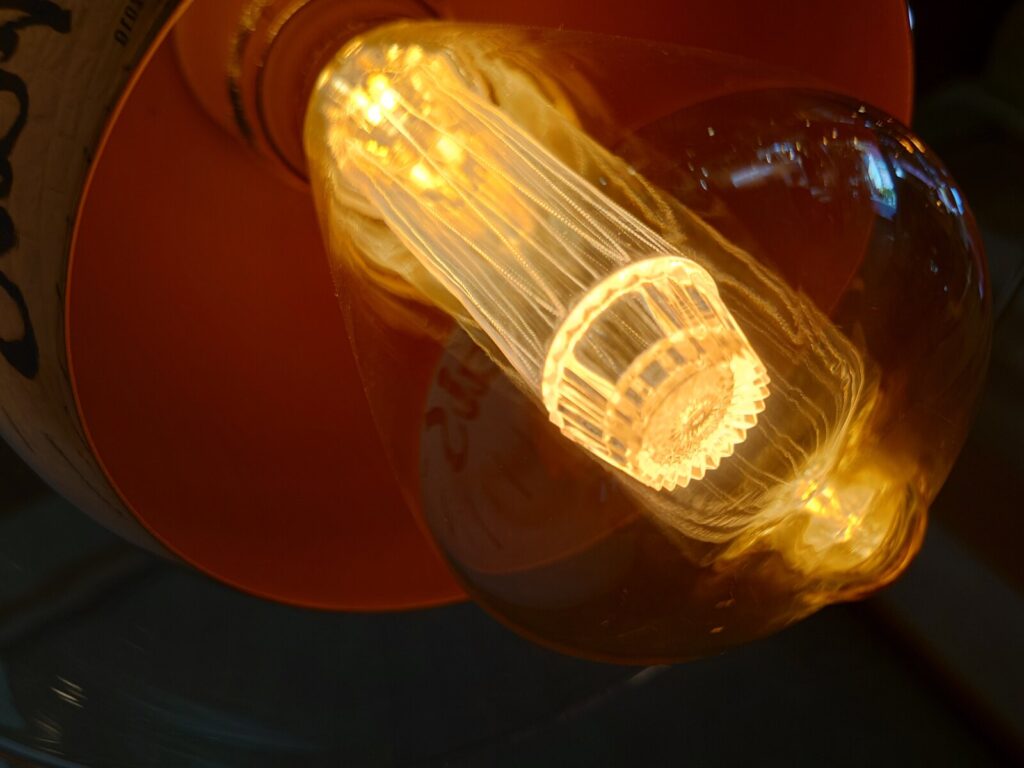


私はブルック=ローズの小説も(先にあげた短いエッセイ“Palimpsest history”以外の)文学評論も読んだことがない。今回あれこれ調べていて彼女が70代から89歳で亡くなるまで長年どうやら神経系の疾病が原因の視力喪失と脊椎系(?)の麻痺に耐えていたようだと知った。またラバテ教授によると、老年期を迎えるよりかなり以前から死に対する心構えについて考えはじめていたらしい (p. 198)。最後の自伝的小説Life, End of(2006年)は日本的私小説とはまるで異質の構成で、自身の晩年を反映させながら複眼的視点を展開しているとのこと。表題からして通例の語順を倒置させる点で特異である。出版時の彼女は失明や麻痺に加えて80歳代という高齢などの問題を抱えていて完全に自立して生活できる状況ではなかったはず。にもかかわらず言語表現の実験を楽しんでいるかのように<生>を不可避の<死>より重視しようという強い意志を表明する。病と老いと寿命とに対峙してくじけない精神は清々しいストイシズムの権化のようだ。彼女の(ラバテ教授のいう)「ストイシズムに裏打ちされた老後の生き様」に興味をそそられるのでぜひKindle版を購入したいと思う。
話が前後してしまうが、今回の私のエッセイはブルック=ローズの没後6年を経過した時点で執筆された(つまり時の経過にともなって熟成したかのような)追悼文(と私には思える)を偶然見つけて読んだことから生まれた。筆者のラバテ教授は人づてに学識、人格ともに人並みすぐれた人物だと聞いている。私は事前にお二人の親しい関係を承知していたわけではない。ラバテ教授はブルック=ローズより26歳年少である。親子の年齢差があるのだ。この追悼文を読んでいると両者の出会いは運命的とも思えてくる。先走って言うと、その文章は知の盟友の死を悼み、その文学的成果を顕彰すると同時に心が通い合う魂に向けた「恋文」だという気がしてならない。
1970年代を迎えてすぐまだ二十歳そこそこの院生であった教授は(現在パリ第8大学と称される)ヴァンセンヌVincennes大学(正式名ヴァンセンヌ実験大学センター)において修士課程、ついで博士課程に学ぶ。指導教授は当時フェミニスト文学批評の分野で広く世界に知られたエレーヌ・シクスーHélène Cixous(1937年生まれ)。ヴァンセンヌは 1968年のパリ五月危機(五月革命)という苦難の時期を経てようやく誕生した(ソルボンヌに代表される古典的、伝統的教育理念を脱して)入学資格やカリキュラムの面で革新性を打ち出した高等教育機関である。この新鮮な知的土壌でラバテ教授は20世紀前半に登場し、文学の普遍性を追求した欧米の作家・詩人たちJames Joyce、Ezra Pound、Hermann Brochを主題にして論考を進めていた。
ちょうど同時期にブルック=ローズがシクスーの推薦でアメリカ文学科の教員となる。(アメリカ詩人パウンドに造詣が深いことが幸いしたのだろう。)就職の件では恩のあるシクスーの政治的党派性の強いフェミニズム思想とは一線を画したブルック=ローズ。彼女の最大関心事は文学表現にあるようで、早くから文飾という伝統的装飾性を排して文学言語のミニマリズムを極めようとするアイルランド出身の作家サミュエル・ベケットに共感を覚え、高く評価していた。一方、若き日のラバテ教授は同じくアイルランド出身で言語表現の実験的創造を目指すジョイスに強く惹かれていたが、それはその後も基本的に変わらないようである。余談ながら、2020年3月ラバテ教授を主賓にしてジョイスをめぐるシンポジウムが京大で開催予定だったが、コロナ禍のためか中止になっている。
院生時代のラバテ教授は文学の極限を探る三人の作家パウンド、ベケット、ジョイスを接点にしてブルック=ローズと親しくなる。詩の原点を求めるパウンドに関して両者の評価は一致していた。だが当初ブルック=ローズはベケット贔屓でラバテ教授はジョイス贔屓と食い違いがあった。文学表現の先端を探る思いの強さがブルック=ローズと共通すると直感した若き日のラバテ教授はジョイスの素晴らしを力説した。その思いが通じて二人は文学論に熱中することになる。文学を通じた熱い親交の始まりである。
ラバテ教授の観察ではブルック=ローズは19世紀西欧文学を特徴づけるリアリズムを評価しなかった。ジャーナリズムならいざ知らず、文学が現実世界を生きる<等身大>の人間像を描いたところで人間性の真実は見えてこないと考えていたようだ。作中の<私>が生身の私と等価であることが納得できないのだ。パウンド、ベケット、ジョイスは日常生活や社会生活上の喜び、不満、憤りを語りはしない。私的、個人的感覚とは別次元の、平常心では向き合うことのできないある種極限性を帯びた生き様、死の予兆がつきまとう生存状況と対峙することが重要だとブルック=ローズは考えていたにちがいない。この追悼文の形式をとる<恋文>をしたためたラバテ教授もそういう生に対する彼女の姿勢に強い共感を覚えている。二人の間には1960年代末の最初の出会いから(おそらく断続的ではあれ)彼女が亡くなる2012年まで40年に渡る親交の歴史がある。さらにその後2018年に公表された彼のエッセイまで6年が経過した。実はこの時間の経過があるからこそラバテ教授はブルック=ローズとの霊性の色濃い魂の触れ合いという思いをいっそう深くしたのではないかと推測する。

老いと死の予兆を乗り越えて
ラバテ教授のエッセイを読んで強く印象に残るのはブルック=ローズが<書くこと>にこだわり続けたことだ。小説家であり文芸評論家であり続けた彼女。そういう社会的肩書きは単なる職業的位置づけを大きく超える意義をもっていたのではないか。書くことを通して生の喜びや悲しみを深く心に刻んだ。とはいえ、これは物書きに共通のことで取り立てて言挙げすることはないだろう。しかし彼女の場合<書くこと>は特別な意味を帯びている。その営為はまず第一に<生きること>であり、同時に現世的死を迎え入れる準備をすることであるように思える。こういう彼女の生き様にラバテ教授は彼女特有のストイックな性格を読みとる。
このように書くことに対するこだわりを暗示するエピソードをラバテ教授が末尾近くで紹介している (p. 198)。先に触れた自伝的小説Life, End ofの出版後間もない頃ラバテ教授はフランス南部のアヴィニョンで隠棲生活を送る彼女を訪問した。目が見えない上に下肢の麻痺を負う彼女は愛用の机を前にして車椅子に座っている。ナースヘルパーが意地悪な人で、手元に置いてあるはずのメモ帳とペンを隠したと必死に訴える彼女。筆記具は生きることが書くことと同じだと考える彼女にとって命綱なのだからそれも当然だった。ラバテ教授は彼女のすぐ側に置かれたその筆記道具を手に持たせる。真っ白なページ。いやメモ帳の最初のページのみ判読不可能な書き込みがあるのを除けば全ページが未記入のままなのだ。ところが彼女は「余白がないから書けない」と言う。
だが、実際は白紙である。文字がすでに書き込まれているか、そうでなければ(劇的描写法で知られる)バロック絵画調の絵柄が刷り込まれていて白紙じゃないと言いはる彼女。そのうち白紙のページに(フェルトペンではなく)指で<見えない文字>をなぞり始め、一編の見えない手紙文に仕上げて音読する。ラバテ教授は驚愕したが、彼女によれば、その手紙は妹から届いた恨みごとを連ねた手紙らしい。しかしその妹は確か十年前に亡くなったはず。にもかかわらず、この文面は間違いなく妹の語り口だと主張する。つまり自分は妹の手紙をでっちあげたのではなく、そのまま読んだだけだと言うのである。
普通ならこれは妄想にとりつかれている人の発言。まさに狂気の沙汰と判断されるだろうが、ラバテ教授は別の解釈をする。自伝的小説を書いても主人公を作者とはほとんど無関係とも言えるほど距離を置いて描写するブルック=ローズである。彼女は見えない文字を使って小説を書いているのだと判断したのである。彼女には見えると言う例のバロック風のミニ絵画も例の手紙も、そのほかメモ帳をくまなく埋め尽くす見えない文字は全て彼女が形而上的に書き込んだものなのだとラバテ教授は理解する。多種多様な言説と人物像を想像、創造する才能に恵まれたブルック=ローズを目の当たりにして誰しも驚異的な知識と想像力を発揮する思想家・作家であるウンベルト・エーコを連想せずにはおれないのではないだろうか。ボルヘス的迷宮図書館の主であるまいか。
ラバテ教授は彼女が手にしたメモ帳を次々に繰ってみる。すると見えないはずのミニ絵画や文字が浮かび上がる。「どの文章も(彼女ではない)<他者>がしたためたものである。作家としての彼女があたかも自分の脳に文章を書き込んだかのように、それをすらすら読み上げる事実には驚きを禁じえない。現実的には深刻な神経系の病に苦しんでいるせいで昔読んだ手紙類や偶然目にした図像などが幻覚としてあらわれただけである。それでいながら彼女は才能溢れる正真正銘の小説家だったのだ」(p. 198)。小説、詩、文芸評論などを<書くこと>こそが老年期に罹患した難病の耐え難い心身の苦痛と死の不安を和らげ、それとくじけずに向き合う勇気を与えたのだ。そうラバテ教授は理解する。
彼女の場合、書くことは<言葉遊び>と切り離せない。まだ難病とは無縁だった若い頃から彼女は小説や評論に言葉遊びをさかんに組み込んでいた。それが彼女の文学的<実験>であったのだ。彼女の老年期から振り返ると若い年代から<死>と対峙する、いや柔軟な心構えで死を迎え入れる準備をしていたのだろうとラバテ教授は言いたいのではないだろうかと私には思えてならない。
文学、いやむしろ<書くこと>に真剣に向き合うブルック=ローズは<生あるものの必然の死>を心乱すことなく受容する意義を理解できるのだ。この心構えはブルック=ローズが生涯をかけて構築した彼女一流のストイシズムだと言えるだろう。老い、失明と麻痺を伴う難病に関するくだりは鬼気迫るものを感じさせると同時に読者に感動を呼びおこすはずだ。

晩年のブルック=ローズは時として気弱になることもあったらしい。病魔の苦痛から最終的に解放してくれるのは親友であるラバテ教授だと彼女が当人に向かって言うことがあったそうだ。そんなときラバテ教授がいうセリフは決まっていた。「文学的処刑執行人」なら進んで務めましょう。」この返答を介して二人に笑いが起こる。<言葉遊び>の重要性と効用を熟知するブルック=ローズとラバテ教授だからこそこういうブラックでないユーモアが意味をもつのだと思える (pp. 198 – 199)。
小説『薔薇の名前』とその映画版で広く一般に知られるウンベルト・エーコの文学の解釈をめぐる議論に触れたのは最近のこと。それがきっかけとなって、歴史のみならず広く物語の本質にかかわる<上書きによる意味の多重化>を論じたブルック=ローズのエッセイ “palimpsest history”、さらにそこからラバテ教授が書いた<恋文>同然と言いたくなる<追悼文>へと私は導かれた。自己をきびしく律する人間の生き様に触れて身が引き締まる思いがする。が、同時に<生きること>の喜びのようなものを感じさせられ、感謝したい気持ちにもなる。霊性を帯びた二つの魂の間に交わされた言葉に接したのだからそれも当然だと心底思える。

(編集: 前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。