活動の実績
老成学研究所 > 初代所長 森下直貴 作品群(2018 09〜2022 12) > 老成学事始 > 【老成学事始】Ⅶ エイジズムをいかに乗り越えるか 森下直貴

©︎Y.Maezawa
老成学事始 Ⅶ
「エイジズム」をいかに乗り越えるか
—半世紀前の先駆者たちに学ぶ—
老成学研究所 代表
森下直貴
はじめに
1970年代の前半、高齢社会に突入したフランスと日本と米国において、今日に通じる「老人問題」を扱った書物が相次いで刊行された。ボーヴォワールの『老い』(1970年)、有吉佐和子の『恍惚の人』(1972年)、ロバート・バトラーの『老後はなぜ悲劇なのか』(1975年)がそれだ。三冊それぞれの詳細については「老成学研究資料」や「私の本棚」で紹介している。
以下ではそれらを踏まえ、「老人問題」を枠づけているエイジズム、つまり〈老い=無価値〉および〈老人=邪魔者〉とする老人差別をいかに乗り越えるかという観点から、それら三冊の見解を比較する中で、老成学の支柱となるべき視点を探り当てたいと考える。
最初に、ボーヴォワールの『老い』(1970年)を取り上げる。
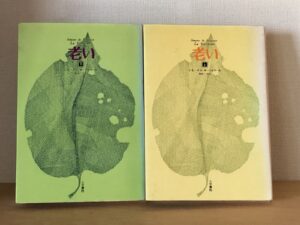
ボーヴォワールは「老い=不幸」という常識をたえず産出するエイジズムを鋭く批判する。そのために、老いの観念を構成する矛盾した態度や幻想をあぶり出しつつ、その背景となる事情を抉り出す。こうして露呈されたのが、生物学的事実としての〈老い=不可避的な衰退〉、社会集団の存続目的の機能的価値(生産性)、特権階級の老人と被搾取階級の老人の差異、そして工業文明の非人間主義である。
ボーヴォワールはエイジズムの外側だけでなく内側にも視線を向ける。それが老いの内的時間意識の現象学的分析だ。この分析から浮かび上がるのは、老いを実感できない現在、凝結した過去、短く閉じられた未来という不安の時間構造である。この不安の意識の中で生じるのは、過去の取り戻しとその挫折による徒労感や倦怠感であり、未来の有限性と切迫からくる焦燥感、無力感、屈辱的な落伍感、孤独感である。そこにさらに貧困状況が加わると、不安はいっそう激化し、最終的には生きる意欲が失われる。
当時、エイジズム文化が社会の隅々まで浸透し、老人に対する無関心が横行した結果、老人は貧困と非人間的な境遇の中に放棄されていた。そのことに激しく憤るボーヴォワールは、老人が人間らしく生きるために、貧困に対しては社会変革を、生きる意味に関しては実存の投企を提案したのだ。
ボーヴォワールは、医学・生理学から社会科学、人文学を総動員してエイジズムの論理構造、すなわち実態と背景と内的意識の連関を浮かび上がらせた。この論理構造の解明が重要なのは、それを念頭に置くことで、いかなる論点をどのように論じればいいかという思考の道筋が示されるためだ。とりわけ老いの内的時間性の哲学的分析は先駆的な試みであり、これを通じて老人の内的世界が初めて照らし出された。
しかし、ボーヴォワールの思考には実存主義とマルクス主義に立脚した人間主義の問題点もまた露呈している。
まず、〈生物学的事実=老い〉を一律に固定しているため、老いの深まりに応じたステージが設定されていない。次に、社会集団の存続目的に基づく機能的価値を問い返し、別の可能性を対置するまでに至っていない。イデオロギーの観点が強すぎる。さらに、老いの時間性の捉え方が個人の直線的な時間意識に限定され、個人を超えたライフサイクルの観点が欠如している。最後に、実践的に提案された一方の社会変革では具体性に欠け、他方の実存の投企では目標を追求する個人の活動のレベルに留まっている。
次に、有吉佐和子の『恍惚の人』(1972年)を取り上げる。

有吉の小説は、高齢化が進展する当時の日本社会の中で、介護する側の家族(とくに嫁=妻)の視点から「老人問題」を身近な事柄として描いたものである。
その中に老い=呆けをめぐる三つのイメージが登場する。基本は〈老い=呆け=恍惚〉である。それをめぐって〈老い=呆け=嫌悪=絶望〉が生じ、さらに絶望から〈老い=呆け=神・幼児〉の幻想が派生する。
〈老い=呆け=恍惚〉のイメージの源泉は〈呆け=精神病〉とする精神医学モデルである。有吉はこのモデルに依拠した老人福祉行政の実態をリアルに描いている。ここが小説の白眉とも言える箇所だ。そこから垣間見えてくるのは、老人にとって家庭で介護されるのが一番幸せだと一般にみなされ、老人を収容する施設が乏しい中で、呆け老人の最後の頼みの綱が精神病院しかないという現実である。共働きの主婦の当惑と憤りと絶望感が直に伝わってくる。
この小説を一貫しているのは〈老い=呆け=恍惚〉に対する〈絶望〉である。それによって〈老い=呆け=恍惚〉というイメージだけが一人歩きし、〈老い=呆け=嫌悪〉という暗澹たる印象が世間に広まった。とはいえ、この小説のおかげで「老人問題」の深刻さが人々の胸に深く刻まれ、その後の改善の取り組みを刺激し続けたことも忘れてはならない。『恍惚の人』は時代の優れた証言者なのだ。
他の二冊に比べると、有吉の場合、小説という表現形式の問題を差し引いても、エイジズムを批判し乗り越えるという視線が欠けている。むしろ、エイジズムの常識が問い直されることなく、人々の意識の内側からそのまま拡大再生産されている。しかも、焦点はどこまでも家族(とくに嫁=妻)の思いに置かれ、老人自身の思い(つまり戸惑いや生き続ける目的)が欠落している。だから老人自身が老い方を問い直す方向性は出てこない。しかし、それが1970年代初めの日本人の意識だったということだ。
三番目は、ロバート・バトラーの『老後はなぜ悲劇なのか』(1975年)である。

バトラーによれば米国の老人たちの生活は〈悲劇〉と表現するにふさわしい。
彼はその悲劇を生み出すエイジズムの実態を克明に描いた上で、貧困を皮切りに、年金、住宅、サービス、労働、教育、医療、介護施設など、老人生活の現状を具体的かつ詳細に分析する。
とくに精神医学界の現状に対する批判は、彼自身の専門分野であるだけに鋭い。ここで否定されているのが、『恍惚の人』も前提にしていた精神医学モデルである。
バトラーは以上の網羅的な現状分析に基づいて、社会改革のプログラムをきめ細かく設定し、そこから制度を設計し、政策立案にまでつなげている。それだけではない。さらにプログラムを実現するための政治活動の綱領まで周到に用意したのだ。
エイジズムは外面の制度ばかりでなく、人々の内面の意識にまで浸透している。そこでバトラーは「内なるエイジズム」を克服するための提言を行なっているが、その内容は老人が長生きすることの意味を正面から問い直すものだ。人生の最期まで成長するためには(プロダクティブ・エイジング)、不快な現実や不完全さを受け入れ、アイデンティティを固定することなく、従来の生き方を変えなければならない。
生き方を変えるためには、老人を研究してその世界観を内側から知る必要がある。ボーヴォワールと違い、バトラーにとってその核心はライフサイクルの経験である。結局、老人が長生きする意味は、後続世代に豊かな文化を引き継ぐことにある。若い人に人生を学んでもらうために老人世代がいるのだ。
*
バトラーの見地はほぼ50年後の今日でも目標とすべき水準にある。彼の慧眼には瞠目させられるが、そこには看過できない問題点も含まれている。それは端的に言えば「政治的正しさ」のリベラリズムの危うさと生産主義の偏りである。
バトラーは老人差別の文化を否定するために「エイジズム」の名称を作った。しかし、その「エイジズム」の視線には「政治的正しさ」を掲げるリベラル思考がまといついている。正しいか正しくないかの二分法からは不要な分断が生じる。世代間の対立より老人世代を含めて全世代の協働と共生をめざすべきではないか。
エイジズムを乗り越えるために、バトラーもボーヴォワール同様、老人の生産的な活動を推奨する。この「生産性」を裏付けているのがバトラーの老年精神医学である。しかし、バトラーのように老いを疾患やうつ病から切り離し、健康と長寿に限りなく近づける限り、老いという事実そのものが意味を持たなくなるだろう(私見では、老いをエントロピー概念に比定し、生命システムの修復機能の柔軟性の低下として捉える)。何れにせよ、「生産的であること」にこだわると、生産的な活動のできない老人の居場所がなくなる。
「生産的であること」と「生産的でないこと」の両方を包摂するためには、老いの深まりに応じたステージを設定するとともに、生産性とは別の原理を用意する必要がある。その候補として注目できるのは、たとえ片方が黙っていても、あるいは不在であっても、受け手の側の解釈によって成り立つようなコミュニケーションの見地でだ。
このコミュニケーションの見地に、バトラーが注目したライフサイクルの経験をつなげてみるとき、世代としての責任という思想が誕生する。この世代の思想にはライフサイクルの周期性だけでなく、同年齢集団の同時代性や、親子の系譜性も組み込まれることから、老いの価値と老人の役割が明確になることが期待できる。若者の世代は先行する老人の世代から人生を学ぶのだ。
最後に、ここまでの考察をまとめて結びとしよう。
ボーヴォワールは『老い』の中でエイジズムを正面から問題にし、その論理構造の解明した上で、それを踏まえて乗り越えるための社会変革と実存の投企を打ち出した。ただし、社会改革は具体性に欠け、実存の投企は個人の時間意識に限定されていた。
有吉は『恍惚の人』の中で老人を介護する家族の視点から「老人問題」をリアルに描き、当時の日本社会に衝撃を与えた。ただし、有吉には「老人問題」の背後にあるエイジズムを問題とする認識は薄く、時代の優れた証言者にとどまった。
バトラーは『老後なぜ悲劇なのか』の中で、エイジズムを乗り越える実践的なプログラムを具体的に提案した。とりわけ老人が長生きする意味を問いかけ、その答えを世代の継承に見出した。ただし、バトラーの提案には政治的リベラリズムの危うさと生産主義の偏りが含まれていた。
以上、半世紀前の先駆者たちの思想を検討した結果、エイジズムを乗り越えるために必要とされる視点として、少なくとも以下の三つが浮かび上がった。
すなわち、老いの深まりに応じた三ステージ、解釈をやりとりするコミュニケーション、それに世代としての責任である。
前二者については「老成学事始シリーズ」の中ですでに言及している。次回は世代の思想を掘り下げてみよう。(次回に続く)

©︎Y.Maezawa
(編集:前澤 祐貴子)