活動の実績
老成学研究所 > 初代所長 森下直貴 作品群(2018 09〜2022 12) > 日本哲学 > 井筒俊彦の東洋哲学とは何か No.1 :森下直貴
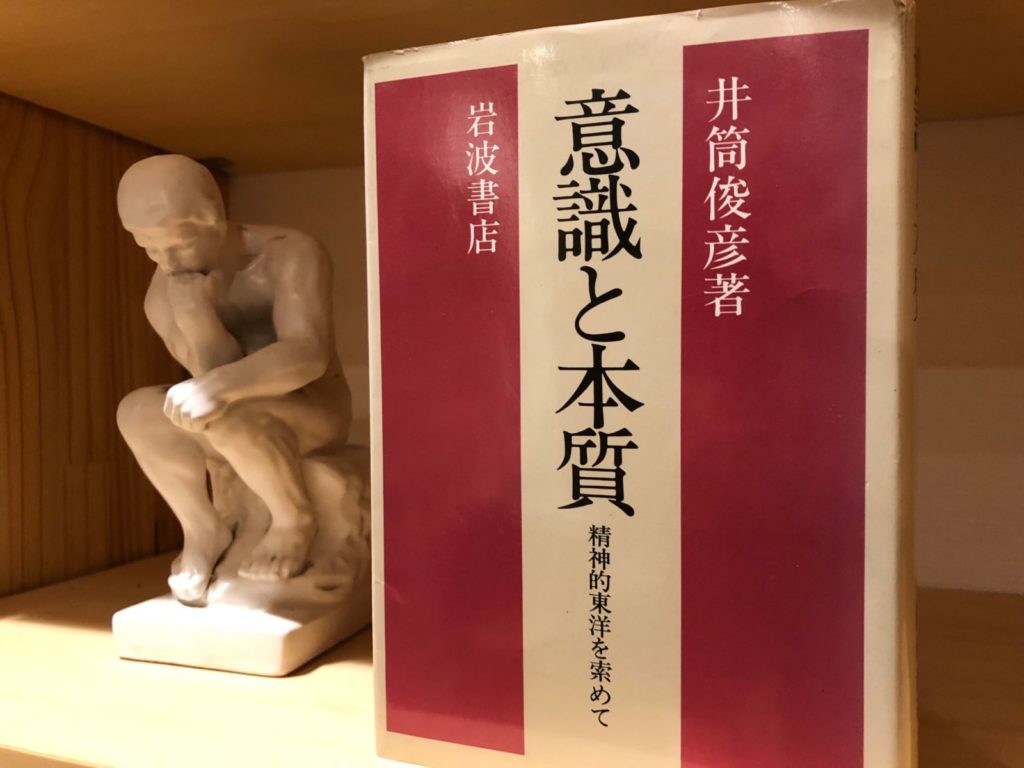
©︎Y.Maezawa
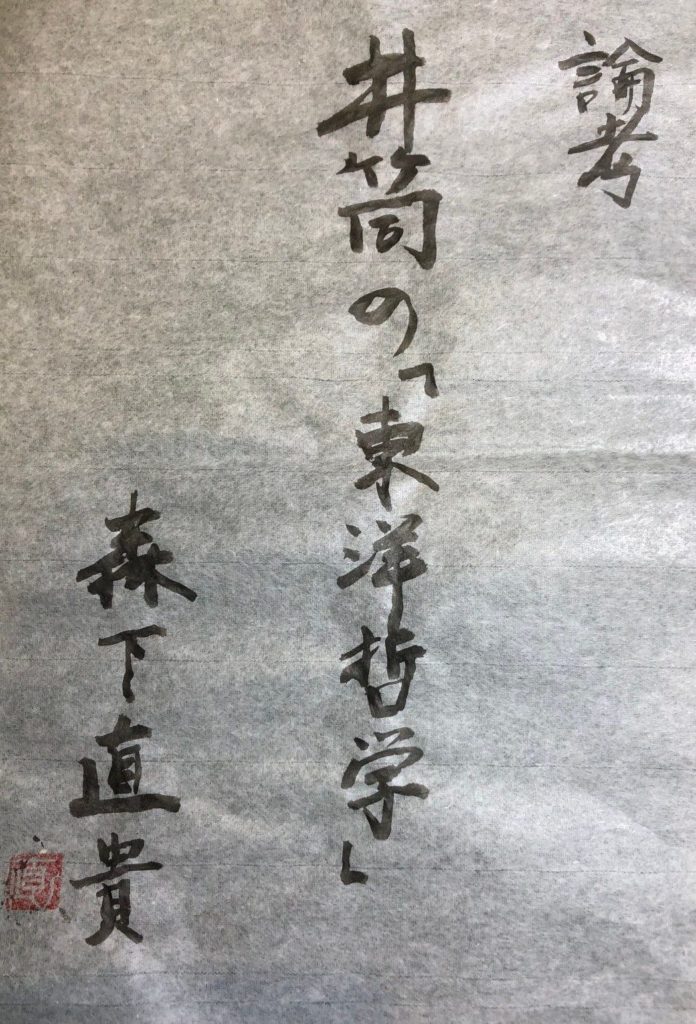
井筒俊彦の「東洋哲学」とは何か
日本形而上学と21世紀リアリティ
老成学研究所 代表 森下直貴
井筒俊彦の「東洋哲学」は形而上学である。それは、日本の形而上学の伝統の中でいかなる位置を占めているのか。そしてまた、21世紀のリアリティの変容の中でいかなる意義を持ちうるのか。この論考では井筒の代表作『意識と本質』を取り上げ、その内容を精査した上で、私自身のコミュニケーションシステム理論の見地から問いの答えを探る。全4回。
第一回 共時的構造化の方法
井筒俊彦(1914〜1993)は、イスラム哲学の世界的な権威であっただけでなく、日本の読者にとってはそれ以上に、独自の方法論に基づいて茫漠たる「東洋哲学」の本質を把握し、世に知らしめた稀代の碩学であった。二〇数ヶ国語を操る天才だったから、もともと外国語の著作や論文が多かった。訃報に接したフランスの哲学者デリダは井筒を知の巨匠と呼んだ。
それから二七年になる。最近ではようやく日本語版全集が刊行され、彼の哲学の全体像が明らかになりつつある。哲学の同行者にとって井筒俊彦の東洋哲学を論じることは、いつか果たさなければならない宿題だといえる。
私はこれまで彼の代表作である『意識と本質』(岩波書店、1983年)を三度読んだ。一度目は一九八四年、残念ながら東洋哲学の奥深さに圧倒されるだけで理解には程遠かった。二度目は忘れもしない二〇一一年、井筒の思想の大要は掴めたものの、自分の見地が未完成だったため思うように論じ切ることができなかった。そして二〇二〇年の今回、ようやく手にした私自身のシステムコミュニケーション理論の見地から、彼の東洋哲学を「日本哲学」の中に位置づけてみたいと考えた。
*
「東洋哲学」とは、井筒の考えに沿っていえば、意識の深層次元に踏み入ってリアリティを捉える思考の総称である。東洋は一般に、中東のユダヤやイスラムから、インドを経て、中国や日本にまたがる地理的な概念である。だが、井筒の考えでは、意識の深層に踏み込むかぎり、「精神的東洋」は西洋にもあることになる。その東洋哲学はリアリティの根拠を探求するから、すべて形而上学である。
「形而上」の出典は『易経』の繋辞伝上12の「形而上とはこれを道といい、形而下とはこれを器という」である。文字通りにとれば、我々にとって見えるものはすべて形を持っており、この形あるものを上から成り立たせるのが道、下から成り立たせるものが器ということになる。上の道や下の器をめぐっては種々の解釈がありうる。例えば朱子は道=理、器=気と解釈した。
他方、西洋のアリストテレスの講義録に『自然学』があり、その後続の束に『メタフィシカ(meta physica)』の名称が与えられた。そこでは事物の「がある」や判断の「である」など、種々の「ある」が統一的に論じられていたことから、存在論(ontology)と呼ばれた。存在論は中世以降のキリスト教世界では霊魂・宇宙・神の存在を論じ、神学の土台となった。
そのメタフィシカが明治の日本において東洋の伝統(形而上の理や真如)と結びつけられ、「形而上学」と訳された(井上哲次郎編『哲学字彙』1881年)。「東洋哲学」を最初に打ち出したのも井上哲次郎であるから、井上の仕事を井筒は時を隔てて引き継いだことになる。十九世紀の西洋哲学の中で育った井上の「東洋」は、西洋に対する地理的空間的な概念だった。二十世紀の世界哲学を咀嚼した井筒との違いは、「日本哲学」の成熟の観点からみて興味深い。
*
西洋哲学の場合、ヘブライズムとヘレニズムを押さえれば全体像が浮かんでくる。ところが東洋哲学ではそうはいかない。地理的に広がるだけでなく、その根は深く、歴史も長い。だから、これを有機的な統一体として論じるにはどうしても知的な操作が必要になる。それが井筒の「共時的構造化」だ。
共時的構造化とは、多様な哲学伝統の時間軸を取り払って一つの理念平面の上に写し、多重の構造の中に思想のタイプを位置づける方法論である。共時的構造化の枠組みは次の三本柱によって支えられている。
第一の柱は、ソシュールに始まる二十世紀の言語哲学を踏まえた意味分節理論である。この見地では、目に見える存在者の世界(リアリティ)自体が区別され、それに言葉が当てはめられるとは考えない。そうではなく、むしろ言葉による分節によって初めて存在者の世界が区別されると捉える。つまり、言葉=分節=存在であり、言葉以前の存在は絶対無分節(渾沌)となる。
第二の柱は、言葉を通じて分節を行う意識が、表層意識と深層意識の二次元に分けられたことだ。西洋哲学ではリアリティは経験的な表層意識の次元でのみ捉えられる。それに対して東洋哲学では深層意識の次元にまで踏みこみ、この次元から表層意識のリアリティを捉え直す。このような意識論では、意識=言葉=分節=存在(リアリティ)となり、意識から離れた存在という捉え方はありえない。
なお、「心」ではなく「意識」を用いる理由について、遺著となった『意識の形而上学』(1993年)では、大乗仏教にいう「心」が、個人意識を超えて生命的・集合的な広がりを持ち、かつ修行的善悪(汚濁清浄)の視点で貫かれているから、東洋哲学全体を間文化的に論じるためには相応しくないと説明されている。
第三の柱は、リアリティの分節に関して事物の「普遍的本質」に注目することである。「普遍的本質」、すなわち事象の「何性(アラビア語でマーヒーヤ)」を言葉で定義することは、いうまでもなく思考にとって不可欠だ。ただし、個体的本質(このもの性、フウィーヤ)の実在を唱える個物主義の立場では、普遍的本質は概念的本質として位置づけられる。
井筒によれば、詩人の多くが「このもの性」に魅せられた。例えば、リルケは個物的リアリティの純化を徹底的に追求したし、芭蕉は「古今」の普遍的本質を(「新古今」の幽玄化を受けて)一瞬のうちに感覚化した。ただし、例外はマラルメであり、純粋な普遍的本質(イデア)のみの不動・静寂の世界を求めたという。
日本思想に目を転じると、歌人でもある宣長は思想家として普遍的本質を徹底的に拒絶し、ものの直観的=情感的把握に固執した。それが「ものの哀れ」である。日本思想の本領はこの個物主義にあると井筒は捉える。
また、本質にはそのほか、イスラムの哲学者アヴィケンナが提唱した、普遍の何性と個別のこのもの性に共通する根源、すなわち「本性(タビーア)」もある。これが後に西洋のスコラ哲学では「自然(ナトゥーラ)」と訳され、論争を巻き起こした。この種的特殊性を基盤におく考えは日本哲学では田辺元の「種の論理」を想起させる。
*
以上の三本柱に支えられた構造論のモデルを図1に示す(本書222頁の図を改作)。
ここでAは表層意識を示し、MBCは深層意識を構成する。Mは詩的神話的想像(非現実的なイメージパターン)の世界、Bは井筒独自の「言語アラヤ識」(可能的な意味連関が潜在する世界)、そしてCは無意識であり、この根底に意識のゼロポイント(無極=太極)がくる。
深層意識の重層構造は唯識とユングを下敷きにしている。表層と深層に分けるだけでなく、深層をさらに四層化した点、またとくにアラヤ識に言語を冠した点が、井筒の独自性であろう。次回は東洋哲学の世界に踏み入る(続く)。
(編集:前澤 祐貴子)