交流の広場

【寄稿C】
(9)
対話 とは
一つの手紙の形式 である
「人と人を繋ぐ手段について」
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院
神経精神科
菅原一晃
ミハイル・シーシキン
『手紙』
奈倉有里訳、新潮社、2012/10/31
今回紹介したいのは ロシア人小説家のミハイル・シーシキンの『手紙』という小説です。
この作者は日本ではあまり知られていないかもしれませんが、世界的にはベストセラー作家であります。その中でも著者の代表作といえる作品です。
どのような小説かといえば、小説のすべての内容が書簡形式で進行していきます。女性の手紙、男性の手紙、女性の手紙、男性の手紙というように、そのままずっと続いていき最後までこの形式ですが、その中で読者は違和感を感じるはずです。
女性の手紙は、日常的な風景の中で、今日はどういうことをして考えた。これまでもこんなことがあった、これからはどうしよう、といったような話です。
朝 トーストを食べたり、散歩をしたり、その中で恋人のことを考えたり とよくある日常の話です。
他方の男性はといえば、戦場にいるのがわかります。その中でも家族や恋人、そして 自分が生き残れるかについて 必死に考え語っています。
この2人の対話であるならば、普通は離れ離れになった男女が 一方は戦場に行き、もう一方は戦場に行った恋人の帰還を待つ という風に考えると思います。お互いにやりとりしている手紙がその支えなのである と思うでしょう。お互いに子供の頃に嫌なことがあったことなど 記憶の思い出の片隅にあるような 読んでいるこちらが恥ずかしくなるようなことも出てきて、こんなに細かく話すのはやはり将来を誓いあった仲だからこそなのだ と思ったりします。

しかし この手紙のやり取りは普通ではないのです。読み進めていけばわかりますが、種明かしてしまうと 男性は1900年前後に義和団の乱の鎮圧に向かうロシア兵の一人であり、女性は といえば現代のロシアで生きているのです。そういう2人の間での往復書簡であることが判明していきます。
そして戦争はどんどん悲惨さを増していきます。男性は果たして無事に帰還できるのかどうかさえわからず、「死の気配」が近づいてくるのを感じる記述が増えていきます。その途中で、なんと男性の死亡連絡の書簡が出現します。この本の半分くらいのあたりで、男性が死んでしまったことが明らかになります。

それでもこの小説、あるいは書簡は続いていきます。男性も女性も書き続けるわけです。
男性は死が近づいている戦場で ただ恋人に向けて手紙を書くこと、無事に帰って愛する人のもとに戻ることだけを支えにしながら 厳しい戦場という場を生きている。そのように思われます。
しかし さらに不思議なことに 現代を生きるこの女性は 恐らく男性が生きている時間、戦争に参加し、そして死亡した時間を遥かに超えるような時間軸の経験をしてしまっているのです。誰かを愛し、結婚をし、妊娠をし、しかし流産、離婚、失職など…人との関わりを そしてその中で 多くの哀しみや虚しさ、失望や絶望を経験します。
世界史を振り返れば明らかなように ”義和団の乱”というのは1899年11月2日から1901年9月7日までの2年に満たない時期、かつての中国(清王朝)を舞台とした植民地戦争です。これにロシア兵として参加した男性は 2年間のどこかの時点で死んだことになるでしょう。
他方の女性は少なくとも10年ほど、あるいは20年以上の時間を経験してしまっています。それだけの時間が過ぎてしまえば、男女の思いは必然的に変わってくるものでしょうし、待ち続けることは不可能になります。そもそも恋をして結婚して妊娠するなどをしているこの女性にとって、それでは手紙を書いているのはどの男性に対してなのか、さっぱりわからなくなります。
そもそも この2人が出会ったことがあるのかどうかさえも分からないし、お互いに完全な独白…誰かに対して書いたわけでもない ”手紙”というより、個人的な日記を順番に重ねているだけなのではないか という疑問すら浮かんできます。時空を超えたラブレターなど存在するはずがない と作者の試みに反発したくなってしまうかもしれません。
しかし だからこそ私はこの手紙、「不可能な」試みであるこの往復書簡 というのは成功していると言えるし、また胸を打つのだ とはっきり言っていいと思います。

私たちは社会で生きている限りにおいて 他者を必要とします。ロビンソン・クルーソーのように無人島に辿り着いたとしても 誰かを探します。それは自分以外の他者が必要だからです。家族がいれば家族、あるいは 恋人や友人、それさえもいない一人暮らしの人であったとしても 出掛けて スーパーやコンビニエンスストアなどで買い物をしたり、インターネットでSNSを用いたり、何らかの手段で「誰か」と繋がろう とします。
とりわけ多くの人にとっては 大切な人がいるはずです。
その人物が近くに居れば それは嬉しいことであり、直接声を聞いて話したり、身体に触れたりすることだって出来ます。一緒に食事や趣味を享受しあうことも出来ます。
それが出来ないならば、電話で声を聞いたりすることやSNSでの電子情報を介した関わりなどもあります。特に現代の世界では SNSは必須となってきています。電話では相手の時間を侵襲してしまう恐れなどもあるために、SNSを用いながら他者と連絡をとり、場合によっては生存確認をします。

それでは、そのようなコミュニケーションというのは、私たちにとってどのような意味を持っているのでしょうか? そして その手段を用いることで相手を大事にしている と言えるのでしょうか?
現代は情報が多く飛び交っています。この小説の女性も現代のロシアに住みながら、数多くのメディアを使用しているはずですが、男性の方は1900年前後の世界でインターネットも電話もなく、手紙のみが唯一の媒体とさえいえる世界に住んでいます。そこでは情報量は圧倒的に異なります。
現代と比べて100年以上前の世界では、何をするにも不便であり、情報を手にすることの困難さを感じずにはいられないでしょう。
現代では 何かを調べたい と思ったらGoogleやYahooなどのサイトに検索ワードを入れればすぐに調べたいことが出てきます。しかし 例えば何十年前か、例えば 1990年前後はそんなことはありませんでした。調べたいことがあれば百科事典を調べたり、図書館に行って本を探したりしたものです。また図書館に行ってもすぐに検索をできるわけではないので、まず調べることすら時間がかかったものです。さらにその100年近く前になると、百科事典すらなく、知りたいことがあれば 知っている人に聞く、などの手段しかなかったかもしれません。そのためにその人と関係性を作って、嫌なことも我慢するなど、不自由さを伴っていた可能性もあります。
それに比べると、現代は圧倒的に楽で 情報を得るために人間関係を気にする必要もない社会です。調べたいことがあればすぐに調べられるし、情報を保存することも非常に簡便にできるようになりました。
しかし、それでも私たちは決してその「情報」をすべて処理できるわけではありません。すべて記憶できるわけでもないです。SNSでは「了解」「よろしく」あるいは「よろ」など短い文字での会話が溢れ、一つ一つの出来事やコミュニケーションを大事にしている と言えなくなっています。だからこそ、相手が機械であっても全く違和感のない会話も出来てしまいます。
実際に かなり多くの企業では 質問に対してチャットを用いた自動の会話が出来るようにしたサイトを設けていたりもします。

翻って この小説では、お互いに必死になって目の前の出来事を刻み、描き、誰かに伝えよう としています。あるいは ただの日記であり、自分以外の他者には伝えるつもりはない かもしれませんが、それでも「自分自身」に対して一生懸命書き連ねています。
人間と人間が対話をする基本にはかならず他者がおり、それを誰しも要望していることは少し前に記しました。但し その他者は実は生きている人間でなくても良いのです。手紙の届け先は生きている人間でも、もはや死んでいる人間であっても あるいは生きているか死んでいるかさえ不明な人間に対してでも良い ということです。
例えば テレビで時折 「死んだおばあちゃんに」、「幼くして死んだわが子に」、「戦争で死んでいった兄弟姉妹に」…手紙を書き 読んで涙している という光景を目にします。芸能人のバラエティーの枠だったり、震災を経験した被災者だったり、戦争を経験した老人だったり…とパターンはいろいろですが、その場面は胸を打つものがあります。それは 死んだ人間に対してだからこそ真摯になれるという面もあるでしょう。結婚式で亡き父親に新婦が書いた手紙、亡き恋人へのレター、両親から亡き幼子に宛てられた手紙には真摯さがあります。

そこに共通するのは 一生懸命自分自身のことを書き連ね、相手に伝えようという思いなのです。まさにこのシーシキンの小説は 人間が真摯にコミュニケーションをする経験を先鋭化して切り取っている作品である と思えるのです。
そしてそれはSNSに浸りきって、目の前の相手に大事なことを伝えることを省いてしまう私たちに対して、大事なことを教えてくれる作品である と言えます。
そう考えれば 現代のロシアに住む女性が、別の男性に恋をしたり結婚をしたりしているにも関わらず 1900年前後の戦争に参加している男性に手紙を宛てているとしても それは全く変なことではないことが分かるはずです。
誰しも目の前のことに必死になるあまり 自分の状況を振り返って言語化したり、客観的に見て振り返る機会を失ったりしてしまいます。普段の生活では 誰かを傷つけ、傷つけられながら 私たちは生きていますし、時には大切な人間を というより 大切な人間に対してこそ 扱いがずさんになり、傷つけ傷つけられることが多くあるのが日常の風景です。
「手紙」というコミュニケーションメディアは 私たちにとって必要不可欠な「対話」の根本が何であり、コミュニケーションにおいて尊いものが何かを気づかせてくれるきっかけになるはずです。
本書は 現代の社会で私たちが大切にすべきものは何か について考えさせてくれる作品であり 現代だからこそ一読をお勧めします。
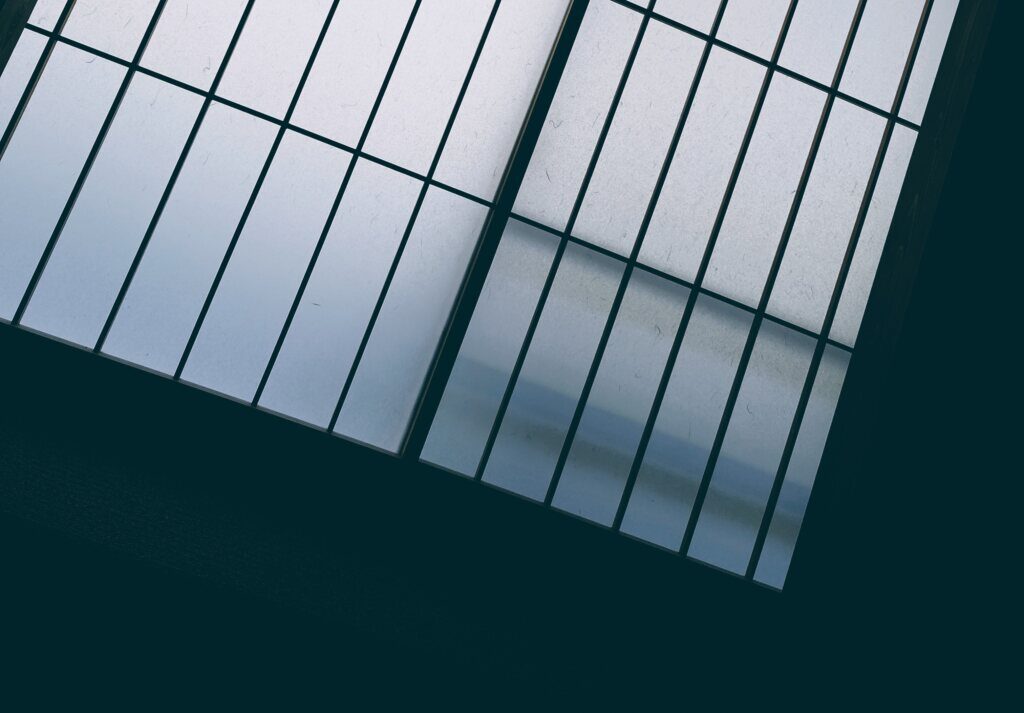
なお 今回私は現代の生活が情報的にあまりにも便利になっているが故に 普段のメッセージやコミュニケーションをないがしろにしている可能性を指摘しましたが、作者は義和団事件という歴史に埋もれがちな出来事を敢えて舞台に描きました。2022年の時点で現在進行形であるロシアとウクライナの戦争を目の前にして 私たちの認識が変わってしまった面もあるでしょうが、第二次世界大戦の戦勝国であるロシア(あるいはソビエト社会主義共和国)を敢えて批判的に書いている面もあり このあたりのことはあとがきに詳しく記されています。同じく「戦争」というものを生々しく書くことで戦争を理想化せずに、多くの人間が犠牲になり、苦しむことも描いた作品でもある といえます。
最後に 2015年に著者が来日した際のインタビューの一部を抜粋して本論を終えさせていただきます。
2022年のロシアとウクライナの戦争を経た私たちには シーシキンの先見性や深い洞察が分かりますし、「言葉」を使うことを繊細に そして大事に考えていることが よくわかるはずです。
さらには 「戦争」を主題にして語ることの切実さや緊迫感も理解できるはずです。
ロシア語圏のインターネットを開けばわかることですが、ロシア語の中に 非常に多くの憎悪が蔓延しています。ロシアはファシズム国家になりつつあります。ファシズムは常に憎悪を中心として成り立っています。憎悪は大気の中をただ漂っているわけではありません。憎悪が生き延びるためには「肉体」が必要になってくる――その「体」となるものこそ 大変悲しいことに「言葉」なのです。
リベラル派を嘲笑するために生まれた リベラルとペデラスト(児童性愛者)を掛け合わせた「リベラスト」という言葉を始め 憎悪を詰め込んだような 聞くに堪えない酷い造語が飛び交っています。
さて、作家はこの言葉を使うべきでしょうか。
私は自分の作品のなかで、これら憎しみの言葉を使うことは絶対にありません。そういった言葉を率先して使う作家もいますが、彼らはそれによって「冷たい内戦」が本当の内戦に発展するよう推し進めているのです。蔓延してしまった憎悪は 長いこと大人しく留まってはいません―― やがて そのはけ口を求めるようになります。 そう遠くない未来に 憎悪が破裂し ロシアでなにか恐ろしいことが起こる――私は今 私たちがその悲しい事件の目撃者になってしまうのではないかという懸念に駆られています。そして「言葉」は、 国が戦闘の可能性を宿しているその状態を示すバロメーターになっているのです。

(編集:前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。