交流の広場
老成学研究所 > 時代への提言 > 【寄稿C】医師 菅原一晃シリーズ > 【寄稿C】 (8) 「命の音が聞こえるカフェで」 精神科医 菅原一晃

命の音が聞こえるカフェで

『カフェ・シェヘラザード』
と
杉原千畝 の 命のビザ
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院
神経精神科
菅原一晃
アーノルド・ゼイブル
『カフェ・シェヘラザード』
菅野賢治訳、
共和国、2020/8/12
現在、ロシアとウクライナの間で 戦争状態が続いています。いつ終結するか見えない状況であり、だから戦争は起こしてはいけない と思わざるを得ません。もちろん 戦争はこの東欧地域だけではなく、現在も中東やアフリカでも起こっています。また 時間軸を過去に戻ると 多くの数え切れない戦争が生じ、信じられない数の命が失われてきました。戦争が起こると難民が出てきます。現在のロシアとウクライナの戦闘でも大量の難民が出ており、近隣の国に逃げているのが現状です。
今回紹介させていただくのは、
第二次世界大戦で戦争に遭い、数々の危機を乗り越えてなんとか生き延びたユダヤ人、
彼らや彼女たちが住むことになったオーストラリアのメルボルンのカフェの小説です。
このカフェは元々実在していましたが、現在は閉じられています。
カフェに集うユダヤ人たちは、どんな過去を背負っているのか、それが一つ一つ語られていきます。
カフェを作った夫婦の物語は凄まじいものですが 実際の話のようです。また 登場する人物も同様に壮絶な体験をしており、この数名の人物たちの体験一つひとつが複数の人たちの体験をコラージュして組み合わせているようです。
これらの物語がそれぞれの語り手によって述べられていきます。登場人物は人生の最晩年を過ごしており、前半生の苛烈な経験は過去のものになっているとすら思える年代です。が、その経験は決して忘れてはいけない質のものであり、それ故に 語り継ぐことになるわけです。

この本の訳者は 後書きでこのように書いています。
これまでも、第二次大戦初期、ナチス・ドイツとその支配地域からシベリア鉄道により日本に避難したユダヤ住民、あるいは、いったん北欧の中立諸国(とりわけリトアニア)に避難し、1940年7月、それらの国がソ連の共産主義体制に組み込まれたことをきっかけとして、やはりシベリアを経由し、日本と中国に新天地への脱出口を求めたユダヤ難民たちによる回想録や証言ビデオは、英語、ドイツ語、イディッシュ語など、さまざまな言語で多数、残されている。また、それらの回想・証言をベースとした後代の書き手によるノンフィクション仕立ての書き物も枚挙に暇がない。
しかし、本書のようにポーランドを起点とし、1年数カ月におよぶリトアニア、ヴィルニュスでの避難生活を経て、シベリアを渡り、日本の敦賀、神戸へ流れ着き、そして日本軍政下の上海で五年ほどを過ごして、戦後、オーストラリアに定住するという、まさに世界地図を大きくかぎ裂きにするかのようなザルマンとヨセルのオデッセイアに伴走させて、同時期、北極地帯とシベリアの奥地で苛酷な労働を強いられた人々(ライゼルとその仲間たち)、カザフスタンやウズベキスタンで戦時期をやり過ごした人々(マーシャの一家)、さらにはリトアニア、ヴィルニュスに留まり、1941年6月、独ソ開戦後に猖獗をきわめたユダヤ・ジェノサイドを抵抗活動家として奇跡的に生き延びたごく少数の人々(エイヴラム)の境遇を、文字どおり「ポリフォニー」として描き出す本書のような作品は、私の知る限り、他に例を見ない。〔……〕
むろん小説は小説であり、史実の厳密さを無理強いすることはできないが、いま〝第二次世界大戦とは何だったか〟との問いを立て直すとき、そこに日本の敦賀と神戸、そして日本軍政下の上海を直接関係づけ、あのとき、すべてはすべてに連動し、全員が全員の命運に参与していたことに思いをいたすよう、重厚にも優しく誘なってくれる本書は、日本語版として読みつがれるに十分以上の意義を有していると信じる。語り手のマーティンが図書館で『タイムズ世界地図』を眺めながら独りごちているように、「いくつもの線が、よじれ、曲がり、ふと脇にそれて思わぬ回り道にさ迷い込んだ末、いま、《シェヘラザード》という名のカフェに、こうして収束している」とするならば、それらの線の何本かは確実に日本と上海を貫いている。戦時期の東アジアにおけるユダヤ難民という、この主題を、単にその特異性、猟奇性の視点からではなく、常にどこにでもあり得る史話として掘り起こし、理解していくことの重要性がそこにあるのだろう……。
「訳者あとがき」より

近年、第二次世界大戦のときに、リトアニアのユダヤ人が日本人の杉原千畝氏によるビザの発行により救われたことが知られています。ただ、私たちはこの事実を知っていても、実際にはどのような経路を通り、どこに行ったのか、どうして助かったかについてはほとんど知らないのです。
それがこの本では何人ものユダヤ人の記憶が組み合わされて作られた2名の記憶として、壮絶な体験の軌跡が描かれています。
リトアニアから陸路を通り、そこでシベリア鉄道でロシアのウラジオストクに行きます。
彼らや彼女たちは常に不安でいっぱいで、杉原千畝のビザも「これは結局嘘なのではないか、実際には無効なもので騙されているのではないか」など疑心暗鬼になります。しかし 出航ができ、そこから貨物船で福井県の敦賀に向かい、日本に到着します。
日本では列車は一分たりとも遅れず到着し、ユダヤ人たちは「感心したのはこの効率の良さ、正確さ、礼儀正しさだった。それから清潔さも」と、現在の日本にも通じるような、或いは ほとんど変わりない部分に感心する場面は興味深くあります。その後 敦賀から神戸に行き、暫く過ごすのです。
神戸滞在時には 大阪の歌舞伎座で「ラ・トラヴィアータ(椿姫)」を鑑賞し、「ヨーロッパ産オペラの決まりごとが 歌舞伎のしきたりと共に再現されていた」と 歌い手を評するなど、太平洋戦争前の日本では ある程度ゆとりがある局面も知ることができます。太平洋戦争というと 戦争末期の東京大空襲や原子爆弾投下など凄惨な悲劇的なイメージがありますが、この戦争の初期はむしろユダヤ人を受け入れるキャパシティが日本にあったことなど、意外なイメージを私たちも知ることができます。
その後、中国の上海に移動します。そこではユダヤ人はゲットーに押し込められます。
さらに太平洋戦争が始まり、アメリカをはじめとする連合軍により、上海への攻撃もなされるようになり、一気に局面が変わるのです。
管理が厳しくなった上海では「日本人の将校たちは、占領軍特有の威張りくさった態度で街中を闊歩していた」 と、日本の生真面目さがある種の機械的な冷酷さとしても描かれており、これもやはり現代に通じるようなテーマでもあるでしょう。登場人物は上海での空襲により、目の前で、知り合った家族たちが焼き殺されるのを目撃します。
上記は 杉原千畝の関わる物語ですが、生き残り語る登場人物たちはほとんど身内が殺され、生きる望みを失い、自身も命からがら生き残っていきます。
その後、生き残ってからオーストラリアに辿り着くまでの経緯は省略されていますが、もはや戦争体験からすれば、メルボルンの土地までは語るにあたらないことでしょう。あまりにも苛烈な物語であり、それが事実であることに 繰り返し驚愕していました。
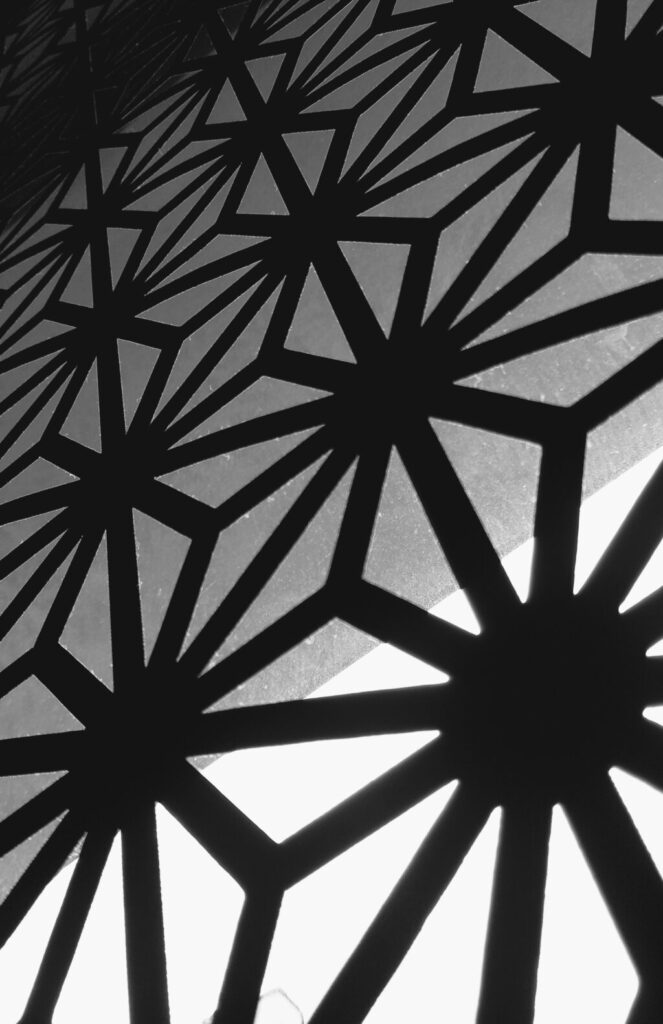
その中で 私はいくつかのことを思いました。
まず、それぞれの語り手は本当にギリギリの状況で生き長らえています。
運が悪ければ、あの時判断を間違えていたら、空襲のときに数メートル場所が違っていたら、確実に死んでいたと思われるのです。現代のように手持ちの電子機器などなく、自分の勘や経験で逃げ、或いは自身の命を追っている敵と戦わなくてはならない状況がある中で、適切な判断などできるのか、ということです。
スマートフォンを持つ私たちでさえ 同じような問いはあり得ます。
ウクライナ難民の映像を見てもそうですが、いつ避難するか、誰と一緒に行動するか、何をもって逃げるか、或いは武器を持って戦うか などは、どんなに機器が発達したとしても決めるのは自分自身であります。その判断が積み重なり、大きく人生に影響を与えることになるのです。
幸い、現代の日本に住む私たちは、戦争が目の前にある状況ではありませんが、これもいつそのようになってもおかしくはありません。或いは地震や水害、台風や火災など震災によっても同じく大きな決断をしなければならなくなります。
この物語の登場人物は間一髪で生き残りますが、翻って私たちの人生の脆さや儚さ、その中で判断し決断しなければならない恐ろしさを感じずにはいられません。
私は医師の立場で多くの患者の病歴や生活歴を聞く機会があります。すると「あと少しのところで…死ぬところでした」ということを聞くことがしばしばあります。病気、外傷、あるいは人間同士のトラブルなどで、多くの人間が巻き込まれ、命や生命、安全を危うくする機会に遭遇していることが意外なほど多いことを知らされます。
また、子どもや青年時代に戦争に参加したという老人もいます。本当に多くの間一髪というケースに驚かされるのです。
臨床医としては感傷的になりすぎると先に進まないので普段は感情を切り離して対応してしまうことが往々にしてありますが、だからこそ こういうことを考えながら普段の仕事や生活、それらがつつがなく回っている日常の有り難みを振り返ることが 尊く重要であろうと思います。

それから 私たちの生きる意味についてです。
これはアウシュビッツのような強制収容所体験をした人々、彼らや彼女たちは、目の前で無慈悲に仲間たちが死んでいく中で 生きている意味が分からなくなるなどの報告があります。アウシュビッツだけではなく、別の形でも戦争は多くのものを犠牲にしますが、その中でも積極的であれ消極的であれ 生きていくことを私たちは選んでいきます。それではどうやって私たちは生きていくのか、です。
現代の日本やその他先進国のように、戦争は目の前にはなく、景気が良くないにしても物が不足する訳でもない社会に私たちは生きています。しかし私たちは不満を持ち、充実感を持てず、さらには自殺する人間も少なくありません。世界の至るところで戦争によって肉親を皆失う人たちがいる中で、現代の私たちが死にたくなり、そして自殺企図する人々が大勢いるのは嘆かわしい状況でありますが、私たちの住む世界というのは私たちしか生きられず、それはあくまでも主観的な形をとります。世界がどんなに豊かであろうと、私たちの世界が荒んでしまっていては、そのようには感じられないのです。そんな中で、私たちが生きる意味とは何か、ということをこの本は考えさせられるのです。

蛇足ですが、私がドイツのハイデルベルクでよく利用していたカフェがあり、そこはユダヤ人が開設した場所でした。そこで毎日食事をとっている老人の方にそのことを聞きました。そのカフェも、もしかしたら色々な物語があるのかもしれません。或いは、普段私たちが何気なく利用するカフェにも、その背景には壮絶なエピソードがあるのかもしれない。そんな想像力すら掻き立てられるものがありました。
(編集:前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。