交流の広場

©︎Y.Maezawa
夢幻能
の
Performativity
過去の蘇り
演劇研究家
遠藤幸英

©︎Y.Maezawa
はじめに
能楽(明治以前の呼称は「猿楽」)の大成者として知られる世阿弥は
素朴な歌舞音曲を組み合わせるにとどまっていた室町時代はじめまでの
舞台芸(田楽や猿楽など)を大きく発展させた。
とりわけ世阿弥が新たに創出した「夢幻能」は能楽史上意義深い。
夢幻能では霊的な存在(神霊あるいは亡霊)が生者の住む現実に出現する。
生・生者と死・死者の遭遇もさることながら、
<現在>と<過去>の出会いもまた
夢幻能に関する研究テーマを設定する上で重要である。
過ぎ去りし思い出に執着する亡霊は理想化された過去を再現しようと企てる。
亡霊の(台詞や歌からなる)謡うたい(主として昔語りという物語の一種)は
聞き手(ワキ=旅の僧)を行動に駆り立て、また周囲の状況にも影響を与える。
その結果過去は生者の今・現在を圧倒せんばかりに存在感を誇示する。
過去の住人である亡霊が現在に姿を現し、
昔を今に返すといういわば力業を優美にやってのける。
今も昔も失われた時をとりもどしたいという思いは人間共通のものだろう。
和歌の世界ではこの切実な思いがとりわけ男女関係における切実な願望として
雅な言葉遣いが工夫された。
その典型が
しづやしづ しづのをだまき 繰りかへし
昔を今に なすよしもがな
である。

©︎Y.Maezawa
伝説によるとこれは源義経の愛妾静御前が頼朝の猜疑心のせいで義経との仲を引き裂かれた悲痛な思いを歌ったものだという。
作者(静御前:しづ)自身の卑賤な(賤)出自(歌舞に長けた遊女であった白拍子)を読み込み、機織りの道具である糸巻き(苧環)の無限に巻取り巻戻す行為が作者の無言ながらもはげしい愛情を浮き立たせる仕掛けである。
この和歌は平安時代から鎌倉、室町時代にかけて『伊勢物語』、『吾妻鏡』そして『義経記』において繰り返し登場する(引用される)。また能『定家』や『黒塚(安達原)』にも同様の心象が援用されている。
静御前と義経の絆を糸巻きになぞらえた詩的イメージは和歌に通じた貴人だけでなく幸若舞などの語物系の芸能や平易な物語構成と表現を特徴とする御伽草子から耳学問したと思われる庶民の心の琴線に触れたにちがいない。

©︎Y.Maezawa
同上の和歌の引き写しこそないけれどもその趣旨を基本テーマにすえた能楽作品がある。
夢幻能の代表作とされる『井筒』や『松風』がそれだ。
舞台に展開するのは一定の戦略に基づく過去奪回作戦であるといえるだろう。
過去が鮮明に浮かびあがるのはその主人公(亡霊)の発言のあり方に起因するのではないか。その点を考察するには J. L. Austinが提唱した「言語行為論(speech act theory)」を無視できない。
発話は基本的に事実確認を意図するとされた従来の平板な言語論を根本から批判してオースチンはそのダイナミックな働きに注目した。
話し手の言葉は一定のルールに則りながら暗黙のうちに聞き手に対して一定の行動をとらせる社会的な働きをするというのだ。オースチンはそれを「performative utterance(行為遂行的発話)」と名づけた。
その後 performativeから「performativity(行為遂行性)」という概念が派生して言語論の枠を越えて学術諸分野の思考を刺激し続けてきた。
発話が本質的に社会的影響力を持つという発想は夢幻能で現世に対する未練に苛まれるあまり出現した亡霊の言葉の本質を照らし出す。
遭遇した生者(行脚僧)に対して亡霊は露骨に指示を出すわけではないが、発する言葉は他者を動かす社会的作用を及ぼす力がある。過去が儚くも輝かしい理想化された姿を現わすために亡霊は文学的技巧(文彩)を凝らす。懐旧というような消極的なものではなく強い意志に基づく積極的な創造行為である。
オースチンの意図を越えてperformativityは本質的に「演劇性」を帯びる。
とすれば 「再現」は「再演」でもある。

©︎Y.Maezawa
今ひとつ注目すべきは 亡霊が企てる過去の再現・再演は特異なねじれ方をしている点である。
それを吟味するためにデリダの「引用性(citationality)」という概念を援用する。
この概念はオースチンの言語行為論には登場しない。しかしオースチンは意識していないが、引用にほぼ相当する事例がたびたび現れる。
結婚式や進水式などで儀式執行の有資格者の発言は社会的に容認された慣習的言辞をほぼ模倣するのでこれも引用とみなせるだろう。第II講では「一定の慣習的効果をもつ、受け入れられた慣習的手順」が不可欠だと指摘されている(オースチン, p. 35)。
オースチンの言語学に対する大きな貢献は 彼の言語行為論が 言語の社会的ダイナミズムに光を当てた点にある。
しかし残念なことに、考察範囲が日常言語に限られ、舞台劇の発話など擬似的な言語は対象外なのだ。
のちにデリダがその偏狭性を批判し 言語が一般的にperformativeであると主張することになる。
デリダはとりわけ「引用性(citationality)」———「引用」という行為自体ではなく「引用」が周囲に波及させる作用———に注目し、頭脳に蓄積された表現を引用(反復)するのが言語活動の基本だという。
引用に基づく発言は 相手に対する影響力を発揮するように意図されているものである。
これはいわば(創造的)模倣(mimesis/imitation)であり 演劇的にならざるをえない。
だが、デリダ は釘をさす。
引用の本元は永遠に欠落していると。
脱構築論の旗手らしい解釈である。
このある種過激な言語論と夢幻能が出会うとどうなるか。
『井筒』と『松風』はどちらも実在の歌人(在原行平、業平兄弟)が情熱的かつ優美に恋愛を歌った和歌を引用しているが、引用の本元が特異なのだ。
両作品はそれぞれ在原業平ならびに在原行平の和歌を正確に引いてはいる。
しかし作者である在原兄弟はかれらの和歌が名作として後世の文学作品に幅広く影響を与えた結果、作者自身の実在性が希薄になってしまったのである。
たしかにかれらが和歌の名手であり宮廷の高級官僚であったという歴史的事実は疑えない。それでも両者の伝説化が極度に進み、ことに業平の場合伝説が異常なくらい一人歩きしてそのひととなりが現実離れしてしまったと考えられている。
そういう人物に言及しその創作物を引用することはデリダが提起したperformative(行為遂行的)な「引用性」と重なる。
幻能に登場する現世に未練を残す亡霊にとって 自らがかくあれかし と願う過去を語ることは 単なる記憶の再現ではなく創造行為なのだ。

©︎Y.Maezawa
あらすじ
『井筒』
大和国(現・奈良県天理市)にある荒れ寺。ここは高貴の歌人在原業平とその妻(貴族。歌人の娘)の旧宅であった。業平の墓所でもある。
(史実の裏づけのない伝説上の)夫婦は隣あわせて住んでいた幼い頃からの仲良しで毎日どちらかの家が所有する井戸のそばで遊んだ。長じて結婚。一時よその女に心移りした業平も妻がそそぐ変わらぬ愛に迷いから覚め、夫婦は再び幸せをとりもどした。やがて夫、妻の順であの世に旅立った。それも遠い昔のことだ。
ある秋の暮れがた、その寺に諸国一見の僧が訪れる。
土地の女が墓参りに来ているのに出くわし言葉を交わす。その女の話ぶりは業平との深いえにしを感じさせる。別れ際に女は自分こそ業平の妻だと名乗って姿を消す。僧は亡霊と出会ったのだ。
やがて僧は境内で一夜を明かすことになり、夢に業平の妻と名乗った女が夫の形見の衣装をまとった男装で現れる。女は夫を偲んで二人の儚くも情熱あふれる夫婦愛を語りながら狂おしく舞う。亡夫の忘れ形見をまとい、夫と一心同体となった姿を二人にとって思い出深い井戸の水面に映して昔に思いを馳せる。
夜明けとともに僧は夢から覚めると物寂しい古寺に一人いる自分に気づくのだった。
『松風』
摂津国(大阪府北中部と兵庫県南東部)は須磨の浦が舞台。
須磨といえば(『源氏物語』の「須磨」の巻にもある通り)平安時代は京都に住む貴族にとって流刑の地として知られたほどの物寂しい鄙びた土地柄だった。
秋の夕暮れ、行脚僧が通りかかる。
浜辺の一本の松の木に目がとまる。土地の男の話から松風と村雨という二人の海女の供養塚だと知る。
ほどなく汐汲み車を引く海女の二人連れと出会う。僧は一夜の宿を乞うと一度は断られるが、結局願いが叶う。どうやら身の上話を聞いてほしいような雰囲気だ。
海女二人は遠い昔に死んだ松風、村雨の姉妹の亡霊だと正体を明かす。
元々は名もなき海女の姉妹であったが、縁あって二人は流罪に処された(都の貴族、業平の兄)在原行平の目に止まる。その寵愛を受け幸せの絶頂だった。が、やがて行平が免罪されて帰京。出立に際して行平は形見の衣装を残した。後に残された二人はその形見を見るたびに恋しさが募り、かえって辛さが増すと漏らす。
やがて姉松風は妹村雨が止めるのも無視して形見の衣装をまとって狂おしく舞う。いつしか妹も行平の霊とり憑かれたのか、姉の狂乱の舞に加わる。ひとしきり狂おしく舞った後姉妹は僧に弔いを頼んで消える。彼らは亡霊だったのだ。
一人残された僧は浜辺に松風が響くなか寂寥感に包まれる。

©︎Y.Maezawa
物語の中の過去——物語る行為の演技性
本稿は二編の亡霊を扱う夢幻能、『井筒』と『松風』で語られる過去が前面にせり出してくる事情に注目する。
議論の出発点として援用するのはオースチンの言語行為論(Speech Act Theory)である。
この11回に及ぶ講義は彼自身のノートに基づいて編者J.O. Urmsonが慎重に追記したことがらを含めて後にオックスフォード大学出版局からHow to Do Things With Wordsと題して正式出版された(1962年)。
言語行為論は誠実な試行錯誤の賜物だと印象づけられる。
オースチンは当初発話を従来の言語論で中心を占めていた「事実確認型発話constative utterance」と彼が考案した「行為遂行型発話performative utterance」に二分する(第1講)。
前者は話題について事実確認すなわち真偽の確認をするのであるから当然話題の指示対象が存在することが前提となる。
他方後者は話題にされている事態がこれから発生するはずの事態である以上、発話の時点では指示対象がまだ存在しない。
指示対象の不在という行為遂行型発話の特性は 後に言語行為論批判においてデリダが自身の言語論の一環として「引用性」を論じる際に重視することになる。
デリダによると、「パフォーマティヴは言語の外、言語以前に存在する何ものかを記述するのではない。それはある一つの状況を産出ないしは変形するのであり、操作するものなのである」(デリダ, p. 35)。
的確な指摘である。
だが、オースチンは講義が進むにつれてこの二分法の未熟さを痛感し、後者(行為遂行型発言)の考察・定義づけを充実させるべく第8講にいたって「発語行為locutionary act」、「発話内行為illocutionary act」、「発語媒介行為perlocutionary act」という三つのカテゴリーに分類することに落ち着いた。発語行為とは話し手が言葉を使って意思疎通を図ることである。ただしこの場合話し手には聞き手をなんらかの行為に駆り立てる意図はない。残る二つは発話と行為を直結するperformativeの概念を精密化する上で不可欠なものである。ただしこの場合聴者発話内行為は話し手の発言が聞き手の心理、思考あるいは行動になにかしら影響を与えること。例文:<AはBに対して今すぐ逃げるように助言した>。最後に残る発語媒介行為が表すのは、話し手の発言が聞き手の心理、思考あるいは行動に対して話し手の意図通りに影響し、実際その意図に沿った行動をとらせることをいう。例文:AはBに向かって勝算が高いから競技会に参加するように励ました結果Bは出場した。
さて、夢幻能の過去語りの考察で有益なのは発話内行為および発語媒介行為の背景をなすperformative(および後にオースチンの思考の枠外で出現したperformativity)という概念である。
オースチンはperformを「行動に出る」という意味合いで用いる。原文では“the issuing of the utterance is the performing of an action”(Derrida, p. 6)。
だが、「演じる、演技をする」という語のもう一つの意味は意識していない。ところが、後年オースチンのperformative論は言語学の枠を越えて建設的な意味で拡大解釈されることになる。
1990年ごろからジェンダー論の急進派として知られたジュディス・バトラー(Judith Butler)はオースチンに触発され、従来女性が社会的に強制されてきた「女らしさ」を女性が社会生活を送る上で強制される身振り、すなわち演技と解釈する立場を打ち出した(Butler)。
このように社会的身振りに着目したバトラーだが、それより遥か以前にフロイド派心理学者ジョウン・リヴィエール(Joan Rivière)が先鞭をつけていた。1929年に発表した論文 “Womanliness as a Masquerade” で「女らしさの偽装」というテーマを論じていたのだ(リヴィエール, p. 306)。リヴィエールが意図的に選んだ用語「マスカレード」は人間関係において他者を一種の観客と認識している点でふりや演技など演劇的な行動である。
ちなみにmerriam-webster.com/dictionaryによると masquerade: a social gathering of persons wearing masks and often fantastic costumes。
オースチンが言語活動と社会的身振りとの深い関係を指摘したことは夢幻能研究に以下に示すような新たな視野をもたらしたと思える。
さらにperformativityを演劇性に関連づけたバトラーの論考も刺激的である。
しかし本稿は女性の亡霊が手立てを尽くして過去を物語るという夢幻能をジェンダー論の範疇で扱わず、その舞台上の言動をあくまで演劇性との関連で捉えたい。
というのも語りという行為は必然的に聴衆の反応を意識しなくてはならない。
極論すれば、相手を説得し話を受け入れさせるのが語りである。語り手は演者(役者)であると言いたくなるほど(場合によっては語りでなく騙りで相手を言いくるめる)演劇的センスが必要とされるのだ。
ただし言語学に新鮮な光を投げかけたにも関わらず旧弊な思考を払拭しきれなかったオースチンなので舞台で展開する現実の裏づけのない架空の発話は考慮しない。
©︎Y.Maezawa

こういうperformativeの概念を四角四面に定義するオースチンの硬直ぶりをデリダは批判する。
そもそも、結局のところ、オースティンが異常、例外、「不真面目」として排除しているもの、つまり(舞台上での、詩のなかでの、あるいは独り言のなかでの)引用は、ある一般的な引用性の———あるいは、むしろ、ある一般的な反覆可能性の———限定された変様なのではないだろうか。そして、そのような一般的な引用性がなければ、「成功した」パフォーマティヴもありさえしないのではないだろうか。(デリダ, p. 43)
あらためてことわるまでもなく、上記翻訳文の「『成功した』パフォーマティヴ」とは聞き手に影響を与えて話し手が意図した行動へと駆り立てた発言(行為遂行的発話)」を指す。
演劇のセリフのような架空の状況における発言——翻訳文中の「限定された変容」の一種、言い換えると特異なケース——は台本にあるセリフを役者が音声的に引用した発言を意味する。
デリダによる「行為遂行的発話」は極論すれば(擬似現実でない)日常生活での発話であっても十分に演劇的だといえそうである。
上に引いたデリダの解釈ですでに「引用」と「行為遂行的発話」とが連結されているが、「未来ではなく過ぎ去った出来事について語る」とは本質的に「引用」行為にならざるをえない。
ただし坂部恵(1990)や野家啓一(1996)らの物語論が指摘するように、引用は単なる丸写し同様の復元とは決定的に異なる。
引用性という概念はデリダによる言語行為論批判「署名 出来事 コンテクスト(Signature, Event, Context)」(デリダ)から借用した。デリダは「引用citationではなく引用性citationality」という用語を優先させて引用という行為がはらむ意味に強い関心を示す。
引用の本元は固定されていない、むしろ本質的に欠落しているというのがデリダのスタンスだ。発話における引用の(自立して存在する)本源は不在であり、必ず引用の本元と引用されたものが対応させられるという言語の本性を踏まえた考察である。
©︎Y.Maezawa

ところがオースチンは引用元に相当する発信源の存在を信じている。
遂行的発話というものの要点は、それが行為の遂行ということにある(中略)発話者こそが行為者でなければならない。(オースチン, p. 99-100)
口頭の場合、(能動態、一人称、直接法、現在という文法条件を満たした上で)発話者即行為者という条件下で発話者を「発信源utterance-origin」(Austin, p. 6) と規定する。他方、記述された発言は発言者当人の署名が添えられることで発信源とみなされる。
発信源をめぐってオースチンを批判するデリダは完璧に純粋な発信源(発話者あるいは署名)が固定され、唯一無二と認定された場合、引用すること自体ができなくなると逆説的に唱える。引用、すなわち別の文脈に移動させて使用することが不可能になるのだと。
一見過激な逆説というか詭弁に聞こえそうだが、筋は通っている。引用するためには(しばしば文脈を移し替えると言う意味で)本元から引き剥がす操作が不可欠なのだ。(半)永久に権威を保持する署名など発信源が絶対優位を誇示するには何が必要か。
デリダは署名の本質を次のように解釈する。
ある署名が機能するためには、つまり読解可能であるためには、それは一つの反復可能、反覆可能、模倣可能な形式をもつのでなければならない。すなわち、自らが産み出される際の現前的で特異な意図=志向から引き離されうるものでなければならない。(デリダ, p. 50)
(署名など)発信源が特定不可能だということ。つまり引用の本元が不在であるというデリダ的引用性が浮き彫りになる。実際そのように明言してもいる。
定義上、書かれた署名は、署名者の顕在的ないし経験的な非=現前を含み込んでいる。(デリダ, p. 49)
ちなみに「非=現前」は英訳ではnonpresenceとされている(Derrida, p. 20)。
署名にまといつく無原則な真正さを否定するデリダは署名を再定義するが、その解釈は引用性という概念に新鮮な光を当てる。
文言の引き写し作業だけが問題になる引用ではなく引き写しの作業がはらむ意味が問われる「引用性」とあえて解釈学的表記が必要なのも理解できる。
引用性の観点から見る『井筒』と『松風』に関しては、詳細な検討は後に回すが、両作品とも平安時代の高貴な身分の歌人在原行平、在原業平兄弟がかれらの和歌と伝説上の恋愛遍歴が巷に流布する伝説から引用され、前景化される。
兄弟のうち弟の業平は『伊勢物語』のみならず後代の(井原西鶴などの)文芸作品などでも超特級のプレイボーイとして21世紀の現代まで知れ渡っている。
池田彌三郎が指摘するとおり在原業平なる人物は(現在でも正確な資料が十分でない)歴史的事実から離れて一人歩きをつづける(池田)。引用性論のテーマとしてふさわしい。
ちなみにデリダは(かれがエクリチュールと称する)文字で書き記されたものに基づくコミュニケーションについて次のようにいう。
不在とはまずもって受け手の不在である。ひとは諸々の不在者に何事かを伝達するために書く。それはまた発信者、送り手の不在である。彼らは自らが放棄したマークに対して不在であり、このマークは彼らとの接触を断ち、彼らの現前を越えて、彼らが<言わんと欲していること(vouloire-dire)の現前的な顕現性、さらには彼らの生そのものを越えて諸々の効果を産み出し続ける。(デリダ, p. 18)
例えば 出版物は著作権という法律上の問題は抜きに考えると、不特定かつ匿名の読者を対象に出版市場に出回る時点で 作者も読者もともに不在だといえる。デリダに倣うとすれば、不在とは実は遍在なのではないか。
作者と読者が同席する必要はない。
話を伝説的人物である在原業平にもどすと、この男が話題になればなるほど歴史的実像の確立に貢献するどころか、むしろ実像の万華鏡化に拍車をかけるのではないか。
こう考えると増殖し続けてきた在原業平伝説のありようは言語活動一般に通底する引用元なき引用を証拠立てているように思える。

©︎Y.Maezawa
過去の制作あるいは創造——大森荘蔵の「想起過去説」
亡霊たちは過去を自由自在に創作し捏造するのか。そうではないらしい。
「想起過去説」を提唱した大森荘蔵によると、
想起体験の中でのみ我々は「過去」を経験できる(後略)。想起とは過去の知覚体験の再生ではない。(中略)過去の風物の初体験なのである。この初体験は言語的には過去形同士のみによって表現され、逆に、動詞の過去形の意味はこの想起体験の中で飲み与えられる。(中略)想起されるされないとは独立に過去なるものがあって、それが想起されるのではないかという問いは全く無意味である。過去ということの意味こそ想起体験の中で経験されるのであるから、想起されない過去とは矛盾である以前に無意味なのである。(大森, p. 22)
ややまどろっこしい語り口だが、過去というものの自律性が強調される。
さらに大森は「想起」を次のようにも定義する。
想起は概して文章的であり物語的なのである。(中略)これらの想起された文章や物語は想起された経験の描写や叙述ではない。その文章や物語、それが想起された当のものなのであって、想起された経験の言語的表現ではないのである。その点で想起は記録や報告にではなく詩作に似ている。(大森, p.54)
大学では物理学を専攻し過去、現在、未来へと流れる直線的時間の観念に親しんだ大森だが、やがて古代ギリシアから西洋中世を経て近代に至る科学的思考に疑問を感じて哲学に転向する。
しかし世間の常識は「捏造」された時間感覚に固執したままであることに納得できなかった。(大森, p. 20−21)。
そういう自覚のもとに後に大森は「想起過去説」を提唱するにいたる。
この想起過去説を通してこそ夢幻能を流れる時間のあり方が照らし出される。

©︎Y.Maezawa
その大森に物理学から哲学に転向するという類似の経験をもつ野家啓一が(大森にも潜在していたと思われる)文学的あるいは詩的感受性を発揮して「想起過去説」を発展させることになる(野家)。
大森が哲学の範疇で過去を再定義しようとしたのに対して 野家は大森の時間論を物語論に融合させる試みを展開する。
一度限りの個人的な体験は、経験のネットワークの中に組み入れられ、他の経験と結びつけられることによって、「構造化」され「共同化」されて記憶に値するものとなる。(中略)体験を経験へと解釈学的に変形し、再編成する言語装置こそが、われわれの主題である物語行為にほかならない。それゆえ物語行為は、孤立した体験に脈絡と屈折を与えることによって、それを新たに意味づける反省的な言語行為といえるであろう。(野家, p. 107)
五感の働きに影響されがちな(個人的な)体験はとかくその生々しさのせいで本質を把握するのがたやすくない。
野家が指摘するように体験は視野を拡大し、個人を越えて社会的に共有されるような広範な文脈において解釈することで初めて正体が浮かび上がる。こうして照らし出される社会的に共有可能な経験が物語の中で<過去>として立ち上がる。
野家の場合、過去に焦点を当てた時間論という枠組みに物語論を導入するといっても文学作品を引き合いに出すわけではない。哲学や歴史学では想像力によって創作された架空の物語は考察対象になるとしても付随的なものと扱われる。
しかし野家は哲学者としての自分の立場をわきまえながらも 常識的な現実と虚構の二元論を乗り越えようとする。
野家にいわせると、歴史を含む広義の過去を「語る言葉」(物語の言語)は次にあるとおり「虚構の言述」である。
虚構の言述こそは、意味生成の現場における言葉の原初的な輝きを想像力によって取り戻そうとする、すぐれて創造的な言語行為にほかならない。そして人間は「言葉を語る動物」であるとともに「虚構を騙る動物」であるがゆえに、われわれは否応なしに「虚実皮膜のあいだ」のあやうい境界に生を営む存在なのであり、人間的真実はその境界の上にこそ開示されるのである。(野家, p. 215)
おそらく大森も無意識のうちに虚と実の境界領域の重要性を感じとっていたにちがいない。
そういう先達の直感を尊重しながら、上記のように野家は<過去>の再定義を注意深く試みている。
それはすでに過ぎ去っていわば歴史上に固定された時間の塊ではなく、今現在において想起され、生成され、さらに社会的に共有されるべき<過去>なのである。
上記引用文にある「虚実皮膜のあいだ」から野家が近松門左衛門の劇作論を意識しているのは明らかだ。
文芸の創作はrealism対 illusionismに二分する立場もあるが、近松は両者の微妙な重なりを劇作の指針とした。
その出典は浄瑠璃注釈書『難波土産』であり近松の死後10年ほどのち1738年に出版された。近松と親交のあった儒学者穂積以貫が著者とされる。近松の浄瑠璃作品について学者的視点からの批評が大部分だが、近松自身が語った劇作論を穂積が聞き書きした「虚実皮膜論」も含まれる。(穂積, p. 346-348)
この文芸論は野家が指摘するように過去、さらに歴史の記述にも適用可能だと思える。
この歴史観に一脈通じる視点を提起したのが演劇理論家・舞台演出家Herbert Blau(1926〜2013年)である。
ブラウはこういう。
事実が事実と認定されるかどうかは人がモノゴトをどのように解釈するか、どのように心に描くかによって決まる。(Blau, p. 257)

©︎Y.Maezawa
虚と実のあわいに立ち上がる過去
ここで再び、亡霊の語る過去が浮き彫りにされる『井筒』と『松風』にもどろう。
物語る行為は(野家がいうように)物語られるたびごとに更新される「意味生成の現場」であることは確かだ。しかし、だからといっていわば文化的遺産がすべて廃棄され新たに創造されるというわけではない。
文化的遺産には種々の民間信仰(民間習俗)およびそれが和歌などに導入されて修辞技法(文彩)化したもの(figure of speech)が含まれる。
一般社会と同様、芸能の分野でもこういう遺産は断片化されてしまう。が、断片化は消滅を意味しない。
©︎Y.Maezawa

というのも たとえ本来の文脈からはずれてしまったとしても、こういう遺産は新たな環境に馴染み成長を始めるからだ。
有史以前からの民間信仰に根づいていた多様な習俗形態や信仰観念は(8世紀末には編纂が完成した)『万葉集』に代表される文学的伝統に徐々に定着し貴族を中心とする知識階級の間で普及し文学的に、また芸術的に昇華されることになる。
被差別民の出自ながら有力貴族や武家階級の庇護を受けたおかげで室町時代に大成した能楽もこの知の集積、一種の文化的ネットワークに参加できた。
先史時代の日本人は 時にきびしく 時にやさしい自然環境や徐々に複雑化する人間関係に想像力をかき立てられ 多種多様な俗信あるいはおまじないを考案する。
そこには人間の素朴な感情、知恵や詩的感受性が投影されている。
やがて時代が進み社会と文化が成熟しはじめると 卑俗であったり 純朴であったりする俗信も 新たな文学的コンテクストにとり込まれ 新鮮な輝きを帯びる。それらの俗信の活躍の場は 人間本来の繊細な文学的感性が集積された『万葉集』や貴族歌人たちの詩心を映し出す『古今和歌集』などである。
室町時代初期に能楽(当時の呼称は猿楽であり、これは幕末まで続いた)を芸術性の高いものに仕上げた世阿弥やその後の世代も『万葉集』ならびに『古今和歌集』などに定着した故事俗信の類を数多く組み込んでいる。
以下で『井筒』や『松風』で重要な役割を担う文彩を検討しよう。
その1 袖返しというおまじない
例えば、太古の呪術の片鱗を感じさせる「衣返し(衣の裏返し)」や「袖返し(袖の折返し)」というまじない。
©︎Y.Maezawa
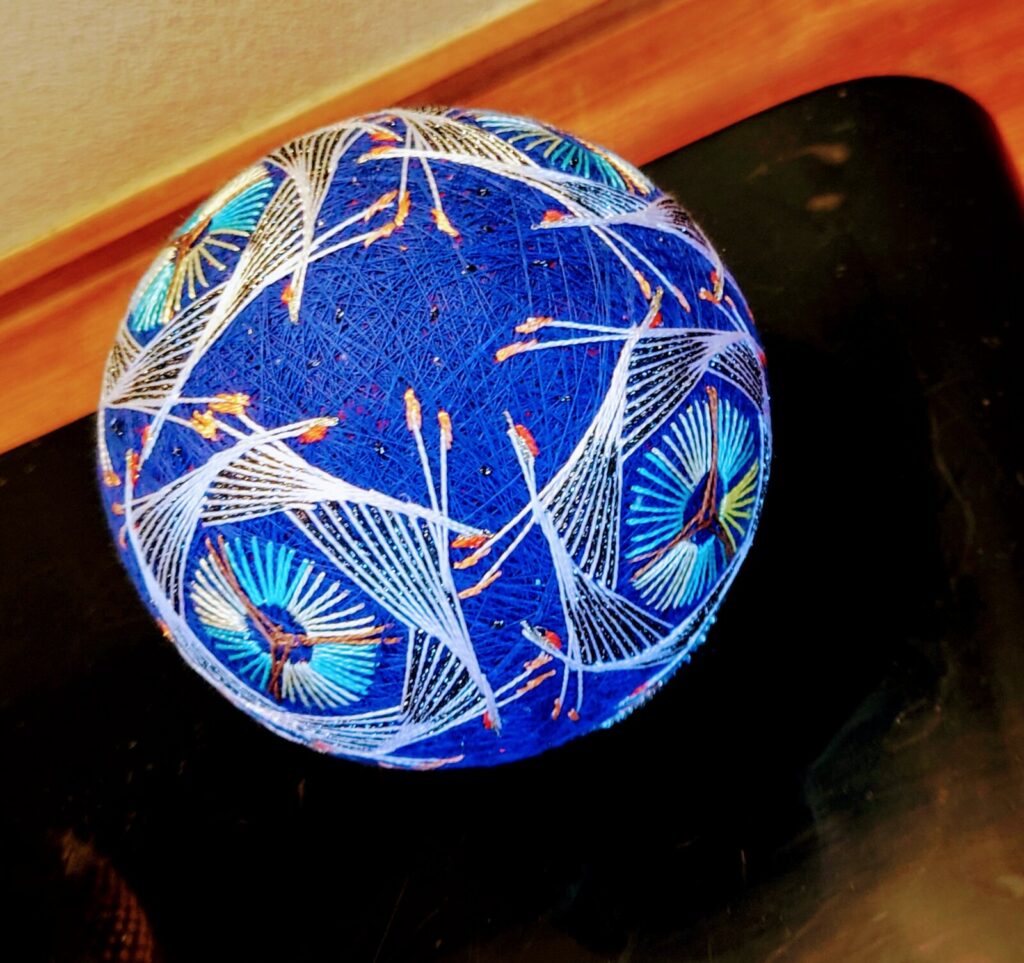
就寝に際して着物一枚を裏返しに着たり、袖(袖口、古語では「衣手」ともいう)を折返すことで不在の配偶者や恋人などが夢に出てくると広く信じられていた。(『新潮日本古典集成』上巻109頁、注16)
『万葉集』や『古今和歌集』に数多く見られる。
我妹子に 恋ひてすべなみ 白妙の 袖返しゝは 夢に見えきや
(『万葉集』巻11、 2812)
我が背子が 袖返す夜の 夢ならし まことも君に 逢ひたるごとし
(巻11、 2813)
白妙の 袖折り返し 恋ふればか 妹が姿の 夢にし見ゆる
(巻12、 2937)
敷栲(しきたえ=寝床の敷物)の 袖返しつつ 寝る夜おちず 夢には見れど
(巻17、 3978)
白妙の 我が衣手を 折り返し ひとりし寝れば ぬばたまの 黒髪敷きて 人の寝る
(巻13、 3274)
このまじないはその出現頻度から判断して当時(奈良時代から平安時代)の社会に広く共有されたにちがいない。
ちなみに小野小町には次の和歌がある。枕詞「むばたま(ぬばたまの変異形)」を伴う「夜の衣」とは今でいう掛け布団に相当する着物をさすのだろう。
いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を 返してぞきる
(『古今和歌集』巻12恋二 554)
こういう純朴な俗信が『古今和歌集』の作者の大半を占める平安貴族たちをとらえていた。
©︎Y.Maezawa

さて『井筒』では末尾近く旅の僧と話していた女が正体(業平の妻)を明かして姿を消す。一人残された僧は女に同情して業平夫婦が再開できるようにと願って裏返しにした予備の着物を一枚掛けて荒れ寺の一隅で就寝する。
すると夢に業平の形見である冠直衣(こうぶりのうし・かんむりのうし)をまとった女が登場する。
女の異性装の姿は夫婦が(女の願いどおり)一体化すなわち昔にもどって再会した象徴なのだ。
詞章にある「昔を返す衣手に」という表現は「衣手(袖口、後に転じて着物全体)」を折返すことによって思い出深い過去をとり返すという意志と願望が込められている。
ワキ 「更け行くや。在原寺の夜の月。在原寺の夜の月。昔を返す衣手に。夢待ち添へて假枕。苔の筵に。臥しにけり苔の筵に臥しにけり。
(『井筒』p. 109)
現代の感覚では単なる迷信かもしれない。しかし古橋信が指摘するように『万葉集』の様々な身分の歌人たちには人口に膾炙した俗信のあれこれが呪性をもつと信じて疑わなかった(古橋,p. 14-15)。さらにそれを歌に組み込むことによって言葉の呪性が勢い生じると考えたのだ。
古代、中世の和歌などではごく当たり前のことだが、引用の本元あるいは作者の特定は問題にされない。際限なく繰り返される引用ないしは模倣とそこから生じるコンテクストの入れ替わりもはげしい。変形、変容は不可避である。
しかしデリダはそれら全てを言語活動一般における引用として認める。オースチンの言語行為論に対する批判文で 引用性あるいは「反復性(iterability)」が発話のperformativityの本質にかかわることだと主張する。
あるパフォーマティヴな発言は、もしもそれを決まり文句として言う行為が一つの「コード化された」ないしは反復可能な発言を反復するのでなかったら、成功しうるであろうか。(中略)決まり文句が、もしも一つの反復可能なモデルに合致しているものとして同定可能でなかったならば、したがってそうした決まり文句がいわば「引用して」として同定可能でなかったならば、パフォーマティヴは成功しうるであろうか。(デリダ, p. 44-45)
この発想にならえば、二編の夢幻能が「反復可能なモデル」の集積である古代日本の知的、文化的ネットワークとたえず密につながっているのも当然である。
その2 形見の呪力
古代以来日本社会に普及していた慣わしの一つに「形見分け」がある。
その歴史の一端を知る助けとなるのが次の和歌である。ただしこれは生き別れに際してのケースである。
我妹子が 形見の衣 なかりせば 何物もてか 命継がまし
(『万葉集』巻15、3733)
©︎Y.Maezawa

奈良時代のこと、都を遠く離れた北陸越前へ流罪に処される夫(中臣宅守)に妻(狭野茅上娘子)が自分の愛用していた衣を「形見」として手渡した。流罪といえば生きて再会することはかなわないものであって、妻はいわば自分の分身、霊力を込めた形見、を夫に持たせて慰めたかったのである。
性別と死別を問わず一枚の着物が思い出のよすがとみなされていたことがわかる。
死別あるいは生別に際して男(夫、仮の夫)から女へ渡される形見、すなわち『井筒』では貴族男子の普段着である冠直衣、他方『松風』ではほぼ同様の普段着としての立烏帽子狩衣。後に残された妻や愛人がそれらを着用することが男女の深い絆を鮮明に象徴する。
両作とも幕切れ近く夫婦愛を描くドラマがクライマックスを迎える。
シテ(『井筒』における業平の妻および『松風』の行平の仮の妻たる松風、村雨姉妹)が形見の衣装をまとって狂乱の舞を舞う。つまり 男女一体の舞という視覚的表現で両作に共通する主旋律が提示されるのである。
『井筒』の場合、
ワキ 地謡 「更けゆくや。在原寺の夜の月。在原寺の夜の月。昔を返す衣手に。
夢待ちそへて仮枕。苔の莚に。臥しにけり苔のむしろに臥しにけり。
後シテ一声「あだなりと名にこそ立てれ桜花。年に稀なる人も待ちけり。
かやうに詠みしも我なれば。人待つ女ともいはれしなり。我筒井筒の昔より。
真弓槻弓年を経て。今は亡き世に業平の。形見の直衣。身に触れて。
恥かしや。昔男に移舞。
(『井筒』p. 110)
『松風』 になると、当初男に去られたことで恨み言を口にする。
此程の形見とて。御立烏帽子狩衣を。残し置き給へども
(『松風』p. 246-24)
©︎Y.Maezawa

だが、その不在の男を偲んで女(姉の松風のみ)形見の衣装をまとうと男が憑依したかのように様子が激変。妹村雨が二人そろって行平を偲び、思いが溢れて狂喜、狂乱の体でひとしきり舞う。
形見の呪力については森朝男の「形見論」が興味深い。
それによると古代日本では形見として特に衣や鏡が用いられた。衣装は相手の身体そのものを表し、鏡は相手の姿を映し出す。それぞれ貴重な呪力を帯びた道具なのである。
恋歌にはしばしば「形見」という語が見える。これは通い結婚の当時の習わしで、形見の物無しには、逢えぬ夜を心穏やかに過ごすことができなかったのである。「形見」はまさしく相手の姿・形を見ること、またはそのための道具で、正真正銘の相手の像(中略)を、逢わずして、見させてくれるものであった。(森, p. 161)
形見の霊力は21世紀の現代日本でもまだ完全消滅してはいないだろう。ましてや奈良時代や平安時代の社会では大真面目に信じられていたとしても不思議ではない。
その3 水鏡の抒情性
形見としての鏡が出たので水鏡という概念を見よう。
古くからの民間信仰に根ざしているが、文学的的技巧の要素が強い。これは古代の歌謡に頻出する。水面を鏡に例える水鏡である。
©︎Y.Maezawa

自然界には、大は海や湖から、小は手の平サイズの水たまりまで鏡に似た働きをするものが無数にある。
『万葉集』には北部九州に配備された無名の防人の歌も多く採録されている。東国など故郷を遠く離れて任地に向かう兵士たちは後に残した家族に想いを馳せる。
川などの水面に映る己の姿を透かして愛妻の姿を懐かしく思い浮かべる。
わが妻は いたく恋ひらし 飲む水に 影さへ見えて 世に忘られず
(『万葉集』巻20、4322)
夫婦はひと時の逢瀬を楽しめたのだろうか。
©︎Y.Maezawa

『井筒』で語られる業平と紀有常の娘がまだ幼かった頃からやがてお互いが異性を意識する思春期へと成長する姿。
幼い二人が毎日のように屋敷の庭にある井戸の水面にお互いの姿を映して楽しんだ。二人が将来結ばれることは幼子の時期にすでに運命づけられていたのだ。
地謡 「あはれを述べしも理なり。
「昔この国に。住む人の有りけるが。宿をならべて門の前。
井筒によりてうなゐ子の。友達かたらひて。互に影を水鏡。
面ならべ袖を懸け。心の水も底ひなく。うつる月日も重なりて。
おとなしく恥ぢがはしく。たがひに今はなりにけり。其後かのまめ男。
言葉の露の玉章{たまづさ}の。心の花も色そひて。
(『井筒』p. 106-07)
©︎Y.Maezawa

終幕間際、荒れ寺(在原寺)で僧は仮寝をするが、夢に業平の形見の衣装を身につけた女(業平の妻)が現れる。夫の霊が憑依したせいで妻は自分と夫との見分けがつかないほど恍惚状態である。幼い頃毎日のように二人でしたように井筒をのぞき込むと水面(水鏡)に二人が幼かった頃の姿が映し出される。
優雅な序ノ舞の後、シテは井筒に近づき、その中を覗き込みながら、昔のことを改めて思い出し、感慨にふける。
シテ 「こゝに来て。昔ぞかへす。在原の。
地 「寺井に澄める。月ぞさやけき。月ぞさやけき。
シテ 「月やあらぬ。春や昔と詠{なが}めしも。いつの頃ぞや。筒井筒。
地謡 「つゝゐづつ。井筒にかけし。
シテ 「まろがたけ。
地謡 「生ひしにけらしな。
シテ 「老いにけるぞや。
地謡 「さながら見みえし昔男の。冠直衣は。女とも見えず。
男なりけり。業平の面影。
シテ 「見ればなつかしや。
地謡 「我ながらなつかしや。亡婦魄霊に姿はしぼめる花の。色なうて匂。
残りて在原の寺の鐘もほのぼのと。明くれば古寺の松風や芭蕉葉の夢も。
破れて覚めにけり夢は破れ明けにけり。
(『井筒』p. 110-111)
業平と仲睦まじく暮らした昔にかえりたいという妻の必死の願望が実現するのは思い出深い井筒のおかげである。いや正確にはその水鏡があればこそなのだ。
水鏡がはるかな時間を遡って夫婦の幸福だった日々を蘇らせてくれるのである。妻にとって水鏡に映じたものは幻影ではなく現実だと信じて疑わない。

©︎Y.Maezawa
さて『松風』の場合、塩作りのために桶に汲んだ海水が水鏡のイメージを生む。
©︎Y.Maezawa

「月は一つ」、「影は二つ、三つ(満つ)」のくだりは二人の海女姉妹にとって高貴の歌人行平は輝かしい月であり、月になぞらえられた行平の姿が二つ、三つ(滿つ)、四つ(夜)と増殖する。繰り返し小さな桶に汲まれていく海水が鏡(水鏡)となったためである。二人のためにまるで万華鏡のように輝かしい行平の姿が次々と出現する。逢瀬が叶うという至福の時が姉妹に訪れたのだ。
地謡 「それは鳴海潟こゝは鳴尾の松蔭に。月こそさはれ芦の屋。
シテ 「灘の汐汲む憂き身ぞと人にや。誰も黄楊の櫛。
地謡 「さしくる汐を汲み分けて。見れば月こそ桶にあれ。
シテ 「これにも月の入りたるや。
地謡 「うれしやこれも月あり。
シテ 「月は一つ。
地謡 「影は二つ満つ汐の夜の車に月を載せて。憂しともおもはぬ汐路かなや。
(『松風』p. 243)
先の防人の歌がそうであるように水鏡は現実的には不可能なことだが、愛する者どうしの逢瀬をもたらしてくれる。まさに魔法の鏡である。

©︎Y.Maezawa
「水鏡」の概念は時代を経るにしたがって庶民の俗信としてよりも文学的技巧として歌人の間で積極的に共有されるようになったのではないだろうか。
世阿弥は少年時代にエリート貴族で政治と歌道の両面で秀でた二条良基から和歌や連歌の手ほどきを受けており、水鏡の概念にも親しんでいたはずである。
その世阿弥の時代から六百年ほどたった1901年に近代日本画の大家横山大観が『阿やめ(水鏡)』と題した作品を発表した。池畔に佇む美女と白いアヤメを配して水鏡のイメージがみごとに生かされている。
このことは大観の「水鏡」に触れている美術史家Miriam Wattlesの論文を通じて知った。日本的美意識が霊力を帯びた水鏡に表象されているといえるだろう。

©︎Y.Maezawa
その4 廃墟・荒地が醸し出す詩的情緒
最後に、これも元来は一般民衆の間で共有された素朴な俗信だったと思われるが、知識階級に属する歌人たちが愛でようになったと思われるのが荒地や廃墟の概念である。
©︎Y.Maezawa

古代日本人にとって海、山、平地を問わず荒涼感漂う場所は神意、神威、霊威が顕現するのだと思えた。
古橋信によると『万葉集』を通して荒涼とした海辺、荒々しい波の打ち寄せる荒磯を見た古代人がそこに神威、神意を感じとる心がうかがえるという。
「荒磯が常世からの波の寄せ来るところ、つまり神の寄り着く所」なのである。(古橋, p. 31) 人間が近づくべきでない禁忌の場所なのだ。
『万葉集』には詠み人知らずのうたとして次の作品がある。
越す 波を恐(かしこ)み 淡路島 見ずや過ぎなむ ここだ近きを
(『万葉集』巻7、1180)
古橋は神威が現前するのは荒磯に限らず数多ある自然界の荒々しい場所だ と論じる。
霊威を強く感じる場所には近づいてはいけないはずである。荒野、荒山中もそうだ。特に荒野は開墾されていない野のことだが、それはできないというより、霊威が強くて近づいてはいけない野とみたほうがいいだろう。(中略)神が威力を発揮して、人間からみれば荒地なのである。(古橋, p. 32)
この荒地や廃墟観が『井筒』によく当てはまる。その舞台は荒れ寺。
世阿弥の時代はすでに荒廃していた在原寺といわれる。(井筒, p. 103)
松岡心平も作品自体が過去を現前化することを目的としている以上、舞台が廃墟とならざるをえないという。(松岡, p. 101-10)
シテ 「暁ごとの閼伽{あか}の水。月もこころ澄ますらん。
「さなきだに物の淋しき秋の夜の。人目まる古寺の。庭の松風更け過ぎて。
月も傾く軒端の草。忘れて過ぎしを。
忍ぶ顔にていつまでか待つ事なくてながらへん。げに何事も。
思ひ出の。人には残る世の中かな。
(『井筒』 p. 103)
©︎Y.Maezawa

荒れ寺という設定は神威、霊威が働くおかげで限られた時間ではあっても死者と生者が出会い、心を通わせることが可能になるという非日常的世界を現出させるために不可欠である。廃墟は成仏できずに生者にとり憑き祟る亡霊の巣窟ではない。
『松風』の浜辺も荒涼とした雰囲気に包まれている。
舞台は須磨の浦。この地は12世紀末に平清盛が短命で終わった都(福原)を置くまでは荒涼、殺風景、(水産物の採取や塩作りでかろうじて生計を立てる)貧寒の地というようなイメージが定着していた。
おそらくそのせいで『源氏物語』では光源氏の流刑地に選ばれたと考えられる。『松風』の不在のままの人物、在原行平も伝説では須磨に流されたという。
シテ ツレ 「汐汲車。わづかなる。うき世にめぐる。はかなさよ。
ツレ 「波こゝもとや須磨のうら。
二人「月さへぬらす。袂かな。
シテ 「心づくしの秋風に。海はすこし遠けれども。かの行平の中納言。
二人「関吹き越ゆるとながめたまふ。[海岸の湾曲したところ]の波の夜々は。実に音 近き海人の家。里離れなる通路の月より外は友もなし。
(『松風』p. 241)
しばらくして海女の姉妹に遠慮がちに宿を乞うた僧もあたりの物寂しさを痛感して、思わず遠い昔に故人となった行平に同情を覚える。
ワキ 「わくらはに 問ふ人あらば 須磨の浦に 藻塩たれつゝ 侘ぶと答へよと。行平も詠じ給ひしとなり。
(p.244-45, 出典『古今和歌集』巻18、962)
©︎Y.Maezawa

上記引用にある通り、流謫中の行平の味わった寂寥感、孤独感は癒しがたいものであっただろう。
古代中世の和歌に導入された概念を見てきた。
©︎Y.Maezawa

このように和歌や短歌に数多く見られる俗信から発展した文学的概念は他の諸々の同類の文化的概念とともに大きな貯蔵庫の中に蓄積され保存されているものである。
何世紀にもわたる歌人集団は適宜引用し改変しながら模倣し、引用する。
ここで再びデリダ的引用性を思い起こさなくてはならない。
引用という行為自体ではなく引用がもたらす広範囲にわたる影響・作用こそが問題である。作者が創造するものの、ドラマが始まれば何ほどかの自立性を発揮する死者としての主人公(シテ)は作者の意向も幾分か反映しながら、知の貯蔵庫からアイデアを引き出す。そうすることで自らの思いを他者(現世の人間)に伝える。
この他者は旅の僧(ワキ)ばかりでなく、ワキが代表するともいえる観客、さらに人間一般も含まれるだろう。
こうして語り(謡い)、舞うシテに接して広義の他者は心に深く感じ、心理的に動くことになる。
このような詩的言葉(文彩)が能舞台を越えて観客席さらに人間社会へと波及する構図は単なる引用(繰り返し)でなく、引用性という(創造的エネルギーを秘めた)概念でこそ可視化できるのではないだろうか。

©︎Y.Maezawa
おわりに
現代の日本人にとって能はすでに完成された至高の芸術の一種と見られている。観客に許されるのは個々の演者や演出の出来不出来を品定めすること。能楽研究者はといえば、正本相当と見なされている謡曲(能)のテクストを様々な視点から微に入り細に入り考察するのが主な仕事のように思える。
たしかに世阿弥をはじめ優れた作者が紡ぎ出した言葉や作品の構成は七百年近く経過した現在も人の心を打つだけの詩的喚起力を発揮しているといえるだろう。しかし、まるでおそれかしこむような能に対する見方は能が他者の介入を許さずそれ独自で存在価値を全面的に保持できるという排他的自己充足性を促進するのではないか。
これはかえって能本来の永続的な生命力を削ぐことになりはしないかと懸念される。
だが、言語一般についていえるように言葉の生命力は枯渇することがなく、たえず自己更新するものだ。
このような言語の自己活性化能力はオースチンの言語行為論によって実証されたものである。個人の発話が他者を行動に駆り立てるという言語の活気溢れる社会性があらわになる。
このような言語活動に本質的に備わっているダイナミズムを照らし出したのはオースチンの功績だ。
この言語活動のダイナミズムはデリダの提起した発話に必然的に伴う「引用性(あるいは反復性)」から生じる高い自由度と連動して、その結果ありとあらゆる状況に適した発話を可能にする。引用性がなければ発話はたえず新規に考案せざるをえず、従って意思疎通が不可能になる。繰り返し使われる言い回しは個々の発話において種々の言い回しと組み合わせることで時宜にかなった表現に仕立てることが可能である。反復が他者の想像力を刺激しない平板この上ない決まり文句に堕すかどうかは状況に応じた活気ある発話の創出いかんにかかっている。
さて『井筒』および『松風』における主にシテによる発話は民間信仰やおまじないなどを元にした比喩的表現、文彩を適宜用いている。個々の表現は作者の独創ではない。従来あれやこれやの名作和歌に繰り返し引用されてきたものである。しかし適切なコンテクストで引用することで表現の独創性が生まれる。
こうして完成された能のテクストは時の移ろいによって変化する(演者と観客を含む)人間の詩的感受性によって種々様々に受容される。
芸術鑑賞に正解はない。
先行世代の鑑賞のあり方がのちの世代によって効果的に発展させられることもあるだろうし、完全否定にいたることもあるかもしれない。
こうして何世代にも渡って緩やかに鑑賞の輪が広がっていく。
身分差を越えて人間の声を反映する『万葉集』において国民的とも言える詩的想像力を発露した古代日本の和歌の伝統。国民的広がりという言い方は古い。
昨今はインターネット上の動画で英語字幕付きで能公演が視聴できる時代である。国内外を問わず現代の人々はそれぞれ文化的境界を乗り越えて動画で提供される能舞台を通して古代、中世の日本の詩的想像力を鑑賞できる状況なのだ。

©︎Y.Maezawa
[参考文献]
オースチン、ジョン・L (2019). 言語と行為—いかにして言葉でものごとを行うか、飯野勝訳 講談社
Austin, John L. (1962). How To Do Things With Words. Oxford: Clarendon Press.
Blau, Herbert (2004). “Thinking History, History Thinking” Theatre Survey 45(2): 253-261.
Butler, Judith (1989). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge. http://www.lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble.pdf.
デリダ(2002). 髙橋哲也, 増田 一夫, 宮崎 裕助 訳 有限責任会社 法政大学出版局
Derrida, Jacques (1977). Limited Inc. Translated by Samuel Weber Baltimore: Johns Hopkins University Press. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2271128/component/file_2271430/content.
古橋信孝 (1988). 古代和歌の発生 東京大学出版局
穂積以貫 (1975). 大久保忠国 編 鑑賞日本古典文学 第29巻
井筒 (1983). 伊藤正義校注 新潮日本古典集成 謡曲集 上巻
池田彌三郎 (1973). 日本の旅人 在原業平 淡交社
古今和歌集全評釈 (1998). 全3巻 片桐洋一編 講談社
松風 伊藤正義校注 新潮日本古典集成 謡曲集 下巻
松岡心平 (2011). 能——大和の世界 山川出版社
森朝男 (1988). 古代和歌と祝祭 有精堂出版
大森荘蔵 (1992). 時間と自我 青土社
万葉集 (1998). 佐竹昭広, 木下正俊 校注・編 塙書房
Rivière, Joan (1929). The International Journal of Psychoanalysis 10.
坂部恵 (1990). 語り———物語の文法 弘文堂
野家啓一 (1996). 物語の哲学 岩波書店
Wattles, Miriam (1996). “The 1909 Ryūtō and the Aesthetics of Affectivity”, Art Journal 55(3) (Autumn, 1996), 48-56. (補注:「ryūtō=流灯」はインドから伝わった日本の灯籠流しのルーツである。)

(編集:前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。