交流の広場
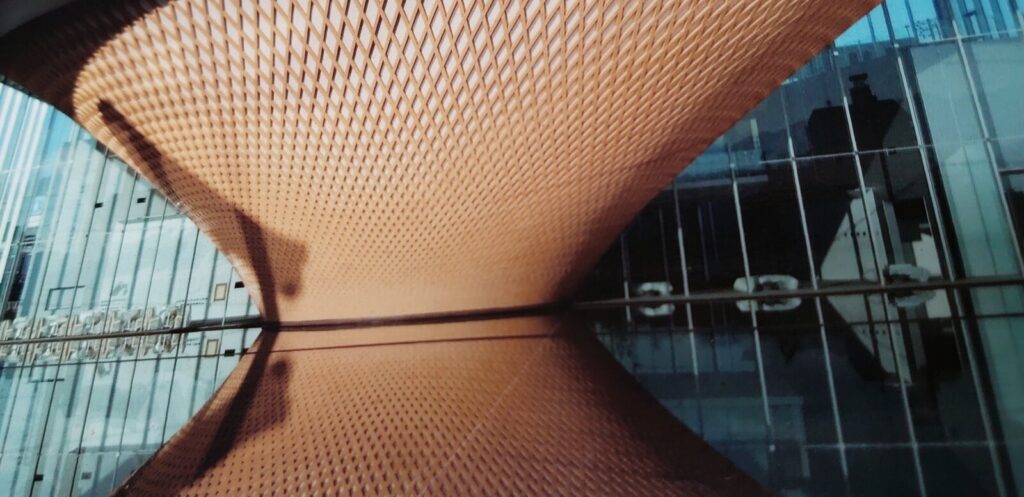
©︎Y.Maezawa
真理を求める「デカルト主義」を疑うべき理由
〜「『正解』なき世界の『バイアス』論」を受けて〜
聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 神経精神科
菅原一晃
はじめに
近年は認知科学が発展しており、英語圏を中心に多くの論者が認知面に関する著作を出版しています。この文章を書いている私も精神医学を専門にしていますので、これまで認知症・統合失調症・うつ病などの疾患から起こる認知機能障害を目にしてきました。また、患者家族から認知機能障害に伴うバイアスやものの見方の変化を聞かされたとき、辛く悲しい気持ちになったことも多々ありました。しかしその一方で、患者に向き合う医療者の側の「バイアス」に直面することもしばしばありました。今回、森下直貴先生(以下、森下先生とします。)の論考「『正解』なき世界の『バイアス』論」(老成学研究所ホームページ「活動の実績」掲載)に影響を受けつつ、医療者自身のバイアスについて考えてみたいと思います。
1. 真理を求めすぎる医療者
多くの人は真理を求めます。しかも性急に。どういうことかというと、医者をしていると特にですが、「うつ病って治るのですか」「牛乳って本当は身体に良くないのですか」「抗がん剤って毒なんですか」「子宮頚がんワクチンって打たない方がいいですか」などなど、診察の合間に聞かれることがあります。真理を性急に求めるのは、患者や受診をしない一般人だけでなく、医療者でも同様です。
例えば、学会で発達障害に関する発表を数年前にやったとき、発表とは全く関係ない内容で「自閉症には〇〇という特徴がありますが、先生はどう考えますか」と聞かれたことがあります。他の人の発表でも同様に発表に全く関係ない質問とか、「私の患者さんでこれに近い方で、〇〇で‥何ですが、こういうことに関してはどうお考えになりますか」と、発表とは全く関係なく自身の患者の解決を求める質問も多くあります。
©︎Y.Maezawa

それらに共通するのは「性急に答えを出したい(そしてそこから楽になりたい)」という態度です。これはこのようなことを書いている私もよく分かることです。医者はとかく孤独になりがちですし、同じ専門でないと話を理解してもらえないということが多分にあります。なので、ちょっとだけでもそういう機会があると、ここぞとばかりに場違いと思われかねないような発言をしてしまうのです。
しかし、自分を戒めるためにも書き連ねますが、大切なのは「真理は一つではない」と考え、疑うことではないかと思います。
2. 最近の健康ブームから
最近ブームになっているのは「食事をするのに低糖質が良いのか」です。あるいは、私たち精神科領域では「睡眠薬(ベンゾジアゼピン系)っていうのは認知症のリスクになるのか」「○○を食べれば認知症を予防できるのか」なんてものもあります。みんながみんな思っているのは「イエスかノーか」ということだと思います。けれども、「人による」ことって多いのではないかと私は考えています。
例えば、「気管支喘息の患者にβブロッカー系の降圧薬」は禁忌であり、断じて使ってはならないです。「抗うつ薬(フルボキサミン)に睡眠薬(ラメルテオン)」は併用禁忌ということは常に正解です。敗血性ショックの患者に対して用いる昇圧薬がノルアドレナリンだということは、「正解」として教科書に載っています。しかし、それ以外の多くの場合は「ケースバイケース」です。どうやったら患者が良くなるかというときに、正解がAでもBでもあるということはしばしば生じます。同じ病気で同じ合併症で年齢も血液型も同じ2人の患者に対して全く同じ治療しても、片一方は良くなり、片一方は死亡するということは全然よくある話です。
最初にあげた質問では、治るうつ病があれば、治らないうつ病もあります。牛乳が合う人もいれば害になる人もいるでしょう。私は無神論者ではありますが、「死後の生」がある人もいれば、「死後の生」はない人もいるということは、「普通にあり得る」ことだと思っています。糖質制限食が良い人もいれば、糖質制限しない食事が良い人もいるでしょう。とにかく、答えというのは本当に人様々だと思います。
最近、精神病理学の専門の先生の本を本屋で手に取りました。恐らく精神科医に向けてでしょう、「あなたの臨床は精神科の名に値するものか」といった内容が書いてありましたが、その著者自体の臨床はそもそもどうなのかと問いたくなります。もちろん患者をしっかり診る態度はとても大事なのですが、「精神科臨床=精神病理学」ではない訳であり、精神分析もあれば、薬物療法中心の治療もあります。〇〇療法という特定の療法でなくともうまく治療している治療者やケースだってあるわけです。「昔ながらの精神病理学的な臨床が最近ではないがしろにされている、現在のように薬物療法中心の治療はちゃんとした臨床ではない」というのは、あまりに偏り過ぎた考え方ではないでしょうか。
何れにせよ、「普遍的な真理」や性急な答えを知らず知らずのうちに求めてしまう傾向は誰にでもありますから、それに気づくというのはとても大事なことではないかと思っています。
©︎Y.Maezawa

森下先生は『システム倫理学的思考』第5章の中で、「論点」「解釈」「観点」「実践目標」という四つのステップを設定し、コミュニケーションの基本枠組み(四次元相関)に基づいて、関係者が論点や観点の相違を吟味し合い、全体の一致ではなく各々の自己変容を通じて対立をずらしていくという方法を提案されています。それに照らしてみれば、上記の例ではいずれもそのようなステップがなく、一気に結論にたどり着こうという性急さが見られています。
今回の「『正解』なき世界の『バイアス』論」ではさらに踏み込んで、問題は、観点の相違というより、観点が硬直化して見解が固定する結果、自分の見解が正解=正答であり、他の見解は誤解=誤答と考えてしまう傾向だと指摘されています。上記の例でも、自分が考えた答えが「真理だ」と言わんばかりに、他者の考えを排除することになってしまっています。その意味で、「観点」の硬直化というのは大きな問題であり、その背景にあるのが「真理がある」「正しい答えが(ただ一つ)ある」という思想ではないかと指摘しておきたいと思います。
3. 医療者にみられる「デカルト主義」
真理の性急な獲得と並んで、もう一点だけ触れていきたい傾向があります。それが「真理を求める際の態度」、つまり「デカルト主義」です。
私が基本的に働く場所は病院です。これまで大学病院、総合病院、精神科病院、また場合によってはクリニックなどで仕事をしてきましたが、いずれも医療現場でした。そこで感じたのが「どの人もデカルト主義者だなあ」ということです。同僚の医者のことです。
例えば外科では、手術中には「身体=モノ」と考えてやらなければなりません。もし「ここを切ると、その生命がどーのこーので」みたいに考えだすと、手術時間が長くかかり、かえって患者を苦しめることになります。それゆえ、手術に集中するためには現実的に「患者=動く身体=もの」と考えることが、逆説的に倫理的に必要な態度と言えます。
もちろん人間に対する態度としてはそれだけでは良くありません。しかし、医療者は得てして「デカルト主義」、つまり身体と精神を分けて考える傾向があるといえます。医者だけではありません。それ以上に看護師、さらには心理士に「デカルト主義者」の態度を感じずにはいられません。
ここでデカルト主義について説明します。ルネ・デカルトは17世紀を生きたフランスの哲学者あるいは自然科学者です。数学のXY座標を考案したのがデカルトです。それまで幾何学と代数学は別の学問でしたが、両者を結びつけたのがこのXY座標です。これによって代数式を視覚的に表せるようになったことは人類の歴史の中でも大きな出来事の一つだと思います。
さらにまた、数学以上に有名なのは『方法序説』のテーゼ、「我思う、故に我あり(コギト・エルゴ・スム)」です。私たちの感覚情報は欺かれやすく、確実なもののほとんどが疑わしいのですが、「疑うこと」「いまこの場所で私が考えていること」だけは疑えず、確実なことです。彼はその思想をテコにして、人間の身体に対する精神の優位性を定義し、「思惟」と「延長」、言ってみれば「精神」と「物質=身体」に分けたのでした。それ以来、現代脳科学などで言われる「心身二元論」の創始者としてデカルトは批判されてきました。
「デカルト主義」とは「身体」と「精神」を明確に分ける態度のことです。私はデカルト主義を退けるべきだと考えます。
「『正解』なき世界の『バイアス』論」から引用します。
統計学で以上の見地を受け継ぐのが頻度主義(無限回試行の確率計算)である。サンプルの選び方や真値からの推定量のズレによって系統的に誤差が生み出される。これが「バイアス」だ。
日常的思考が「偏向」とされるのは、数学的思考と物理学的(=科学的)思考における「真理」が「正解」として前提されているからだ。曖昧な日常的思考に比べると、それらの真理はたしかに厳密であり精密ではある。だが、その根拠を探っていくと個々の研究者の直観に突き当たる。
科学的真理の場合、仮説に始まり、一定の単純で厳密な条件の下で、データ→関係・規則の発見→解釈の比較検討→テーゼをへて、当初の仮説の証明と検証にいたる一連の手続きがある。この仮説の背後には研究者の理論的関心がある。ところが、それが真であることは保証されていない。
他方、数学的真理とは、理念的対象としての数の世界で発見される種々の不変の関係・規則性である。それらが真であることは構成可能性や、無矛盾性、美といった基準によって保証されている。ところが、数学的世界では日常世界を支える物理的条件が完全に無視されているだけでなく、基準の選択と正当化が数学者のセンスに委ねられている。
医療現場においては正解かそうではないかがはっきりしないことが多く、柔軟な観点が要求されますが、実際にはその観点が非常に固定されがちです。さらに一回の経験が「成功体験」となり、その観点の固定をより強めていくのです。
4. 臨床現場からの批判
私は総合病院にいますので、内科や外科や整形外科から相談されることがあります。
例えば、肺炎の患者で熱が40℃の状態だとします。普通の人でも熱が40℃あったら、頭がボーっとしたり、普段は考えられないことを考えたりしてもおかしくないでしょう。幻覚が見えるかもしれない。そういう人たちが落ち着かなかったり、暴れたりすることがある。そういう場合、看護師が私たちに「なんとかしてください」と依頼してきます。暴れたり、おかしいことを言ったりするのは、誤解を恐れずに言えば、「この人は頭がおかしいからだ」と思う医療者が結構います。
しかし、正確に言えば、発熱が起きると炎症が起きてサイトカインという伝達物質が産生されます。そしてその物質が脳内にある血液脳関門(BBB ; blood brain barrier )を破って脳に影響を与えることが起きます。それによって広い意味での意識障害(せん妄)を招くのです。
このような生物学的なメカニズムを理解しなくても、身体の病気から精神に影響するというのは、医学を学んだことのない素人でも分ると思います。しかし、最近は「むしろ医学を学んだことで」そういうことが分からなくなるのではないかと考えるようになりました。
看護師は「看護」のエキスパートです。そして何を看護するかと言えば、病気の患者、とりわけその身体です。「痛み」や「傷」といった所見、さらには血圧や体温といったバイタルサインを聴取し、どこがおかしいかを報告したり、ケアしたりすることに慣れていきます。また、患者が病気と闘って辛さを感じていることも学びます。怪我や重症の病気に苦しみ悩む患者と一番近い場所で向き合う職業、それが看護師です。
が、だからこそと言いますか、看護師も身体と精神は分けて考えがちです。身体に関しては訓練されてしっかりケアしつつも、精神面に関しては看護師の素顔が出ることがあります。もし、看護師が見ている患者がおかしいことを言ったとして、病気とその発言をどれだけ結びつけて考えられるか。精神科病棟の看護師でも怪しい場合があります。いずれにしろ、看護とは「身体のケア」のことなのです。もちろん「精神のケア」を専門にする看護師も多くいますが、身体と精神の両領域が強く隔てられているように感じずにはいられません。
また、心理士もその罠を免れません。心理士は身体と精神を分けた後の、身体を除いた部分にアプローチします。例えば、がんの患者や膠原病の患者の場合。患者が病気であることが分かり、そのことで落ち込んでいるとき、「患者が病気を知ったこと」で気分が落ち込んでいると大部分の心理士は考えるはずです。これはとても大事な要素であり、それだからこそ、患者に対して病気のことをどうやって伝えるかが大事になるのです。「あなたはがんで余命半年。もう手術もできない」とか、直接的に言ってはならないのは当然であり、どうやって患者が精神的な苦痛を和らげたり向き合ったりしながら、病気を受容するかを考えないといけないのです。
ところで、精神的な苦痛の背後には「病気それ自体の影響」があります。つまり、例えばがん細胞によって作られる炎症性物質による気分への影響や、膠原病によって作られる物質やホルモンの気分への影響のことです。しかし、心理士の場合、それらの影響が捨象されがちになるのです。学部時代に特に身体疾患の勉強をする機会が少ないため仕方がない面もありますが、心理士は精神を強調することでデカルト主義者になるのです。
要するに、考え方がどんどん固まり、身体と精神を分け、正しい答えがあるように思ってしまう傾向、つまり「観点の固定化」が再生産される場所が医療現場なのです。

©︎Y.Maezawa
5. 医学の進歩の罠
病院という場所は患者の病気を治すところです。そこには近代医学の200年以上の歴史があり、昔ならば治せなかった患者が良くなるようになってきました。そこには、身体と精神を分けて考える発想が基盤にはあります。身体を物質と考えるからこそ多くの発展がなされてきたわけです。
しかし、そうであるがゆえに、身体の疾患に比べて精神の疾患は様々な面で遅れがちです。はっきり言って診断さえも怪しいことが多くあります。また、身体より精神が高次であるという発想から、「精神は悪くならない」し、「精神がおかしくなるのはあり得ない、どうしようもない」という考えになりがちです。
そうした考え方の原因の一つは、医者や看護師や心理士ほかが「デカルト主義者」であるためだと思います。そうなると、どうしても患者の治療やケアが後回しになる傾向が生じます。医療者の態度が変わる必要があると思っています。
デカルトは『方法序説』や『省察』にて「絶対に疑い得ない」ものを探しにいきます。そして『方法序説』では「我思う、故に、我あり」、『省察』では「私はある、私は存在する」という確信=核心に至る訳です。
ただし、以前とある現象学者が書いたものを少し思い出すと、デカルト自身は「『絶対に疑い得ない』ものがある」ということを疑っていません。これは20世紀の哲学者ヴィトゲンシュタインの死の直前の『確実性の問題』とも関わる点ですが、どの水準で疑うかというのはとても大切なことだと思います。
医療者の場合には、身体と精神を分けて考えることで「疑いない身体治療」という後ろ盾によって安心感を得ているように思われます。しかし、そのように分けることの弊害が非常に大きいと感じることが、特に総合病院の身体的重症患者には多くあります。身体的に重症であるからこそ、精神的にも乱れやすいのに、精神面に配慮なされないというパラドックスがそこにはあります。
ここで「『正解』なき世界の『バイアス』論」の「行動経済学」を説明した箇所を引用します。
現状維持バイアスは、参照点を自分の現在の状態に置くことから生じる。このバイアスが働くと、確実なものとわずかに確実なものとのあいだで確実なものを選ぶ傾向(確実性効果)や、利得よりも損失を大きく嫌う傾向(損失回避)が発現する。また、同じ内容でも表現方法が異なるだけで意思決定に違いをもたらすフレーミング効果や、すでに所有しているものの価値を高く見積もる保有効果もある。
現在バイアスは、現状維持のうちで現在(時間意識)を参照点においたとき生じる。このバイアスが働くと、将来の利益を小さく見積もり、現在の楽しみを大きく見て優先する傾向(即時的快楽志向)が生じる。また、好まないことは計画しても実行を先延ばしする傾向も同様だ。
社会的選好のバイアスは、人間が他者の利得に対しても関心を持つことから生じる。ここで社会的とは社交的=共同的という意味だ。この種の選好には、他者の満足が上がることが自分の満足を高めることになる利他性、他者の親切な行動にお返しをする互恵性、所得や栄誉の分配が依怙贔屓に見られることを嫌う不平等回避がある。
限定的合理性とは人々が合理的ではなく直感的に判断する傾向であり、またヒューリスティックスとは安易な近道によって意思決定する傾向のことだ。前者の例は、サンクコスト(過去の埋没費用)へのこだわり、肉体的・精神的な疲労による意志力のにぶり、情報過剰負荷、選択過剰負荷、平均回帰に関する誤解、メンタル・アカウンティング(最初のデフォルトへのこだわり)等である。後者の例は、利用可能な身近な情報に頼る傾向、似た属性だけから一般的に判断する傾向、最初の情報を参照点にするアンカリング効果(係留効果)、上中下のうち中央を選ぶ極端回避の傾向、同僚や隣人の意見や行動に引きずられる同調傾向だ。
以上の四群の「傾向」は人間の日常的思考の現実=真実である。
このようなバイアスが常に医療現場では再生産されているのを感じます。
6. 病気の背後にあるもの
精神科医でドイツでも有名な木村敏が繰り返し書いていることの中に、「精神病(症状)の背後にあるもの」があります。
それによれば、精神病症状というのは本質的なものではなく、本当の病気があって、それに対して身体や精神が反応することによって精神病症状が出てくるということです。例えば、うつ病であれば、気分が落ち込んだり、食べても美味しくなかったり、寝ようとしても眠れなかったりなど、色々な症状がありますが、木村敏によればそうした症状は「うつ病」それ自体ではない。「うつ病」になったことに対して身体や精神が反応し、それによる症状が前述のような形で現れる。だから、明らかに分かりやすい症状に目を向けすぎては病気の実体を見失うし、目に見える症状だけを治療しようとしてはいけないという警告の意味合いもあります。
以上の指摘は個人的には納得しやすいものがありますし、臨床的に大切な視点だと思います。
例えば、風邪をひくと38度とか39度の熱が出ます。頭が痛いし動くこともできず、横になって寝ているしかできなくなる。ただし、この「高熱が出る」というのは「風邪そのもの」ではないわけです。ばい菌(細菌)やウイルスが身体に入り込み、疲労がたまって抵抗力が落ちていたりすると、身体の免疫システムがばい菌やウイルスを排除できず、身体の中で菌が増える状況になりします。それに対して身体も通常とは異なる形の免疫細胞を作って応戦します。その際、ある程度体温が高い方が免疫細胞が増えるので熱が上がります。
今とても簡単に風邪のメカニズムを書きましたが、発熱は風邪の原因でなくて結果なので、風邪を治したいからといって、熱を下げるために解熱剤を飲むのは本末転倒であり、自身の身体が免疫細胞を作ることを妨げることになり得るわけです。なので、病気においては「ある症状」が出て来たときに、それがどういうメカニズムで起こっているかを考える必要があり、特に原因と結果を履き違えてはいけないのです。これは精神科疾患だけではなく、身体疾患にも有用であると考えられます。身体と精神の原因を敢えて分けず、共通した病気の原因を措定することで、患者の病気は理解しやすくなるのだと思います。
ここで捕捉しますが、精神疾患の中でも「うつ病」に関しては「病気の原因」がよく分からないという面があります。例えば、「気分が落ち込む」ということの裏には、「仕事のし過ぎや睡眠不足から身体が悲鳴をあげている」ということがあるかもしれません。そのため、うつ病の患者には無理して症状を治そうとするのではなく、疲労をとるために休むことを奨励することが大切だというのは、とても理にかなっている考えだと思います。
ただし、統合失調症に関して木村敏は、妄想や陰性症状(本来ならばできるはずのことができなくなる)に関して、患者の生き方や実存的の危機のように意味付けします。統合失調症の症状だけにフォーカスするのではなく、生き方そのものに着目せよということです。
私が疑問に思うことは、うつ病と統合失調症とでは「精神病症状の背後にあるもの」の位相が、異なるのではないかということです。多分、神経症圏であれば、精神分析的な理解が要請されるはずであり、位相の水準が異なるはずです。これらの相違に関しては今後の精神医学の課題になるでしょう。しかし、いずれにせよ、病気の背景の「生命」、身体・精神両面に共通した要素を考えることは重要になると思われます。ここで森下先生が描く生命システムを前提にした考え方が要求されるはずです。
引用します。
それでは、人間本性の性向(バイアスⅢ)の根源とは何か。
私見ではその答えは生命システムに求められる。
環境との関わりの中で外部から内部を区分し、この区分を維持し続けることでシステムが形成される。内外の区分はシステムの本質であり、内部=自己の維持はシステムの内在的な目的である。情報の面からいえば、外部の複雑な情報を縮減しつつ、取捨選択することで内部=自己が成り立つ。とすれば、生命システムの存立は、それ自体が環境から見たら「傾性」になる。ここにバイアスの起源がある。これを「バイアスⅣ」と呼ぼう。
生命システムの「傾性=バイアスⅣ」を根源として人間本性の「性向=バイアスⅢ」が発現する。
そもそも医学を論じている以上全てが生命に関係しているのではないかと思いますが、実際のところ、医療者は「身体」と「精神」を二分して考えており、またその「観点」自体が固定され、それが「真理」だと思っています。そのような固定した見方を超える枠組みとして、生命の「内部」に関する知見が必要となってきます。木村敏のように(もっとも木村敏はそこまで言っていないかもしれませんが)、病気や目の前の現象の背後に身体・精神に共通する生命のシステムを考えることは重要であると考えます。
7. 結語
「病気の裏に必ず○○がある」という考え自体に関して、その解釈の水準をその時々で変えていく必要があります。そうすると、そもそもその何かが「病気の背後にある」かどうかがよく分からない、と言えるようになると思います。
月並みになりますが、それは「真理がある」ということを棚上げにする態度であると思います。
医療者は常に決断をしなければならない。そのためにはゆるぎない考えが必要だというのは確かにそうなのですが、現実問題として、身体と精神を分けること(デカルト主義)、そして「(誰もが納得できるであろう)真理を求めること」の弊害は著しくあると思うのです。
集中を要する現場では定まった考えかたを持ちつつも、その考え方を常に疑問視するという柔軟な態度が必要なのではないか思います。
引用します。
四次元相関のバランスの傾きは、各人が自分の観点を維持しつつも、特定の問題に対する自分の見解をたえず他者の異なる見解と比較する中で、観点の偏重(バイアスⅤ)を弱めて相対化することによって回復される。そのときバイアスⅥは消え、混乱と対立は解きほぐされるだろう。
森下先生の考え方には私も同意します。これは私が臨床においてずっと疑問に思っていることなのですが、今後も繰り返し考えねばならないことなので、頭に入れておくべきことと思っています。

©︎Y.Maezawa
(編集:前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。