活動の実績
老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学事始 > 【老成学事始】 Ⅰ 人生100年時代の生き方 森下直貴
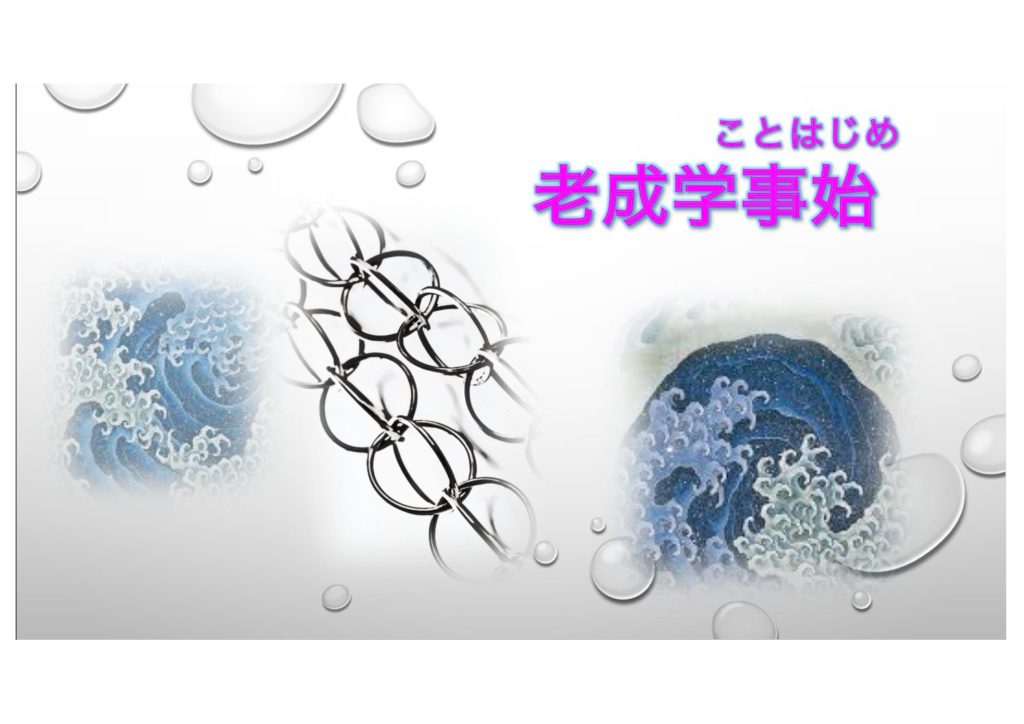
老成学事始
I
人生100年時代の生き方
老成学から「安楽死」を考える
森下 直貴
老成学は人生100年時代の老い方を探求し、
デジタル化された超高齢社会にふさわしい生き方を提案する。
提案される生き方は 多世代を持続的につなぐようなコミュニティ形成にかかわる。
そして その担い手として期待されるのは、現在の老人世代だけでなく、
それ以上に 将来の老人世代、つまり 現在の中高年や若者の世代 である。
つまり、すべての可能的老人だ。
さて これから 老成学事始の皮切りとして 尊厳死や自殺幇助を含む広義の「安楽死」をとりあげる。
しかし、なぜ「安楽死」か。
デジタル化された超高齢社会の今日、生きる意味を喪失した一部の高齢者のあいだで安楽死を切望する声が上がっている。高齢化の進展につれて、その声は今後ますます強まると考えられる。ただし、安楽死への関心は高齢者だけのものではない。自殺の延長線上に安楽死があるとすれば、難病患者や中高年や若者を含め生きづらさを感じる全世代に及んでいる。その一方で、生きる意味というより能力差別の文脈において安楽死のからんだ凄惨なテロ事件も起こっている。
安楽死を問題として論じる世間や学界の傾向をみると、死に方だけがクローズアップされたり、人工呼吸器・致死薬・鎮静といった医療処置にのみ関心が限定されたりしている*。しかし、死に方はそれまでの老い方から切り離せないし、老い方は人生後半の生き方そのものである。また、終末期医療は社会のさまざまな生活領域と連関し、それらの影響を受けている。超高齢社会の老い方、とりわけ最晩年期の老い方とその生きる意味との関連に注目する老成学にとって、安楽死の論じ方を問い直すことは避けて通れない課題である。
*医療処置に限定する傾向の典型は有馬斉『死ぬ権利はあるか』(春秋社、2018)である。本書は満遍なく論点を拾い上げ、論争をていねいに整理しているため、学術書として教えられるところも多い。しかし、老人自身の生き方や生きる意味を重視する老成学からみれば、死に方と医療者のふるまいと理論的正当化に限定する議論の設定は狭すぎる。本書については別の機会に詳細に論じる。
安楽死については、すでに『システム倫理学的思考』の第6章後半で「倫理の方法」の応用例として、生きがいの観点からとりあげている。ここでは視点を変え、生きる意味のコミュニケーションと能力差別のコミュニケーションのもつれ合いに焦点を合わせ、一歩ふみこんだ考察をおこなう。能力差別を構造的に制御する社会のなかで、一人ひとりがそれなりの役割を果たし、希望をもって生き、そして死ねるために、新たな安楽死論を提示したい(なお、文中では敬称を略させていただく)。
1 言葉の意味について
「どうせ死ぬなら、苦しまないで楽に逝きたい。」
安楽な死に方を求める思いは、漠然としている上に表現としても千差万別であろうが、死に方を問われたとき、おそらく多くの人が思い浮かべる願望であろう。一昔前の日本人なら「畳の上で大往生」という言葉がしっくりくるかもしれない(永六輔『大往生』岩波新書、1994)。また、「ピンピンコロリ」というあっけらかんとした表現もある。
ところが、その人類共通の願望は19世紀に西欧で誕生した近代医療のなかで、苦痛に苛まれている患者を前にした医師が「何らかの医療手段を用いて苦しまないで死なせる行為」へと限定された。いわゆる「慈悲殺」としての「安楽死(Euthanasia)」である。安楽死の元来の意味は古代ギリシャ語の「よき死(eu+thanatos)」であるから、この近代的な限定によって元の意味は、「よき死」から「安楽な死」へ、「安楽な死」から「苦しまないで死なせる行為」へと二重に屈折したことになる(松田純『安楽死・尊厳死の現在』中公新書、2019)。
ここで三点に留意しておきたい。まず、上述のように「安楽死」はたんなる「安楽な死」ではない。「(治療を目的とする)医療」とは認められていない(医師を介した)行為である。二番目に、安楽死の定義に世界標準はない。この点は「尊厳なき状態」を終わらせる「尊厳死」でも同様である(安藤泰至『安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと』岩波ブックレット、2019)。広義の安楽死には尊厳死や医師による自殺幇助も含まれる。最後に、安楽死の問題はもともと「よき死」をめぐる問題であり、したがって「よき生」に関する問題である。この点は老い方を考える上でとりわけ重要である。
2 安楽死問題の現代史素描
まずは、現代史における安楽死の社会問題に関して、日本社会の経験に的を絞って概観しておこう。
(一)安楽死が臨終の場面を飛び出し、瀕死の患者を「安楽死」させる社会運動となったのは、19世紀後半の欧州である(森鴎外「高瀬舟」1916)。時代の政治課題は下層民・移民・犯罪者・精神病患者等に対する包摂と排除である。これに正面から取り組んだのが「優生学」である*。20世紀に入るとそれは世界中に広まり、それに基づいて「断種」や「隔離」が行われ、さらにその延長線上で安楽死が遂行された。ナチスの安楽死政策では、その対象が患者から障害者へ、障害者から政治犯やユダヤ人へと拡大された。
*優生学(eu+genics)とは「生物の遺伝構造を改良することで人類の進歩を促そうとする科学的な社会改良運動」である。これは1883年のフランシス・ゴルトン(ダーウィンの甥)による定義であるが、20世紀になると遺伝子が発見されたため、遺伝子操作によって人間の改良を企てることに修正された。今日の生物学はあえて優生学とは名乗らないが、遺伝子レベルの操作を行なっているから、事実上の優生学を含んでいる。エンハンスメントやサイボーグもその延長線上にある。
ナチスの所業の全貌については最近の10年間でかなりの部分が明らかになっている(NHKBSプレミアム:フランケンシュタインの誘惑、2017.1.26)。ナチスはユダヤ人を大量殺害する前に知的障害者・精神障害者を安楽死という名で密かに殺害していた。これを「T4計画」という。公に遂行した場合の政治的デメリットを考慮して秘密に遂行したらしい。その作戦にはドイツの著名な科学者や多くの精神科医が関与し、犠牲者の数は20万人を超えると見積もられている。科学者たちは優生学に依拠して、隔離・断種の延長線上に安楽死を遂行した。安楽死の社会実験に真っ先に供されたのが、「社会のお荷物」とみなされた知的障害者や精神障害者である。
戦後になると、「ナチス=強制収容所=ユダヤ人絶滅=優生思想」という連想のもと、優生学と結びついた安楽死は一転して封印され、タブーとされた。「ナチス=ユダヤ人大量殺害=絶対悪」という言説は、戦後の国際政治における絶対不可侵の正義であり、日本人でも常識の一部となっている。欧米では今日なお「安楽死」という言葉そのものが忌避されている。
安楽死をめぐる状況が変わり始めたのは1970年代初めである。安楽死の要請はもともと病室から起こった。1960年代になると、延命治療の技術が飛躍的に進展し、終末期医療に大きな変化が生じた。その流れを受けてオランダなどの医療先進国では、延命治療の停止を含む広義の安楽死を求める運動が再燃したのである*。なお、英国では1967年、安楽死運動に対抗してホスピス運動が起こる。
*ここで疑問が生じる。「ナチス=優生思想=安楽死」という常識がありながら、オランダ、ベルギー、スイス、ルクセンブルク、カナダ、米国各州で広義の安楽死が合法化たり、事実上容認されたりしているのはなぜか。単純に考えると「安楽死」という言葉を隠しているからだといえるが、その他の理由は考えられないか。欧米社会はキリスト教を精神的基盤とする。カトリック教会は広義の安楽死を認めていない。容認する国々の多くはキリスト教のうちでもプロテスタントに属している。しかし、プロテスタント国のスウェーデンやドイツでも認められていない。それなら、個人や家族の捉え方の違いを考慮しなければならないのか。私見では、背景にあるのは、各人が自分の人生の主人公(主権者)であると考える文化的土壌である。その根本にはさらに自然環境の厳しさと共に生きる人々の助け合いと寛容の精神がある。宗教(プロテスタント)も家族の捉え方も、そうした土壌と精神に根ざしている。この点はあらためてとりあげる。
(二)安楽死を求める海外の動向はやがて日本にも波及し、70年代後半には安楽死法制化の動きが起こった。しかし、障害者団体を中心とする根強い反対運動を受けた。そのため安楽死法案は断念され、代わって1980年代半ばから(延命処置を差し控え・取りやめるという日本流の)「尊厳死」運動が広まった。潜伏を余儀なくされた安楽死は1990年代、東海大学医学部付属病院事件(1991年)を皮切りに、終末期医療の現場で事件となって表面化した。
1997年、小さいが別の動きがあった。「安楽死法制化を阻止する会」の発起人であった医師の松田道雄が『安楽に死にたい』を出版し、あえて老人と障害者を分けて論じてはどうかと提案した。90歳を超えて生き疲れを感じる老人には、優生思想は当てはまらないと考えたのである。しかし、松田の提案は衰弱した老人の気の迷いとして無視されるか、大義を曲げる変節として糾弾されることになる。
2000年代に入ると、国民的な規模で議論を続けてきた海外では続々と尊厳死を含む広義の安楽死法が成立した。これは潜在化した安楽死を法的にコントロールするためである。日本でも2007年、安楽死事件を防止するため、「尊厳死」を容認する終末期医療のガイドライン(厚生労働省)が作成された*。さらに2014年、尊厳死法案が公表されたが、根強い反対の声を受け、現在なお国会に提出されていない。
*これは2018年、地域包括ケアやACP(アドバンス・ケア・プランニング)に対応するために改訂され、名称も「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」となった。
(三)2016年、知的障害者施設(津久井やまゆり園)の入所者19人が殺害され、26(または27)人が負傷するという相模原事件が起こった。実行犯の青年は面会や裁判の中で、「コミュニケーションできない障害者(心失者)は生きる価値がない」から「安楽死」させるべきだと語った。その際、殺害ではなくむしろ安楽死させるべきだったと反省している(月刊「創」編集部『開けられたパンドラの箱 やまゆり園障害者殺害事件』創出版、2018)。
相模原事件は社会に衝撃を与えた。障害者の中には恐怖から体の震えが止まらない人も現れたという。この報道がきっかけとなってネット上を飛び交ったのが「ナチス=優生思想=安楽死」という言説である。この連想は欧米(Euthanasia=Euthanazia)や日本の障害学でこそ常識となっているが、日本の多くの人々にはそれほど馴染みがなかった。それが今回の事件によって表に出てきたのである(保坂展人『相模原事件とヘイトクライム』岩波ブックレット、No.959、2016)。
*なお、2020年3月、裁判が行われて死刑判決が出た。被告が控訴しなかったため刑が確定した。あたかも世の中は新型コロナウィルスで大騒ぎしていた。そのためか、あるいはかなり風化したせいか、事件当初に比べると、裁判を伝えるメディアの扱いは目立たなかった。
相模原事件と同年の12月、老人の安楽死を要請するエッセイが雑誌に掲載された(『文藝春秋』)。有名な脚本家・橋田壽賀子の『安楽死で死なせて下さい』(後に同名の単行本、2017)である。橋田は、認知症になって「自分をコントロールできなくなること」に恐怖を覚え、家族の負担や、周囲の迷惑、国家の財政破綻に配慮しつつ、高齢で生きる意味(目標)をもはや不要とする限り、死に方を選択する自由を認めて欲しいと訴えた。終末期のガイドラインはあるが、それでは本人の希望はかならずしも保証されないと考えたのだ。松田道雄の問題提起からすでに20年が経っていた。
相模原事件の直後ということもあって橋田の訴えは反響を呼んだ。医療関係者や障害者団体から轟々たる非難を浴びた。医療関係者は橋田の認識をたしなめ、障害者団体は橋田の考えを真っ向から拒否した。橋田が安楽死に関する発言を止めた(論争から降りた)ため、議論はそれ以上続かなかった。しかし、とくに高齢の知識人層からは共感をもって受け止められた(『文藝春秋』「安楽死は是か否か」アンケート、2017年3月号。結果は著名人60名中33名が賛成)。この共感の背景には28%を超える超高齢社会の現実がある。
超高齢社会は、一面では元気な高齢者が溢れているが、他面では自殺者が高率で存在している。人は生きる目標がなくなると、生きる意味(生きがい)を見失い、さらに生きる価値を見出せなくなる。そして絶望し、自殺を願う。ただし、自殺のハードルは高い。ならばどうするか。安楽死である。安楽死を合法化すれば、いつでも安楽死できるという安心が辛うじて日常を支える。「自殺」と「安楽死」は地続きでつながる。
いま、日本の各地の施設や地域で、生きる目標を見失っている老人が少なからずいる。2018年に入水自殺(自裁)した西部邁のように、安楽死に共感を覚えるとくに団塊世代の老人がますます増えている。いや、老人だけではない。中高年を含めて引きこもりは100万人に達すると見積もられている。人々は生きづらさを抱え、生きる意味を失い、自殺を念慮している*。
*自殺願望の裏返しが殺害である。それは日本だけでも、また老人だけの話ではない。たとえば、米国の男子学生が引き起こす大量殺害は、全世代の自殺率の上昇と関連している。とりわけ若い女性の自殺が急増している。問題の根源には、貧困や病気や宗教離れだけでなく、強い自己同士の競争に起因する生き辛さがあると指摘される(「自殺が他殺を上回るようになった米国の『病巣』」長野慶太、Forbes Japan, 2019.12.14)。したがってたんなる銃規制で済む話ではない。ちなみに、米国や英国、ベルギーではパラリンピックの女子アスリートが安楽死を選んでいる。
2018年、ふたたび社会に衝撃が走った。相模原事件の余震がなお続くなか、橋田から刺激を受けた51歳の難病患者がスイスで安楽死(医師による自殺幇助)を遂げたが、何とその様子が翌年にテレビで放映されたのである。これによって議論が再燃することになった。海外に目を転じると、米国各州を中心に広義の安楽死を認める国家や地域が最近になって増えている(宮下洋一『安楽死を遂げるまで』小学館、2017、『安楽死を遂げた日本人』小学館、2019)。
3 安楽死をめぐる二つのコミュニケーション
以上みてきたように、近代的な意味での安楽死(慈悲殺)は19世紀の臨床の場面で浮上した。20世紀の前半には優生学と結びついて国家政策となった。戦後は一転してタブーとして封印された。20世紀の後半ではふたたび臨床の終末期の場面で復活し、さらに法律の場面に移された。21世紀の今日、「生きる意味の喪失→自殺→安楽死」という流れが浮上し、患者や障害者だけでなく、老人と中高年と若者を問わず、すべての現代人の抱える深刻な問題となっている。
安楽死問題の現代史を通覧する限り、二つのコミュニケーションが重なり合い、もつれ合っていることが見えてくる。一つは生きる意味=自殺=安楽死のコミュニケーション(これをAとする)、もう一つは優生思想=国家政策=安楽死のコミュニケーション(これをBとする)である。
安楽死問題の中心はもとより臨床上のコミュニケーションAだが、そこにたえず公共領域のコミュニケーションBが介入し、両者がもつれ合うことになる。対立状況を切り向けるためには、AとBのもつれ合いを解きほぐさなければならない。両者が依って立つ前提を捉え返してみよう。
まずは、コミュニケーションAの主軸を分析してみる。これは「死ぬ権利」を容認する「死の自己決定」の思想であり、次の四つの要素から構成される。一つめは、自分の人生は自分で決めるという主権者・主人公の見地(A1)。自己決定は生き方だけでなく死に方にも及ぶ(ただし、J.S.ミル『自由論』では死に方は論じられていない)。二つめは、自分で立てた目標を実現することが人生に意味を与えるという見地(A2)。目標を実現できない場合、「生きる意味」、つまり自分らしさが消え、自分の人生でなくなる。こうなると、生きがい感(生きる意欲)を失うから「生きている価値」もない(A3)。であれば、もはや生きていても仕方ないし、苦しいだけであるから、死にたいと考える(A4)。以上を箇条書きにする。
A1 各人は自分の人生の主権者である。
A 2 生きる目標が生きる意味を与える。
A3 生きる意味が生きる価値を支える。
A4 生きる価値がないと死んでもよい。
A4の先は死に方に関する技術的な問題になる。自殺は大変で厄介である冷たいし、寂しい。嫌だ。周囲に迷惑をかけてします。だから面倒だ(『死の選択』)。できれば、法的にも認められ、周囲の理解もあり、医療の手法としては穏やか、確実、費用もかからない方がいい。それが安楽死だ。安楽死は手段の問題である。
続いて、コミュニケーションAを批判するコミュニケーションBをとりあげる。ここでもAに応じて四つの要素がある。まず、A1主権者の思想は独立した個人が想定されているが、人同士の関係から個人を切り離すことはできない(B1)。また、生きる目標と意味は多様であり、目標の実現ができなくなれば、別の目標に切り替え、「生きる意味」を修正することができる(B2)。さらに、「生きる価値」は個人の相対的な意味づけを超越しているから、たとえ生きる意味がなくなったとしても、「生きる価値」が消えることはない(B3)。それゆえ、自ら死ぬという選択は許されない(B4)。
B1 個人は他者との関係性の中にある。
B2 生きる目標や意味は相対的である。
B3 生きる価値は個人の意味づけを超える。
B4 いかなる場合でも自ら死ぬ選択はない。
関係性や生命の超越的価値という反対理由は、Aからすれば価値観の相違である。Bにとっての反対の核心的理由は、Aを突き詰めると、障害を持った人もしくは障害を持つことになる人の「生きる価値」を否定すること、つまり「命の選別」にある。安楽死の「合法化」が批判されるのも「命の選別」を促進するリスクがあるからだ。
しかし、Aでいう「生きる意味」という理由が「命の選別」を含意するとはどういうことであろうか。この点に拘ってしばらく立ち止まって考えてみたい。命の選別の前提にあるのは広義の優生思想である。そこで論点を次の二つに絞る。すなわち、コミュニケーションAがはたして優生思想に該当するのか(論点1)。そして、優生思想はなぜ規範的に否定されなければならないのか(論点2)。
4 優生思想の構造
論点1(Aは優生思想?)に対する答えは「優生思想」をいかに定義するかにかかっている。わたしが考える定義にしたがって話を進める。広義の優生思想を構成する要件は次の三つである。
まずは、「生まれ」によって貴賎・上下を区別する身分差別ではなく、優秀な人々を選別し劣等な人々を排除する「能力」差別である(①)。二つめに、優劣の能力選別は生物学的に遺伝子を操作することによって行われる(②)。三つめに、能力差別は「生きる価値」の査定(値踏み)にまでふみこむ(③)。その結果、査定には幅があるが、かりに査定が全面否定なら生命剥奪(安楽死)にいたる(④)。
① 優劣の能力差別
② 生物学的手段(遺伝子操作)による選別
③ 生きる価値の査定(値踏み)→ ④全面否定なら死
上記の要件に照らして「自発的な安楽死」を検討してみよう。自発的な安楽死は、①「自分の目標を実現できなくなった」ために「生きる意味」を見出せず、そこから③「生きている価値がない」と考えて絶望し、④何らかの医学的な手段に頼って「安楽死」を遂行することである。この④安楽死の遂行が②生物学的な介入(断種)の延長線上にあるとみなせるなら、その行為全体はたしかに広義の優生思想に当てはまる、といえる。
自発的な安楽死を希望する理由には、橋田壽賀子も説明するように、生きる意味の喪失だけではなく、世話をしてくれる人の負担への配慮、寝たきりの自分の惨めさと世話されることへの抵抗感(プラ以後)、医療費の高騰は社会的公正もある。しかしこれらの点はしばらく脇におく。ここで視線を絞り、あえて次の疑問を投げかけてみたい。自発的な安楽死が広義の優生思想に該当するとして、そのことがなぜ規範的に否定されなければならないのか。これは論点2(優生思想はなぜいけないのか)である。
さしあたりいくつかの答えが浮かぶ。安楽死という方法は、周囲(とくに医師)を巻き込んでストレスをかけ、法律化されると強制的になり、看取りの文化としてみても継承されにくい。その点では人々の拒否反応の根強い自殺に類似する。あるいは、安楽死を含む生物学的介入は身体に不可逆的な影響を与え、内側からの変容と違って主体性を消してしまう。それゆえ、伝統的に能力開発の方法として生物学よりも教育が好まれてきた。
しかし、以上の答えは「優生思想ゆえの安楽死」を規範的に否とするものではない。決定的な理由は、③生きる価値の値踏みである、その値踏みが④全面否定になる場合、②の延長線上に④自殺や安楽死が浮上する。それでは、③からどうやって④に進むのか。「生きる意味」を喪失するからだ。なぜ喪失するか。それは①能力差別が前提にあるからだ。
要するに、広義の優生思想が規範的に否定される根本の理由は能力差別にある。とすれば、そもそも能力差別はなぜいけないのか。もう一歩ふみこんで考えてみよう。
5 能力差別の根源:集団であること
能力差別という事柄は単純ではない。能力差別と一口に言っても、そこには相対的差別と絶対的差別の区別がある*。
*機能的な能力差別(格差)以外に、身分差別、集団の仲間/敵の差別、身体に関わる穢れ差別がある。四者の関係についてパンデミックとからめて別の機会に考察する。
相対的差別は比較の視点から生じ、「生きる価値」を全面否定することはない。能力に応じた役割を割り当てる適材適所を旨とする。ちなみに、身分差別の文脈でいえば、ヒンドゥー社会の約800を超える職種(ジャーティ)が相対的差別に当たる。
それに対して絶対的差別は生きる価値の全面評価、つまり「命の選別」をおこなう。全か無か、生か死である。ただし、この絶対的な能力差別はきわめて稀であり、社会環境に余裕のない危機の時代に、相対的な能力差別から転化する。その一例が、寒村の棄老伝説を描いた『楢山節考』である。家族環境に余裕のない「水子」も同様である(『水子』)。現代国家は福祉制度によってその種の命の選別を極力回避する*。
*新型コロナウィルスの感染に対して発動されるトリアージの場合、事態が切迫していない段階では患者は症状に応じて区別され、重篤の患者から優先的に処置されるが、事態が切迫して極限の段階に進むと、命の選別が行われ、瀕死の重症患者は処置の対象から外される。
能力差別はそもそもどこから発生するのか。「能力」をここでは大まかに「何かができること」としよう。「できること」には、単純な動き(握り)から、一連の動きからなる動作(素振り)、一連の動作からなる行為(打球)、一連の行為からなる活動(ゲーム)にいたるまで、種々のレベルがある。能力が問題になるのは生活の場面では活動である。能力は多次元にして多水準であり、個人差が大きい。個々人の能力は持って生まれた才能と環境と個人的な努力の協働の結果である。
*人間の活動は人同士の相互的なコミュニケーションである。この点の確認はここでの考察の結論に関わって重要である。人間の活動は「生L」のレベルでは「生活L2」に対応し、四次元相関の思考法を適用すると16分野に区別される。以上については『システム倫理学的思考』の第3章、第4章、第7章を見られたい。
能力の優劣の区別は多数の人々がいる限りなくならない。しかし、区別は差別ではない。区別とは異なる差別は社会集団の中で構造的に産出される。差別は社会集団の機能目的に沿った価値の序列化である。四次元相関の思考法によれば、構造的差別を生み出す社会集団は機能目的の違いによって四つの類型に分けられる。すなわち、Ⅰ実用性次元の類型、Ⅱ共同性次元の類型、Ⅲ統合性次元の類型(北朝鮮や中国のようなイデオロギー国家)、Ⅳ超越性次元の類型(イランやインドのような宗教国家)である。
今日の日本では、差別を構造的に生み出す社会集団として二つが想定されている。その一つは効率重視の機能的な社会である(資本主義社会とも呼ばれる)。これは実用性の次元の類型である。ここでは有用性・効率性の観点から、能力のある人(強い自己)/能力のない人(弱い自己)という構造的な差別が生み出される。このなかでは「強い自己」でなければ競争に勝てないし、組織から切り捨てられる。弱い自己では生きていけない。頑張ろうとしてもできない時、人は絶望して自殺する。
もう一つは同調圧力の強い集団主義の社会(日本社会が典型とされる)である。これは共同性の次元の類型である。ここでは集団の和(調和・秩序)の観点から、平均的な人/並み外れた人という構造的な差別を生み出される。このなかで「わがまま」と「のろさ」は「迷惑」として嫌われ、過度の平均主義=平等主義が蔓延する。平均的な自己から外れた強すぎる自己や弱すぎる自己の排除が、いじめや引きこもりの温床となる。障害者を含めて異人に対する日常的な差別が起こりやすいのは、効率重視の社会よりも同調圧力の強い集団といえる。
以上の二つの社会集団のいずれにおいても、平均の自己/強い自己/弱い自己といった差別が構造的に生み出される。両者に共通するのは、唯一「集団であること」である。つまり、集団であることが相対的な能力差別の構造的な根源ということになる。
一般に社会集団は自己を維持しようとする。そのために成員を守る一方で成員を切り捨てる。集団が危機の時その本性が露呈する。切り捨てられるのは、異なる意見を唱えて団結を乱す者、個人の自由を唱える者、足手まといとなる者等である。集団は平時には平均人によって運営され、強い人を嫌って弱い人を保護するが、非常時には平均人は役に立たず、強い人が求められ、弱い人は捨てられる。
安楽死の前提には能力差別があり、能力差別の根元には集団がある。能力差別は集団の宿命である。人は集団の外では生きられない(だから人間である)。私たちがふだん、薄められた形であれ「内なる優生思想」を払拭できないのは、集団を自明の前提として生きているからである。いや、そういうふうにしか生きられないからである。とすれば、「ナチス=優生思想=安楽死=絶対悪」に寄りかかるだけでは、優生思想と根本から対峙したことにはならないだろう。ナチスもまた民族「集団」を強調したからである。
6 老人の生きる価値
集団であることが能力の構造的な差別の根源である。人々の能力の区別は能力の相対的な差別に転化する。この日常的な転化を避けることはできないが、両者の差異を知ることはできる。また、能力の相対的な差別はときに絶対的な差別(つまり命の選別)に転化する。しかし、その転化を防止し回避することはできる。
能力の区別→能力の差別(相対的差別→絶対的差別)という事態を洞察するなら、安楽死をめぐってもつれ合う二つのコミュニケーションの本質的な難点を指摘することができるだろう。両者とも、その帰結は「生きる価値」であり、その前提は「能力差別」である。
コミュニケーションAでは、能力区別と能力差別の差異が考慮されず、転化した能力差別がそのまま個人化・内面化されている。そのため、生きる目標が固定され、生きる意味が柔軟に受け止められない。その帰結が「生きる価値」の自己否定である。
それに対してコミュニケーションBでは、能力の相対的差別と絶対的な差別の差異が考慮されず、能力差別から切り離された能力区別が想定されている。そのため、相対的な差別の存在が否定され、またそれに伴う生きる意味づけの多様性も認められない。その帰結が「生きる価値」の無条件的・絶対的な肯定である。
両者のもつれ合いを解きほぐすために必要なのは、まず、集団のなかにいる限り相対的な能力差別は避けられないという冷厳な現実を知ることである。その上で、能力区別と能力差別の差異、相対的な能力差別と絶対的な能力差別の差異を知り、三者の不可逆的な転化を制御することである。
ここで私たちは壁に突き当たる。三者のあいだの差異の維持ならびに能力差別の絶対化の防止・回避を制御する社会集団、これを短縮していえば、能力差別を構造的に制御する社会集団はそもそも実現可能なのであろうか。その鍵を握るのは担い手である。社会集団には担い手がいる。担い手に実現可能性がかかっている。それでは、誰が先発的に担うのか。老成学が期待を寄せるのは老人である。それも現在の老人世代だけでなく、将来の老人たるべき若者世代である。しかし、なぜ「老人」か。
老人たちはいま、世話受動や自己能動から完全受動や自己放棄までの老いの姿のスペクトルを見せている。その中で死に方の選択肢は三つに絞られる。平穏死と呼ばれる安楽死か、自分の意志で生(自己)を終える安楽死か、身体を捨て機械体の中に永遠の生(自己)の居場所を求めるサイボーグ(「ピーター2.0」)か。それらに共通するのは、死に方と老い方と生き方を切り離す分離の観点である。しかし、分離の観点から偏った生きる意味しか生じない。
生きる意味は生きる目標を持って活動することから生まれる。生きる意味を持つことで生きがい(生きる意欲)が感じられる。人が生きがいを感じるのはとりわけコミュニケーションの中で一定の役割を果たすときである。その中で尊敬が生じる。たとえ90歳を超えていても、人は老い抜く姿を同輩の仲間や若い人に見せることはできる。これを人生の役割として捉え直すことができれば、どれだけ無様な醜態をさらけ出そうと、老い抜く姿を見せる中でつながり合いが生まれ、そこに尊敬の念がともなう。「尊敬に値する老い方をしたい」という願いが老いを生き生きとしたものにする。
老人は、健常者であると同時に障害者であるが、徐々に後者の比重が増してくる。したがって老人に当てはまることは障害をもつ人一般にも通用する。いかなる状況やどのような状態であろうと、人は生きている限り、世代をつなぐ役割を担っている。いや、それは死んでからも生者とのコミュニケーションの中で役割を果たす。その役割はむろんさまざまである。コミュニケーションAによって安楽死を提起した松田道雄や橋田壽賀子に欠けていたのは、一人ひとりが生き抜き、そして老い抜く中で、みずからの姿を若い世代に提示することを通じて、尊敬に値する人になるという、つながり合いの観点である。
(編集:前澤 祐貴子)