活動の実績
老成学研究所 > 初代所長 森下直貴 作品群(2018 09〜2022 12) > 老成学 > 【老成学 研究資料】⑶ 「老年学の父」バトラーの見た「老人問題」 森下直貴
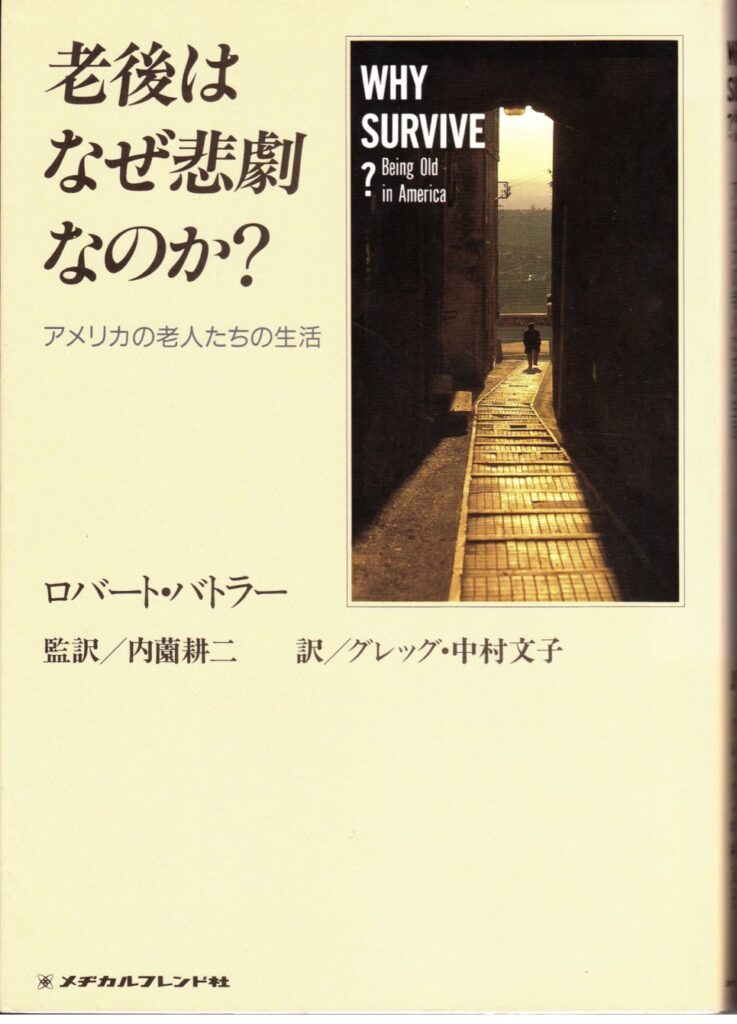
【老成学 研究資料】 (3)
「老年学の父」バトラーの見た「老人問題」
人は何のために長生きするのか
「エイジズム」を相対化する
森下 直貴

はじめに
高齢社会に特有の「老人問題」が登場したのは工業先進国では1970年前後である。背景には戦後世界で同時に進行した経済成長がある。
1970年の時点で高齢化率7.1%の日本には『恍惚の人』が現れた。
高齢化率12%のフランスではボーヴォワールの『老い』(1970年)が出た。
そして高齢化率10%の米国では
ロバート・バトラー(Robert N. Butler)の『老後はなぜ悲劇なのか—アメリカの老人たちの生活』(1975年)
が周到な研究の末に出版された。
これら三冊はいずれも先進工業国における「老人問題」の名著である。
高齢社会に特有の「老人問題」とは、長寿で健康な老人が大量に出現する中で、核家族化・単身化によって家族の介護力が弱体化し、それを補うために社会保障制度の充実が求められる一方で、長生きすることの意味が一人ひとりに問われるようになった時代の社会意識である。
もちろん経済成長以前の時代にも老人はいたし、それなりの問題も生じていた。しかし、ここでいう意味での社会「問題」として意識されていたわけではない。
なお、厳密には高齢化率7%以上が「高齢化社会」、14%以上が「高齢社会」、21%以上が「超高齢社会」と呼ばれる。
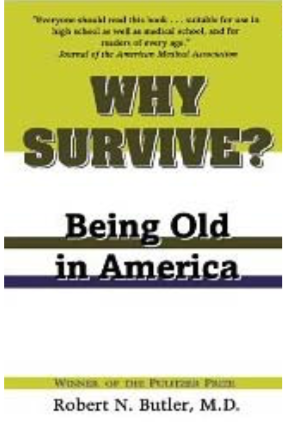
前回の『恍惚の人』に引き続き、今回はバトラーの著書を取り上げる。
日本語版は1991年に出版された(監訳/内薗耕二、訳/グレッグ・中村文子、メヂカルフレンド社)。上下二段488頁の大作である。原題はWhy Survive? Being Old in America, Harper & Row Publishers, Inc., 1975. 直訳すると「なぜ長生きするのか?」。1976年度のノンフィクション部門でピュリッツァー賞を受賞している。

バトラーという老年精神科医は「エイジズム」の名称を創り、米国老化研究所の初代所長としてアルツハイマー病の啓発運動を展開し、「プロダクティブ・エイジング」を提唱した。
そこまでは私も知識として持っていたが、「老年学の父」として彼の名を世間に知らしめた本書を直接読んだことはなかった。
このたび「老人問題」の原点に立ち還るという研究目的から、実際に本書を読んでみて驚かされた。
1970年代の時点で「老人問題」をこれほどまで包括的に捉えた研究者がいたのだ。

昨今、『ライフシフト』や『ライフスパン』という翻訳書が話題となったが、本書はそれらをすでに40年も前に先取りしている。
包括性や先駆性だけでない。細部の具体性、提案の現実性、人間洞察の深さなど、どれをとっても瞠目に値する。
ただし、老成学の視点から見ると「エイジズム」という視線そのものには疑問が生じる。
老成学の基軸を固めるために本書を研究し、これと比較する作業は避けて通れない。
以下、(老年学の専門外の読者のために)私の関心に沿って本書の要点を紹介しつつ、私自身の個人的な体験を交えた【私のコメント】(文中太字)を書き添えた上で、バトラーの「エイジズム」の視線に対して批判的な考察を試みる。
※引用の頁付は日本語版による。
1 本書の構成
原著の序文(1975年)と日本語版序文(1991年)には本書の構成が示されている。
① 死の前には老いという長い時間がある(ⅷ)。
1970年当時、米国の人口の10%、2000万人が65歳以上だった。また、平均寿命は1900年の47歳に対して71歳に延びた。
ところが、老いの時間の延長は老人を幸せにしない。却って老人の社会的地位を低下させるばかりだとバトラーは指摘する(ⅷ)。

なぜか。
老人は社会にとって基本的に邪魔者だからだ。
そのため老人はこれまで長らく社会の犠牲となってきた。長生きするとますますそうなる。
しかし、「現代においても一つの年齢層を別の年齢層のために犠牲にする必要はあるのか」とバトラーは問いかける(xv)。

② 問題の根源にあるのは「エイジズム(Ageism)」である。
この言葉をバトラーは1968年に作った(ⅰ)。
その意味は、「歳をとっている」という理由で老人たちを組織的に一つの型にはめて差別することだ。
この老人差別が社会の常識である限り、老人たちがしばしば貧しく、社会・経済的苦境に立たされている事実は無視される(15)。
③ 本書は、「エイジズム」批判の見地から、1970年代前半当時のアメリカの老人が体験している現実を描いた上で、
老人問題をめぐる政治課題を明確に打ち出しながら、バトラー自身の解決法を具体的に提示する(xvi)。
④ 本書を通じてバトラーが最も重要だと考えるのは、「老人は何のために生き続けるのか」「なぜ長生きするのか」という問いである。
これが原著の題名になっている。
これに対して彼自身の答えはこうだ。

老人は先に死ぬからこそ、「前の世代の文化、つまり価値観や感情を次の世代に伝達することに責任を負っている」(ⅷ)。
二つの序文に続く本論の章立てを掲げておこう。
これらを眺めると「老人問題」がいかに網羅的に論じられているかが分かる。

第1章 アメリカの老人問題の悲劇
第2章 老いると貧しくなる豊かな社会
第3章 年金はどうなっているのか?
第4章 働く権利
第5章 住む場所がない
第6章 もう待ち時間はない
第7章 満たされない処方箋
第8章 「呆けているだけさ」

第9章 死の家は大繁昌
第10章 犠牲にされる老人
第11章 老人の問題解決と政治
第12章 人生の贈り物
第13章 人生を解きほぐそう
第14章 年をとって馬鹿になる
2 老後という悲劇
多くのアメリカ人にとって老後は「悲劇」だが、その背後には「エイジズム」がある。
① 「悲劇」とはどういうことか。誰もが老いて死ぬということではない。老いへの道のりが「無自覚、無知、貧困のために、不必要なまでの耐え難い苦痛や、侮辱、無気力、孤独なものになってしまった」という事実なのだ(4)。
しかも、人生前半が順調だった人の老後にもその事実が当てはまる。さらに、女性(未亡人)の場合は事態がより深刻である(7)。

② 悲劇の背後には老人をめぐる相矛盾した二つの見方がある。老人は、一方で「大先輩」「シルバー市民「黄金年代」と持ち上げられるが、他方で「どんどん衰えている」「しおれている」「排水溝に流す」「終わった」「時代遅れ」「旧式の古いツボ」「旧弊」「わからず屋」「風変わり」「丘の彼方」「牧場に放つ」などと軽蔑される。それらは希望と恐怖が混合した偏見である(3)。
老人に対する偏見から固定観念が生まれる。例えば、思考は遅く動作ものろい、独創性がない、過去にしばられ、変わることがなく、過去に生きる、保守的、第二の幼年期、利己主義、イライラして付き合いにくい、時代に取り残される、衰えそのもの、減退、無気力、無関心、死を待つばかり、社会や家族にとってさらに老人自身にとっても重荷、等々だ(9)。
③ しかしバトラーによれば、老後の本質は惨めでも荘厳でもない(9)。

歳をとればとるほど個人差は大きくなるものだ。生産的な人も多い。非生産的と見えるのは喪失体験や、病気、環境の影響のせいである。孤立や、適応性の欠如、硬直化は個人の性格によるところが多い。「呆け」は多様な要因から起こる(9〜14)。

④ 深刻なのは老人自身が偏見や固定観念を受け入れ、自分自身を否定的に見ることだ。自分自身を老人とみなすことを拒否する態度もそこに根ざしている(17)。
老人の価値を否定する「エイジズム」の社会環境の中で、老人と若者は互いに偏見を持ち、間に立つ中年層の責任と負担が増すことになる(19)。
【私のコメント】
前回取り上げた『恍惚の人』の主人公の舅(84歳)は、「偏屈」「嫌味」「無教養」「辛い嫁いびり」と描かれている。
他方、両者の間に入って取りなした姑は「優しい」とされる。
また、1995年出版の佐江衆一作『黄落(こうらく)』では、登場する老人(94歳)は「狡猾」「猜疑心」「好色」「嫌らしい」と表現されるが、姑については「チャーミング」と語られる。舅はどちらも「明治の男」とされる。
3 貧困・年金・住宅・サービス
バトラーが真っ先に取り上げるのは貧困だ。
ここには年金、住宅、医療を含めた各種のサービスが関連する。

① 大半の老人は老後にはじめて貧しくなる(31)。
② 老人の大半は年金生活者である。米国にも基本国民年金制度が必要だ(69)。
③ 老人の住宅問題は一般に考えられているよりも深刻である(126)。
住宅問題の核心は我が家(マイホーム)、つまり居場所があることだ。人によって居場所の構成や範囲は異なってくるが、居場所という点が施設に移ることへの抵抗感を生む(122)。
ニューヨーク市の場合、住民の13%に当たる100万人の老人がいるが、そのうち70%が賃貸アパートで暮らしている。その多くは未亡人であり、エレベーターなしの3、4階のワンルームに住んでいる(132)。
借家では年金生活者には家賃が重荷になる。他方、自宅では身体が不自由でも維持活動が必要になるし、資産価値は低下し、公共料金や維持費はかかり、固定資産税が家計を圧迫する。
退職者コミュニティでは老人だけで暮らすよりも、あらゆる年齢階層、社会階級、民族、人種の人たちと混ざって住むことが望ましい(141)。
住宅は人生の各段階に対応するように効率的に計画されるべきである(160)。

④ 人並みの老後を提供するには、交通・医療・公共住宅といった公共・社会サービスも必要だ。そうすれば貧しくても残酷さや恐怖の度合いが少なくなる(44)。
サービスには、ホームヘルプ、情報・照合、栄養、医薬品、交通、通信、法律、保護、税申告、レクリエーション等がある。ところが、それらは往々にして分断され、限りがあり、老人にとって差別的だ。しかも、老人は自分の番が来るまでひたすら「待つ」のが当たり前だと考えられている(164)。

各種サービスの現状を変えるにはどうすればいいのか。
バトラーは、老人自身が協同組合や自助組織を通じて、他の老人にサービスをもたらす試みを提案する。それは余力的で付随的ではあるが可能性はあるという(199)。
【私のコメント】
『老後破産』(NHKスペシャル取材班、新潮社、2015年)に出ていたフレーズを思い出した。
「老人問題のほとんどはお金で解決できる」230頁。
貧困に関しては岩田正美氏の著作が参考になる。
それによると、日本では「生活保護」基準が社会保障制度一般の事実上の標準基準となっていて、その中身は一般消費水準のほぼ6割だという。
金額ベースでいえば、大都市の場合は一人約13万円、医療費などが無料になるため、合計で17〜18万円程度になる。

老人問題に限らず、社会問題の土台は「貧困」である。
ロスリングの『ファクトフルネス』では、一人当たりのドル収入に応じて世界の現実が四区分されている。
先ごろインド映画の「スラムドッグ&ミリオネラー」を観た。その中にホームレスの孤児を乞食にして搾取する組織の親方が子供の目をわざと潰す場面が出てくる。
その瞬間、15年前のインド旅行中に東部ビハール州のパトナ駅で見た光景が浮かんできた。箒を持ってプラットホームの下から這い上がってきた少年の目も潰れていた。生まれつきではない。潰されていたのだ。

バトラーと同様、私も以前から住宅問題に注目してきた。
早川和男『住宅貧乏物語』(岩波新書、1979年)によれば、日本の住宅政策は経済政策の一環であり、スクラップ・アンド・ビルドのできる戸建て主義(マイホーム主義)を特徴とする。そのため公共住宅の供給量が少なく、劣悪な条件の民間アパートに頼ってきた。
ところが現在、全国津々浦々で空き家が急増し、関係省庁で対策を検討中という。
住宅問題は低所得層政策と合わせて総合的に取り組む必要がある。この点がベーシック・インカムの考えに欠落していると思う。
住宅と人生の段階との対応に関してはスウェーデンの住宅政策は参考になる。子育て期は郊外の庭付き一戸建て住宅に住み、高齢期にはそれを手放して街中のアパートで暮らす。老人も街中で買い物や散歩ができ、人との交流の輪も維持できる。老化が進むとアパートを改造した少人数のグループホームに移る。近所には看護師や医師も住んでいる。
【私のコメント】

たとえ貧困であっても、住宅や各種のサービスが充実していれば悲劇の度合いは減る。これは至言である。
ただし、老人は受給者として受け身一方であってはいけない。老人自身が立ち上げ運営する協同組合というアイデアは、老成学が強調する老人同士の互助にとっても重要である。
日本では実際に老人が主体となって町おこしのための協同組合を作っている例がある。

4 仕事と教育
老後には老人に適した仕事が必要だが、
そのためには社会の仕組みと人生の設計を変えなければならない。
① 65歳以上の就労は老人自身の生きがいのため、そして社会の負担比率の維持のために必要である(81)。
② 老人に適した仕事の分野がある。
もちろん決まった型にはめ込むべきではないが、人生の経験と老年期の現実を考慮すると、それなりに自然な適性がある。

それは例えば、教えること、カウンセリング、工芸の保存、若者のスポンサーとしての励まし、司法や行政の役割、政治・社会の長期的な展望からの解説、歴史書などの遺産の保護、歴史的文化財の研究・報告・保護、次世代への遺産=天然資源の保存、である(94)。
③ 老人を受け入れるには、全社会としての効率という見地に立って、効率性の低い人々をも職場に組み込む必要である。人を強制的に職場に適合させるのではなく、職場を人間に適合させるべきなのだ(105〜106)。
④ 一生涯を通じて仕事を続ける場合の鍵が老人教育である(109)。

バトラーによれば、仕事・労働もお金も必要であるから、退職制度は廃止すべきだ。より包括的にいえば、教育と勤労と余暇をライフサイクル(若年期・中年期・老年期)の三区分に割り振ることをやめるべきだ(120)。
【私のコメント】
教育・勤労・余暇の再配置を通じた人生の再設計という考え方が繰り返し出てくるが、これはまさに『ライフシシフト』の先取りである。
5 医療の現実と老人研究
バトラーは精神科医として老人医療の現状を鋭く批判し、老人研究の必要性を訴える。

©︎Y.Maezawa
① バトラーによれば、老化現象の多くは予防し、進行を遅らせ、治療することが可能な「疾患」である(204)。
とくに可逆性の脳症候群の原因は、低栄養、貧血、うっ血性の循環不全、感染症、薬の副作用、頭痛障害、アルコール、脳血管性障害、脱水、手術への反応などだ。それらを素早く診断して治療しないと、慢性化し不可逆になる(206、262)。
② 医師や医療関係者は老人の価値を否定するエイジズムを共有している(208)。
そのため、老人患者を積極的に避け、毛嫌いし、パターナリスティックに振る舞うだけでなく、前向きな治療をせず、おざなりな世話に終始する。そこには個人的、職業的、官僚的、財政的な考慮や思惑が交錯している(208〜210)。
偏見や固定観念の影響を受けているのは精神科医も同じである。彼らは可逆性疾患に罹患しているにもかかわらず、老人の精神問題は治療できないと仮定しがちだ(6)。
ひとたび老人性痴呆のレッテルを貼られると施設に送られ、そこで死ぬことになる(7)。
精神科医は全体として老人の治療は無益だと感じている(267)。
©︎Y.Maezawa

医師はエイジズムを医学コースの研修中に学習する。そのコースには、老いぼれや愚痴っぽいといった軽蔑的な用語、年齢や動脈硬化、老衰などの理由で老人を治療不能として簡単に片付ける傾向、さらには器質性や不可逆性、限られた余命、第二の子供時代、子供のようだ等の悲観的な記述で溢れている(213)。
他方、老人患者を粗末に扱う病院側の戦略もある。向精神薬を用いて老人をボーっとさせることは、患者の気分を良くするためであるが、それ以上に施設の平和のためなのだ(230)。
③ 医療の現状を打破するには老人の実態に即した研究が不可欠である。
バトラーは四つの理由を挙げる(292〜293)。
・財政上の理由(老人が健康だと経済生産性が延長し、社会負担金の大幅な削減になる)
・人道上の理由(尊厳ある老後が望ましい)
・社会的な理由(ライフサイクルの一つの段階の研究が他の段階にも参考になる)
・哲学的な理由(老いることへの恐怖心を減らす)
④ 若々しく生き生きとした老人たちの共通点は、積極的な参加、自己決定、愛情や尊敬の分かち合いなどである。
また、高齢期の独自の経験とは、人生の諸段階の経験があり、死期に直面していること、突き詰めると自分自身の人生の意味に直面していることだ(260)。
人生上の危機に直面すると、老人でなくてもストレスを覚え、感情問題を起こすものだ。老人には悲哀感や、罪悪感、孤独感、憂鬱感、絶望、不安、無力、激怒がしばしば見られるが、それらを精神異常とみなすべきではない(261、479)。
バトラーは「老人呆け」に代わる言葉が必要だという(283)。
それが「高齢期情緒・精神障害(emotional and mental disorder)」である。

©︎Y.Maezawa
【私のコメント】
バトラーの描く老人医療の実態はとてもリアルである。
とくに精神医学はエイジズムの影響を受けるだけではなく、逆にそれを作り出してもいる。
ここには『恍惚の人』が依拠した精神医学モデルの実態が描かれている。
エイジズム(老い=無価値、老人=邪魔者とする老人差別文化)を克服するための鍵を握るのは老年医学、とくに脳神経科学である。
バトラーは「老化」と「疾患」と「うつ状態」を分けている。
「老人呆け=精神的・感情的障害」はそれらを混合したものだ。
後二者なら対処できるというが、ここで疑問が生じる。疾患でもなければ、精神的なうつ状態でもないとすれば、「老化」とは何か。それは長生=健康の別名ではないか。
認知症の症状を「中核症状」と「周辺症状」に分ける理論がある(小澤勲『痴呆を生きるということ』岩波新書、2003年)。
周辺症状は周囲の人々とのやり取りやその他の環境条件に左右されから改善できる。
とすれば、治癒しない中核症状が老化なのだろうか。それとも、老化は認知症とは関連しないのか。
他方、『ライフスパン』の著者シンクレアによれば、老化は疾患であり、治療や予防が可能だという。
しかし、そうなるとバトラーの見解と同様、老化そのものは消え、健康=長生だけが残ることにならないか。
私の考えでは、
老化とは、癌などの身体疾患や認知障害や精神的なうつ状態そのものではない。身体障害や認知障害や精神障害に「なりにくい/なりやすい」という傾向を想定するなら、その「なりにくさ/なりやすさ」を調整・制御する身体全体の働き合いが弛緩し弱まることである。
言い換えれば、身体全体の修復機能の脆弱化という傾向である。この傾向の生物的な基盤として幹細胞の増殖能の衰えが考えられる。老化には限界=寿命があるということだ。
以上のように老化を捉えると、若いうちは癌になりにくく、齢をとるとともに癌になりやすくなることも説明できる。
もちろん小児や若年で癌になる人もいるが、この場合は身体の全体ではなく、その一部に「なりやすさ」を抱えているからだろう。身体全体の修復機能の脆弱化という老化の傾向は、鍛え方次第ではその進行を遅らせることができる。老いても若々しい老人は日々努力している。筋肉は裏切らない。

©︎Y.Maezawa
6 介護施設
バトラーは老人ホームの実態を踏まえつつ、理想的な老人ホームについて語る。

① 米国の「ナーシングホーム」は、回復期の患者や全年齢とくに老人の長期ケアを目的とする介護=ケア施設のことである。
したがって病院ではなく、最低限の看護と医療を提供する居住スペースだ。
これには二種ある。
一つは商業ベースのホームであり、営利目的だ。
もう一つは宗教や慈善の任意団体か政府によって運営された非営利のホーム。
ただし、この入所には選択的条件がつくし、治療が必要な場合は別の病院・施設に移動しなくてはならない(301〜302)。
② ナーシングホームは社会と墓場の中間とみなされている(303)。
医学部の学生や、インターン、レジデントはナーシングホームの患者を卒中でダメな人と見ている(305)。
しかし、ナーシングホームに必要なのは、居住し治療を受ける場所として一定水準の人間らしさを確保することだ(313)。

③ 理想的な老人ケアを実現するのが「多目的センター」である(339〜343)。
このセンターの要件はこうなる。
・公的資金を商業ベースの老人ホームにではなく、非営利の公立ホームに回すこと。
・総合的で継続的なケアを同一の多機能施設で提供すること(医療的ケアを超えてトータルなケアを必要とする)。
・総合的な診断・治療のプログラミングを開発すること(可逆性障害と診断して不適切な施設に送り込むと言う悲劇的なミスを避ける)。
・在宅ケアの終身介護サービスとともに、コミュニティケアにも重点を置くこと。
・サービス・訓練・研究の三部門を設けること。
・全国パーソナル部隊を創設し、看護師・ホームヘルパー・ホームヘルスヘルパー・作業療法士を派遣すること。
・デイケアとショートステイを併設すること。
・家族が同居するために資金を提供すること。
・特別養護サービスや終身介護によって最高の質のケアを行うこと。
④ 老人施設では死の直前まで可能な限り最大限のリハビリを提供すべきである。なぜなら、人生最後のもっとも難しい歳月を価値あるものにするための希望と自尊心を育むのにふさわしい場所なのだから(344)。
【私のコメント】
バトラーによれば、米国では1935年以前、今日でいうナーシングホームはほぼなかった。
救急農場、養護室、労役所、宗教・慈善団体の老人ホームはあったが、葬られる場所とみなされていた。
ちなみに、映画「ベンジャミン・バトンの数奇な一生」では、主人公のベンジャミンは老人ホームの階段に捨てられた。そのホームでは黒人夫婦が世話をしていたが、運営主体は宗教団体か慈善団体のようだった。
1935年、タウンゼント運動やその他の動きを受け、社会保障法が成立して老人に直接現金が支給された。
そのお金を目当てに、個人住宅を改造した夫婦経営のナーシングホームが乱立した。大恐慌の下で個人の努力ではどうにもならない貧困状況が背後にある。
戦後の1965年、老人用メディケアと低所得者用メディケイドの制度ができた。
そのお金を求めて商業ベースのナーシングホーム産業が繁盛した。

5年ほど前、ドイツの福祉団体運営の老人ホーム二か所を見学したことがある。ドイツには六大社会福祉団体がある。連邦政府や各州の自治体の福祉政策を左右する力を持っている。そのうち五つは宗教系であるが、その中でもカトリックとプロテスタントの組織が抜きん出ている。非常に充実しているが、介護スタッフの質や移民の問題を抱えている。
また3年前には英国を訪れ、二つの慈善団体の老人ホームを見学した。こちらも充実していたが、近年では民間ベースの老人ホームが席巻し、70%を超えるそうだ。
7 政治への参加
「老人問題」を解決するためには老人の積極的な政治活動が必要だ、とバトラーは言う。

① 1960〜70年代の公民権運動、反戦運動、女性解放運動は老人の政治的自覚を生んだ。老人が選択可能で効果的な政治活動とは何か(373)。
バトラーは、地域社会の活動から監視活動や告発までを包含する「積極的行動主義」を提唱する(394)。
② 適切で尊厳のある老後のための政治の重点項目は次の三つだ。
老人のニーズへの文化的感性を肯定的なものに変えること、
その方向に国家の資金を手当てすること、
そして最後は老人を効果的に政治に代表させることである(409)。
③ バトラーは老人対策の主要緊急目標として以下の14項目を挙げる(421)。
・優先事項の再調整(ハイリスクグループの人間としてのニーズを満たすため)
・高齢局の創設:老人対策の統一司令塔
・老人の低栄養と貧困の根絶
・住宅の選択肢の提供
・就労の権利
・社会的役割への権利(各種プログラムへの参加)
・生涯学習およびライサイクル教育
・移動の自由のために交通機関の利用
・犯罪からの防護
・包括的なサービスの供給(非商業ベースの公共事業の一環)
・適切なヘルスケア、ソーシャルケアの樹立(医療制度の構造改革)
・非営利老人ホームに社会公共事業の補助金を回すこと
・精神衛生医療を受ける権利(国立精神衛生研究所の設立)
・基礎と応用の研究
【私のコメント】
ここに打ち出されている見地は1970年代のリベラルな政治思想である。
エイジズム批判に基づく政治運動とフェミニズム運動を置き換えてもおかしくないが、問題はまさにそこにある。
8 公共政策と死ぬ権利
高齢社会のための公共政策や死の意味づけには世代の責任という観点が要請される。
① 寿命は延びたが質が伴っていない。たんに生き長らえるだけでなく、社会の重要な一部として元気で仕事に従事し、貢献し、尊厳ある生活を送るためにはどうすればいいのか(410)。
② 高齢社会のための公共政策の柱は五つある(412〜413)。
・医学や科学技術が社会に与える影響の研究(科学研究費の一部を社会科学や人文学に割り当てること)。
・老化プロセスの包括的で学際的な研究。
・教育・勤労・余暇を人生全体に再配分すること。
・高齢・余暇に対応できる人間教育(一人暮らし、家族の枠を超えた人間的連帯、充実した楽しい生活、想像力の自由な駆使)。
・未来世代へのコミットメント(数世代先の世界はどうなるかと考え、そのため準備すること)。

③ 若々しい老人も増えたが、同時に重病や障害の老人も増えた。老化の研究の目標は、健康で活力に満ちて自己生産的な老齢期の実現であり、死ぬ直前の障害の時期の短縮である。そのことによって介護する中年の負担は軽減される(411)。
高齢者や老人という言葉は衰退を連想させる。バトラーが新たに提案するのは「長生者(long-term people)」だ(427、479〜480)。
④ 「死ぬ権利」に関してバトラーはこう言う。消極的安楽死(延命措置の停止)が厳格な管理下で考慮され始めているが、医師の使命はあくまで延命の尽力にある。したがって死に関する決定は他の人々と共有すべきであり(430〜431)、具体的には委員会方式が望ましい(432〜433)。
また、法律は注意深く記述され、厳格に適用され、絶えず検討されなければならない(433)。
他方でこうも言う。死期が迫ったとき最も重要なことは、死を身近な人々と分かち合うことである。たった一人で死んでいく恐怖は不必要で残酷だ。生きている人たちは死んでいく人たちを慰めることで人生について多くを学ぶことができる。ここでバトラーはシシリー・サンダースの仕事に言及している(435〜436)。
バトラーによれば、死の意味づけには四側面がある(436)。
すなわち、
ニヒリズム(私も世界も消える)、
皮肉な無関心(未来を心配しても仕方ない、未来も我々を心配しない)、
足跡を残す努力(後世に自分を知らしめる)、
そして文化・貴重なものを後世に新しい形態で残す営みだ。
後二者には個人的関心だけでなく社会的関心を含まれる(437)。

【私のコメント】
公共政策ではELSI(倫理的・法的・社会的アプローチ)のアイデアも出されている。死に関するバトラーの論述は全体として手薄の感がある。それは老いの深まりのステージが考慮されていないからではないか。その中でバトラーが指摘する死の意味づけの四側面は、世代責任の観点から重要である。
ただし、「ニヒリズム」と「皮肉な無関心」は同じカテゴリーに属すると考えたい。

したがって四側面を再構成するなら、
⑴自分の消滅・世界の終わり、
⑵親しい人々との再会、
⑶自分の存在の記録、
⑷文化・価値観の継承
になるだろう。
世代責任を重視するのは⑷である。
9 人生の再発見
エイジズムには、社会的慣行や制度に関わる外なるエイジズムと、老人の生き方に関わる内なるエイジズムがある。
後者を克服するためには老人自身が変わらなければならない。

①目標とすべきは人が人生の最期のときまで成長できるような社会の構築である(440)。
そのためには、教育・就労・退職の区分を人生の三つの時期に割り振る習慣から自分自身を解放しなければならない(442)。
新たなライフサイクル教育では人生の特定の段階においてどのような出来事が生じ、心理的・個人的・家族的・職業的な課題が生じるかを学ぶ(445)。
②生きる権利を保障するのはお金(財政的基盤)だ。社会保障制度の改正はライフサイクルに応じた柔軟性が必要である。その際、最低所得という安定条件が重要だ(446)。
ボーヴォワールやフリーダンらのフェミニズム運動は、いまだに未亡人の貧困問題に取り組んでいない(449)。
③親密な関係におけるトラブルの解決策の一つは「不完全さ」を受け入れることだ(450)。
あらゆる親密な関係はやがて失われる。これを受け入れる準備が必要になる。人間のパラドックスとは、対立・分断するくせに強い絆を望むことである(450)。
高齢期における性的欲望のコントロールは家庭生活と社会の基礎であるが、成長・興奮・新しいレベルの親密さを促す心の余裕があってこそ、コントロールも可能になる(453〜454)。
④型にはまったアイデンティティは固定した対処の仕方をもたらす(457)。
そこから生じるのは二重人格、偽りの生活、静かな絶望、単なる蒸発・失踪だ。それらを未然に防ぐにはアイデンティティの固定化に抵抗することが必要だ(458)。
エリクソンの理論は受身的で服従的で過去のレッテルで固めたものだ(459)。人間は変化とともに生きていく必要がある。一生を通して何回も自分を発見し、再発見するべきだ(460)。

【私のコメント】
バトラーは老人が「変わること」を強調する。
しかし問題は、固定した見方をたんに変えることではなく、どこへ向けて変わるかだ。
あるいは、特定の時代状況では「変わらない」「あえて変えない」という姿勢もありうる。
例えば、ポーランドのアンジェイ・ワイダ監督の遺作に『残像』がある。主人公はシャガールらとともに現代芸術運動を牽引したな画家、ストゥシェミンスキー教授である。彼は戦後の共産主義体制下で自分の芸術の信念を曲げず、圧迫を受けながらも絵を描き続け、最後は孤独のうちに惨めな死に方をした。しかし、彼を慕う弟子たちの心に教授の愚直なまでの生き様が強く刻まれ、後年、ウィチ美術大学に彼の名前が冠されることになった。彼の場合は生き方を変えていない。

10 老人の世界観の可能性

老人が世界をどのように見ているかを知ることから老人の新しい可能性は生まれる。
① 老後の生活は一般には衰退、無価値、不条理と思われている。そのため老人は受動的であれと強制される(462)。
老人の価値を否定する考え方、すなわちエイジズムは、古代からの遺産や、アメリカ文化、産業文明、自分の老い=死への悲嘆、老化=懲罰(シワ・シミ)、老いの醜さ・いやらしさ(美学的反応)といった、多くの力の作用の結果である(462〜463)。

②エイジズムを変えるには、魅力的でないものを魅力的にすると同時に、不快なものを受け入れる感覚・人情を培うことが必要だ(464)。
子どもも若者も中年も、老人と接触する中で人生の手本を学べる(464)。

③ 多様性の内に老齢期特有の世界観を認めることができる(469)。
・時間感覚の変化:
老後は将来のない唯一の時期であり、残っている現在の時間の量より質が重視される。
・ライフサイクルの感覚:
これには六つの要素がある。
⑴死の自覚
⑵世代間の歴史的つながり、
⑶人間的な時間の体験
⑷人生経験の感覚
⑸各段階の知識
⑹サイクルや段階についての考え
・人生回顧への傾向:回想録、映画・小説、人生反省の作品ている。
・償いと決意、あるいは後悔の念。
・慣れ親しんでいるものへの愛着。
・伝承のための保守主義、つまり長老的機能。
・遺産を残したいという欲望。
・権力の委譲。
・人生を全うしたという感覚:人生満足感は必ずしも「成功とは限らない。
・成長する能力:独創性や変化する能力。
④ 老人の世界観は、人生の危機に生じる感情的反応(例えば、悲嘆、罪悪感、孤独感、意気消沈、不安、激怒、無力感)から区別すべきだ(261、479)。
人生の最後の最後まで人間の可能性は存在する。ライフサイクルが提供することを全て味わい尽くすために闘うべきだ(483)。

⑤ アメリカの老人の悲劇は老後の不条理をほぼ不可避なものにしたが、それで人生を芸術作品にする可能性は失われていない(483〜484)。
【私のコメント】
老人の世界観の内容について、またそれに関連してとくにエリクソンのライフサイクル論やアイデンティティ論については、次回、ボーヴォワールの『老い』をとりあげ、老人の内的経験の世界を問い深める中で検討して見たい。


11 「エイジズム」を相対化する
本書の根本的な立脚点は「老人差別(エイジズム)」という捉え方である。
そこには絶対正義の視線とともに、生産重視の価値づけが組み込まれている。エイジズムの捉え方を相対化するためには、「世代責任の自覚を組み込んだコミュニケーション」という視点が必要だと考える。
「老い=無価値」「老人=邪魔者」とみなす老人差別=エイジズムは、社会の制度・慣習の隅々まで浸透しているだけでなく、一人ひとりの心の中にも浸透している。したがってエイジズムには、社会的慣行や制度に関わる外なるエイジズムと、老人の生き方に関わる内なるエイジズムの二側面がある。
⑴ 「政治的に正しいこと」を相対化する
バトラーは、外なるエイジズムに対して、現実を変革する政治課題を網羅的に列挙した上で、実践的な解決案として国民年金制度、老人同士の協同組合、国民医療保険制度、老人の総合的研究、多目的センター、教育・就労・退職の組み替え、ライフサイクル教育等を提示する。それらは現時点においても目指すべき方向であり、誠に慧眼というべきだ。
しかし、制度の全面的な改革を提案するバトラーの視線は、平等を重視するリベラルの政治思想に立脚している。それは人種差別、民族差別、障害者差別、女性差別、患者差別(パターナリズム批判)等に通底する政治的立場であるが、そこにはパラドックスがある。すなわち、多様性と寛容を唱えながらも、自己の立場の絶対的正義を疑わないことだ。ここで主張される「政治的な正しさ」からは対立の図式が生じる。老人は誰に対立するのか。
差別は社会集団によって不可避的に生み出される。社会集団の存続に役立つか否かという必要性の機能が線引きの基準になる(森下直貴・佐野誠編著『新版「生きるに値しない命」とは誰のことか』中央公論新社、2020年)。それでは、例えば女性差別や障害者差別と比較した場合、老人差別の特徴はどこにあるのか。
女性差別の場合、女性に対立するのは権力によって支配する男性である。女性は社会集団にとって再生産のために必要である。再生産を支配してきたのが男性である。それが人類の歴史である。女性は表向き丁重に扱われるが、その裏には支配の意志が見え隠れている。
障害者差別の場合、障害者は社会集団から必要とされていないし、権力も持たない。端的に弱者なのだ。しかし、現代における国際政治の常識(リベラル思想)では、障害者=弱者は絶対正義によって守られている。とはいえ、人々のホンネの部分では自分は障害者になりたくないと考えている。「政治的な正しさ」というタテマエは必然的にホンネとのあいだの分裂を生み出す。
老人差別の場合、老人男性は権力を握ったまま容易には手放さない。そのため男性同士の世代間闘争が起こる。権力を奪取された老人男性はたんに不必要なだけでなく、危険な邪魔者でもある。そこから老人男性に対する理想化と侮蔑化が生じる。このような偏見の二面性は旧権力者=邪魔者に対する両義的な対応を反映している。
バトラーは「老人を犠牲にしてはならない」という。この指摘は正しいと同時に間違っている。バトラーの真意が、マイナスからゼロレベルへの回復、つまり悲劇からふつうの生活への引き上げであるなら、その指摘は正しい。しかし、そこに老人以外のグループの排除がともなう限り間違っている。財政的余裕のない環境であっても、どの年齢層や世代であれ、基本的に犠牲にされてはならない。エイジズムという絶対正義の視線を相対化し、全世代が共存する方向を探るべきなのだ。
⑵ 「生産的であること」を相対化する
バトラーは、内なるエイジズムに対して、老人自身が変わることが必要だと考え、長生きすることの意味の問い直し、固定したアイデンティティの解きほぐし、老人特有の世界観の受け止め、人生を芸術作品にする可能性、次世代に文化を継承する責務を提案する。いずれも説得力がある。
問題は老人が変わる方向である。バトラーの視線は社会集団に役立ち、貢献する方向に向けられている。彼は後年、生産的な老いの見地を「プロダクティブ・エイジング」と名付けた。老人の役割は後進の育成であり、老いの価値は人生経験の豊富さにあり、そして長生きする目的は次世代への文化伝授である。
バトラーは老人一人ひとりの個性や、老人世代の多様性を強調している。また、社会全体の効率性という重要な指摘もある。ところが、その多様性や人間的な効率性もまた生産性の観点から見られているといえる。なぜならバトラーにとって老化そのものは存在せず、長生=健康の別名にすぎないと解釈できるからだ。とすれば、エイジズムは生産的な老人から生産的に活動できない老人へと平行移動したことになる。
世の中には生産的に活動できる老人ばかりいない。程度の差はあれ、生産的に活動できない老人も多くいる。彼らの居場所や役割はないのか。
それを老いの中に位置づけるためには、老いの深まりに応じで三つのステージを設定しなければならない。元気で活動できるステージ、支障が生じて世話を受けるステージ、死に直面したステージの三つだ。ステージの違いはたんなる多様性には解消できない。
老いのステージの全体を見渡すとき、生産的である/生産的でない、役に立つ/役にたたない、できる/できないといった区別が維持できないことが見えてくる。それに代わって登場するのが相互的コミュニケーションの視点だ。ここでコミュニケーションとは意味の解釈のやりとりのことだ。このやりとりは双方のうちの一方の側が黙っていても、あるいは極端な場合に不在であったとしても、他方の側が意味を解釈しながらやりとりを続ける限り、コミュニケーションは成り立つ。
生産に活動できない老人にも一定の役割はある。自分の老いの姿を見てもらい、それを通じて若い人に人生を学んでもらうという役割だ。これが世代責任の自覚を組み込んだコミュニケーションである。「できる/できない」「する/しない」「する/ある」という区別、あるいは「生産的である/生産的でない」という区別は、世代責任の自覚を組み込んだコミュニケーションというプラットフォームの上に位置付けられて意義を持つことになる。
⑶ 老いの最期のステージを生きる
人々は老いの深まりの中で、寝たきり状態や重度の認知症 になることを恐れている。何もできない自分への苛立ち、惨め・不幸という感情、家族の負担、社会的評価・落伍感、迷惑・重荷、こうありたいと思い描く「自己」の理想との落差、等々。そこまでして生き延びたくない、だからそうなる前か、そうなった時点で死にたいと願う人もいる。
ここで生じる問題は、意思表示ができる時点での考えと意思表示ができない時点での思いのうち、どちらを優先するかである。通常はそこに対立が想定される。事前には惨めだから死にたいと考えていても、重度の場合は本能のままに生きることになる。そうなると事前の意思と事後の思いとは一致しない。別の問題もある。死にたいと願って実際に死ぬ時点がいつなのかは漠然としている。また、惨めさの主観的な基準も曖昧である。時期は見境なく遡り、適用の範囲はどこまでも広がっていく可能性がある。一定の条件、私見では「死期の切迫」条件が不可欠である。もちろんこれ自体も幅があるが、常識的には食べられなくなった時点、したがって死の2週間ぐらい前あたりになろう。
事前と事後のあいだにギャップがない場合がある。死期が迫ったとき、延命治療をせずに自然死するが、それまではどんな状態になろうと、しっかりとしぶとく生き続けるという場合だ。ここでは事前の意思と現時点の思いは変わらない。この一貫性を支えるのが、世代責任の自覚である。自分の姿、老い方、死に様を若い人に見てもらう。その姿から人生について学んでもらう。人は生まれ、老いて死ぬものだという真実。それは生き方・老い方・死に方の文化を次世代に伝授するという責任意識に基づいている。
誰もがいつかは老いて死んでいく。寝たきりや認知症になる場合もある。しかし、そうなったらそうなったで、仕方ないではないか。それも人生の最期の姿だ。自分で決めるか、他者から決められるかが重要なのではない。自分で決める際に、自分だけの問題として考えるか、世代の継承の問題として考えるかの違いが重要なのだ。世代への責任として自分で決めることだ。世代責任という観点の核心は「人生を学ぶこと」にある。若い人に人生の最期の姿を見せる。文化・価値を伝える。最後の迎え方について考えてもらう。残念ながら、安楽死の場合は死後にまで続くコミュニケーションが断ち切られる。自分だけの問題として死を捉えているからだ。
生まれたときも死ぬとき一人であるとか、偶然たまたまこの生を受けた、好んで自分から生まれたわけではないと考える人がいる。しかし、それは少し違うと思う。生まれたときは出迎えられるし、死ぬときも看取られる。待ち望んでくれる人や、残念がってくれる人がいる。たしかに孤独の中で死ぬ人もいるのが現実であり、それでいいと考える人もいる。しかし、私はできれば人々に囲まれて感謝し感謝されながら最期を迎えたいと思う。最期の最後まで世代責任を織り込んだコミュニケーションだ。だからこそ前もってそういう関係を作っておく必要がある(以上の見地は前掲拙著で示している)。

(編集:前澤 祐貴子)