交流の広場

老化に関する訳本を
出版する過程で学んだこと
筒井祥博
1. 出版の過程で学んだこと
訳本への発端
2021年 老成学研究所のホームページに「高齢期を生きるということ」というエッセイを書かせて頂いた。編集者が内容を見て “ポジティブな老い方” というサブタイトルを付けてくれた。
翌年の2022年5月に 購読していた英字新聞NYTに、「老化の常識をくつがえす:いかに長く健康で生きられるかはあなたの信念がきめる」(Breaking the age code) という本の書評が出た。この本は 高齢期をポジティブに考えることが自分自身の老後にもよい とされ、私が考えていたことと似ている と感じた。
常葉大学で配下であった大星有美氏に話したところ 翻訳してみたい と言った。大星氏は 東京外国語大学スペイン語を出てから 作業療法師になり、浜松医大で 脳科学の領域で学位をとり ポスドクとして研究していた。
早速 この本を書いたイエール大学の心理学と疫学の教授である ベッカ・レヴィに メールを送った。
半年前に 苦労して日本情報学研究所のresearchmapマイポータルを更新しておいてよかった。大星氏と私の業績は このresearchmapの英語版のURLを送るだけで済んだ。
2日ほどして ベッカ・レヴィ教授から OKのメールをもらった。日本から私たちが レヴィ教授にコンタクトしたのが一番早かったのだろう。
知人に依頼して 出版社を何社か当たってもらったが、引き受けてくれる出版社はなかった。近年 出版業界は不況で 確実に売れると思われるものしか出版しない と言われた。
訳本の出版社が決まるまで
著者は ハーバード大学の大学院生であった時に、世界で一番の長寿国である日本へ その理由を知るために 奨学金を得て一学期間やって来た。
日本では 「敬老の日」などを設けて 高齢者を敬う文化があることを知り、長寿とその国の文化的な要因が関係するのではないか と考え、ハーバード大学へ帰ってから その観点から研究を始めた と。
序章の見だしは 「アメリカと日本の間で思いついたこと」を書き、本文のなかでも 日本の長寿者のことに詳細に触れている。日本へ来たことが 研究のきっかけになり、今では この領域で国際的に評価されている研究者の本を 日本で出版できない と断ることは忍びなかった。
その時 ふと 日本の老化の学会に依頼したらどうだろう と思いついた。日本老年学会の重鎮と思える先生に 顔見知りではなかったが、懇願する手紙をメールで送った。正月の休日の期間であったが 丁寧に対応していただき、大手出版社「講談社」のベテランの編集者を紹介して下さった。
私たちは この本の概要、アピールする点を 紹介者を通じて送ってあったが、すぐに出版が決まった訳ではない。
この本について 様々のことを説明させられた。編集部の上にある業務部会で出版が最終的に決定されるまで 申請してから3カ月がかかった。本を出版してもらうためには 編集部の有力者に個人的にコンタクトできること、その人と自ら交渉できること が決定的に必要であることが分かった。
本の翻訳の過程
出版社が決まり 10カ月近く頭の上にあった重石から開放されて ほっとした。 しかし 出版社が決まった時点で 直訳の翻訳は 本全体の半分しか進んでいなかった。
翻訳は 大星氏が 本のKindle版(電子書籍)から一文ずつワードへ移し、英文の下に日本語の訳文を書き、特に訳の難しい部分をマークして私にメールで送ってもらった。
私は 英文と訳文を見比べて 内容が正確に訳されているかどうかチェックし、大星氏が疑問とした部分を中心に 私の意見を書いて送り返した。
次の段階として 大星氏から英文を除いた日本語文だけを送ってもらい、日本語の文章として分かりやすく読めるかどうかをチェックし、部分ごとに 私の意見を添えた。
私は 主として 意味が正しいか、文章として不自然でないか をみて、文体などは 大星氏に任せた。
編集担当者から学んだこと
編集部としては出版が決まっている以上なるべく高い水準の本を作らなければならないという配慮があったのだろう、英文を除いて日本語の訳文だけにしたものを1章ごとに送ればベテランの編集担当者に修正してもらえることになった。担当者に大変で申し分けないと言ったところ、「我々はプロだから、修正することは慣れている」と言われて感心した。
まず指摘されたことは ”文章がこなれていない”、”滑らかさがない” と言われた。
私は 文章の流れは大星氏に任せていた…そうしないと前に進まない。翻訳には 英語力だけでなく、人名、アメリカのメデイアなどで使われている特殊な言葉の日本語訳なども ネットを駆使して 適切に訳す力が必要であったが、大星氏は よく頑張った。翻訳を通じて 英語だけでなく 一般常識や日本語の文章力が試されていることが分かった。英語は ひとつの文章で肝心なことを先に書いて、関連したことを関係代名詞や接続詞でつないでいくことが多いが、訳文では 頭でっかちになる傾向があった。
担当者は 一章ごとに送られた文を 驚くほどの早さで修正してくれたが、文章の終わり方、接続、などを直すことが主体なので、文章全体の構築は ほぼそのままであった。
編集担当者に言わせると 文章が直訳的で 頭でっかちになりがちであるが、読めないことはない ということで 骨格はこのままにして進めていくことになった。
大星氏は よく頑張って 本の後半を4カ月で終わらせた。全部の原稿を提出して 出版社が図版にして 四六版で380ページになることが分かった。
英語の原著では最後にNOTESとして参考資料50頁が添付されていた。これを入れると頁がかさみどうするかが問題であったが、編集担担当者が最後にこれらの資料を出版社のホームページに移し、スマートフォンのQR コードで見られるようにしてくれた。これは新しい試みだと思う。
編集担当者は 何回も推敲し 頑張ってくれ その度に新たな質問をされた。
質問に答えながら 送り返されるファイルをチェックした。
編集担当者が 半年前に出た ハーバード大学の幸福に関する80年に渡る縦断研究の責任者らの出した「グッドライフ:幸せになるのに、遅すぎることはない」の訳本が 5万部以上売り上げた と知らせてきた。担当者は 同じ生き方に関する本なので「グッドライフ」を目指して頑張ろう と言われたが 結果的には到底及ばなかった と思う。
最後に この本のタイトル「Breaking the age code」を いかに日本語のタイトルにするか が問題であった。
「年齢に関する固定観念を打ち破る」という意味であるが、私たちは 幾つかの候補を挙げたが、最終的には どのようなタイトルが一般受けするかは 経験のある編集担当者に任せ 「老化のプログラムを書き換える」になった。
「“プログラム”と言うと コンピューター用語だ」 と後から 高校の同級生で半導体の研究をしてきた人に言われ、必ずしも 適切なタイトルであったかどうか 分からない。

2.訳本の内容で 印象に残ったこと
疫学的結果を 生物学で説明できる とは限らない
この本の著者は 高齢期あるいは高齢者について ポジティブに考える人はネガティブに考える人より 老後を健康で幸せに過ごし 寿命も長いことを 疫学的な結果から示した。
最も注目された結果は オハイオ州オックスフォードで 30年以上にわたり縦断的に続けられた「加齢と退職に関するオハイオ縦断研究」の中に 「年をとるにつれて 役に立たなくなるという考えに 賛成ですか、反対ですか?」という質問を著者らが見つけ、ポジティブとネガティブのグループに分け、他の質問結果と比較した。さらに、これらのグループの人を 「国民死亡指標」と比較して 寿命を調べた。この結果から ポジティブな年齢観を持っている人は 老後が健康で、ネガティブな年齢観の人より 平均寿命が7.5歳長いこと を明らかにした。
この解析は 20世紀後半のアメリカのおける最も信頼できる調査の上で行われたために 真実性が高かった。この結果が発表されると その領域の専門家、老化に関心をもつ一般人、新聞、テレビ、ラジオなどのメディアで注目された。
これは 疫学的な事実であり、その理由を説明できるかどうか はその次の問題である。
遺伝子が運命ではない
著者の祖父はアルツハイマー病で亡くなったため、この病気にとりわけ関心があった。アルツハイマー病発症の関連遺伝子APOEε4をもっている人の中で、この病気の発症に関して全国調査をした。ポジティブな年齢観の人はネガティブな年齢観の人と比較して、発症率が約半分であることが明らかになった。同じ遺伝子状態であっても病気が発症するかどうかは文化的要因である年齢観が大きく影響する。著者は「私たちは生物学的生きものだが、生物学をはるかに越えた存在である」と述べている。
以上、著者らは ポジティブな年齢観の人が 老後の健康がよく 寿命が長い、また アルツハイマー病関連遺伝子を持っていても発症しにくいこと を明らかにした。
しかし 現時点では なぜそうなのか…生物学的説明は困難である。高齢期をポジティブに考える信念 あるいは 心構えが 病気の発症や寿命に いかに働くかは興味ある課題である。
心の在り方が 精神や身体の機能に いかに作用するか は 新たな学問領域である という研究者もいる。
重篤な患者で 孫が生まれるまで生きていたい と強く望む人は、本当にその時まで生きることがある。生きがいが 病気の発症や死に影響を与える としたら、どのようなメカニズムが働くか。心の在り方が身体や精神にいかに影響するか が問題である。著者は 「神経細胞や遺伝子が 必ずしも その人の幸福感や運命(寿命)を決定しない」 と言う。
発達し続ける精神
翻訳するに当たって 私が この本に興味を感じたことは、高齢化することによって高まっていく機能はあるか、あるとすれば何故か という問題である。
著者は 老化について 記憶、知性、経験の蓄積、創造性などの側面から 文化、文学、絵画、音楽、スポーツなどの広範な領域にわたって 多くの側面をあげ、ポジティブな年齢観を持つことよって それらが高まること を示している。
特に 高齢者の精神機能、心理学的特徴をあげ、高齢にならないと身につかない知性があること を指摘している。
高齢者は 蓄積された経験、広い視野、人生を振り返る内省、人生の葛藤を克服する能力、他者に対する見返りのない愛などの特徴を有する と その領域の尊敬する人物との対話を通じて述べている。
しかし 高齢化した脳が 神経科学的にいかに変化するかについては 漠然と簡単に触れるに留まっている。
例えば 高齢化によって 脳のネットワークは減少するが、特定のネットワークの再生と柔軟性(可塑性)によって より効率性が高まる と述べているが、具体的ではない。著者の専門領域は 老年心理学と疫学であり、本書の目的は 高齢者の脳の脳神経科学的特徴を 科学的に示すことではない。
エイジズムが絡みつく
国立加齢研究所を創設したロバート・バトラーが “エイジズム”と名付けた年齢差別主義が 特にアメリカでは 構造的に固定観念化している。エイジズムは社会的レベルで タコの触手のように絡みついて 致命的に作用している と著者は言う。
多くの本では 高齢者の健康について 良い栄養を摂り、ストレスを減らし、適度な運動をすること に着目している。
川の岸に立つ人が 溺れている人を見つけ、飛び込んで助け、肺蘇生をするうちに、また他の人が溺れているのを見つけ、助けようとする、そして また溺れている人を見つける。
下流の問題に対処することも必要だが、さらに上流の問題を見る必要がある。何が 人々を川へ突き落としているのか その原因を見る。
高齢者の健康を考える時 ネガティブ年齢観は 上流の問題として 大きく影響している。
老人の不幸の根底には エイジズムがあり、それは ネガティブ年齢観に根差している、と著者は言う。
日本では 現時点ではエイジズムがそれほど問題になっていないので、違和感を感じる人が多いと考えるが、将来は分からない。
この本は エイジズムについて大系的に書かれている。
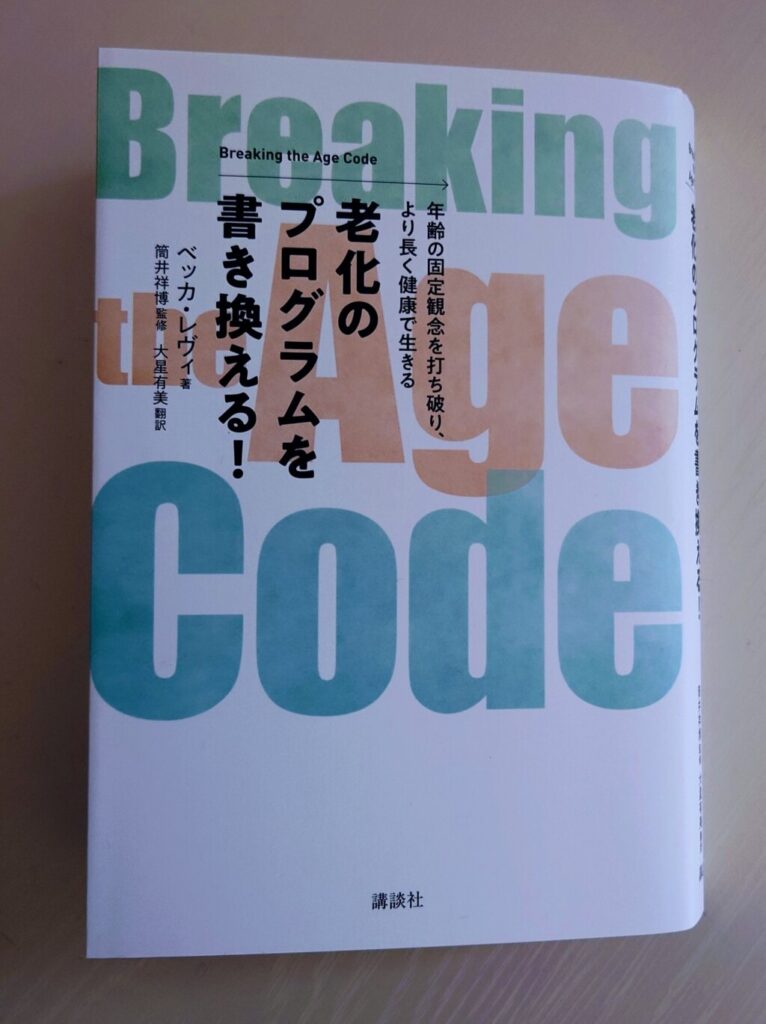
3.訳本を終えて
筒井は 翻訳のプロセスの進行の最中に 家の中で転倒、胸椎を圧迫骨折した。整形外科でコルセットを作ってもらい、骨粗鬆症の薬を飲みながら、パソコンの前に坐り続け 訳本のためのファイルのチェックと問題点の検討を行った。出版社のスケジュールは定まっているので、止めるわけにはいかなかった。その結果、脊椎が前弯し、身長は6センチ低くなった。
大星は 新設の私学の講師から この本の出版2年後に 名古屋市立大学医学部保健学科の教授に就任した。講談社のベテラン編集者からの暑中見舞いのメールには「華麗なる転身だ」と書かれ 驚かれた。
私たちは 個人的に翻訳したい本を英字新聞で見つけ、著者にメールを送り、翻訳許可を取り、出版社を探し 訳本を出版することができた。私たちの経験が これから興味ある本を翻訳したい と考える人にとって 参考になれば幸いである。
* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せください。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。