活動の実績
老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学事始 > 【老成学事始】IV 21世紀の「老人」哲学 森下直貴

©︎Y.Maezawa
21世紀の「老人」哲学
——世代をつなぐ責任と三つの役割
老成学研究所 代表 森下直貴

©︎Y.Maezawa
老いという時間
人は誰もが死ぬ。釈迦も孔子もソクラテスもカント死んだ。本書を書いている私、そして読んでいるあなたも、いずれ死ぬときが来る。しかし、「死ぬ」とはどういうことか。また死んだ後はどうなるのか。
「人が死ぬ」という場合、そこには多様な側面が含まれている。例えば、生物としての死、自己の死、関係の中の死、制度の中の死などだ(拙著『死の選択』)。また、死んだ後についても漠然とではあるが、無になるとか、あの世に行くとか、再生するといった答えが用意されている。それでは、死ぬ前についてはどうか。
伝統社会では死の手前にはたいてい「傷病」、すなわち広義の「病」があった。この点は乳幼児にのみ限ったことではない。若者や中高年の大人でも同様だった。そのため一般に環境の影響や他者の暴力による死が日常化した社会では、人生はせいぜい「50年」とみなされた*。それに対して、比較的に安定し安全が保障された社会では、死の手前にあるのはほとんどが「老い」である。そこでは病もその多くは老いとともに生じる。人は老いにつれて病み、そして死ぬ。
*日本の古代から中世までの時代、人々の平均寿命はだいたい40歳であった。そして40歳に老いが始まり、60歳で本格的な老年期に入るとされた(本村ほか編著『老い』)。
20世紀の後半、延命治療が目覚ましく進展した結果、人々の視線は「老い」そのものよりも慢性的な「病の中の死」に注がれた。視線がようやく「老い」に向けら始めたのは、長寿化の影響が顕著に現れた21世紀の初めからである。長寿社会では人はなかなか死なない。死にたくても死ねない。死の手前には「老い」という長くて緩慢な時間が広がる*。
*人の死に方には「病の中の死」のほかに「環境の中の死」や「暴力の中の死」があるが、長寿社会ではあらゆる死に方の中心に「老いの中の死」がある。

©︎Y.Maezawa
人生100年
死が避けられないのと同様、死の手前にある「老い」もまた避けられない。これが人類のこれまでの常識だった。ところが最近、老いは治療によって予防できる疾患だという説が出てきた(シンクレア他『ライフスパン』)。それによれば、エピゲノムを含めたゲノム全体の情報の乱れを防ぐなら、現在の10年程度の健康寿命を2倍以上に延ばすことができる。さらにリプログラミング治療をすれば理論上、寿命に限界はなくなるそうだ*。とはいえ、老年医学の研究者の大半がターゲットにしているは不老不死ではなく、健康寿命の延長のほうである。
*生き物にはなぜ寿命があるのか。細胞(生命体)は栄養状態が良ければ分裂して増殖する。つまり自分の分身を増やし、そうすることで自分自身の存在を存続させようとする。なぜか。生存にとっては過酷な環境の中で、生命体同士が食うか食われるかの競争をしているからだ。ゲノムを介して自己保存と自己分出のバランスをとるのが生命体の生存戦略であり、これを人類も引き継いでいる。
日本社会では2020年現在、65歳以上の人口が約3700万人に達する。この数は全人口の約29%に当たる。他方、0歳児は全国で約84万人になる。団塊世代のうち最多人数の学年が約260万人だったから、驚くほどの減少ぶりだ。人口推計によれば、超高齢化は2060年まで続くし、人口減少化の傾向は止まるところを知らないようだ。つまり、日本は世界の先頭を走る超高齢かつ人口減少社会ということになる(総務省統計局資料、国立社会保障・人口問題研究所資料)。
特筆すべきは百寿者が8万人を超えることである。平均寿命に関して男性は82歳、女性は89歳という数字が出されているが、私の実感は少し違う*。新聞の死亡欄を眺めると90歳代が半数近くを占めているし、シルバータウン化した近所を見渡しても90歳前後の老人があちこちにいる。だから、老年医学が唱えるように「人生100年」も決して誇張とは思えない。
人生100年になると、人生後半は50年に及ぶ。65歳定年後でも35年の長期である。老いという長くて緩慢な時間をどのように過ごせばいいのか。しかし、思案の行く手に障壁が立ちはだかる。「老い」をめぐる否定的な常識のことだ。
*平均寿命の計算にはピリオド法とコホート法の二つがある(グラッドン他『ライフシフト』)。ピリオド平均寿命は現時点での各年齢の死亡率を掛け合わせて算出する。他方、コホート平均寿命は各年齢の将来の死亡率を推計して算出するため、実態を反映する可能性が高いが、将来にならないと確定値を得られない。そこで一般に前者のピリオド法が採用されている。だから生命表の平均余命と実態がずれることになる。
人生50年
©︎Y.Maezawa
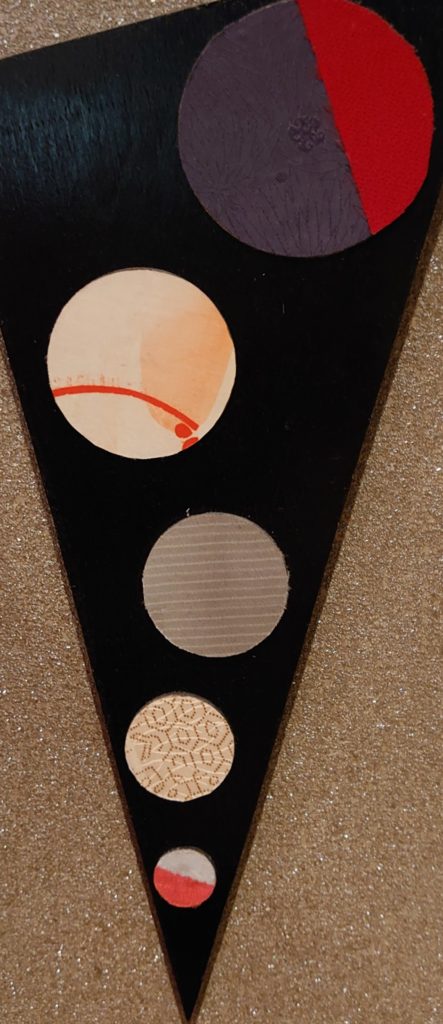
人類は古来、「老い」を醜く惨めな存在として捉え、「老人」を無益無用の役立たずとみなしてきた。古代ギリシャの英雄譚や悲劇でも同様であるが、ここでは仏教の「四門出遊」説話を取り上げる。若きゴータマが城の外に初めて出たとき、東門では醜く惨めな老人を見た。北門では病人を見た。西門では死者を見た。そして南門では修行者を見た*。この体験からゴータマは人生の実相を「苦」として捉え、やがて出家を志すことになる。ここに登場する「生老病死」の筆頭に位置するのが「老い」である。
*この説話では修行者の位置付けが曖昧である。修行者を見て出家を志したとする解説もあるが、それでは四苦にならない。もしも話を一貫させるなら、むしろ修行者=生=苦でなければならない。バラモン教の教義や修行のやり方(尺取り虫のような五体投地の苦行)では苦の輪廻から解脱できない。これがゴータマの直感である。
次に、古代から十七世紀のイングランドに飛んでみる。シェークスピアの作品に老人の頑固さと醜悪さを主題にした『リア王』があるが、ここでは『お気に召すまま』を覗いてみる。その一場面に「人生は舞台」、「人はみな役者」という有名な科白があり、それに続いて「人生は七幕」が登場する。赤ん坊から始まる七幕の最後が老人である。何と形容されているか。「第二の赤ん坊、記憶もなければ、歯もなし、目もなし、耳もなし、けっきょく何もなし」だ。これが当時の常識である。
他方、役立たずの老人に関しては世界各地の姥捨伝説がある。例えばグリム童話の「ブレーメンの音楽隊」もその一つだが、その賑やかな語りの奥には言い知れぬ悲哀が漂う。日本に目を転じると、柳田國男の『遠野物語』に「デンデラ野」の話がある。あるいは深沢七郎の小説『楢山節考』も有名である。どちらも50歳を過ぎた老人が60歳になると村の掟に従って捨てられる話だ。
*もちろん、老人は他面で、人生経験の知恵を体現する「長老」や「古老」として尊重されてきたし、平均寿命をはるかに超えた場合、物欲から解放された超俗的で神々しい「仙人」として崇められてきた。この点で中国の文化は極めて例外的であり、興味を抱かせる。しかし、そのような理想化や神格化は、かえって生身の老人の赤裸々な欲望を覆い隠し、困窮と悲惨の中の老後という現実を見えなくしてきた。その点を鋭く指摘したのは、老いについて記念碑的な本を書いたボーヴォワールである(『老い』)。
老いの否定的なイメージを生み出してきたのは、余剰人口を養うことのできない生産力の低さであり、身分制度における不平等であり、公衆衛生の知識や実践の欠如であった。その結果が「人生50年」である。悲惨な老いや無益無用の老人という常識は人生50年の産物である。余生わずかな老人は社会集団にとっては欄外者であり、それゆえに貧しく醜いのだ。
人生75年
©︎Y.Maezawa

産業革命以来、教育・仕事・引退という三ステージの人生プランが社会に定着してきた。人々は一斉に入学し、入社し、定年退職した。それに合わせて一斉に結婚し、男女の役割を固定し、子育てをし、余暇を楽しんだ。年齢を区分原理にして人生と社会のしくみを構築する考え方を「エイジズム」と呼ぶ。近代社会のエイジズムを枠付けるが「人生75年」だ。この場合、引退後の人生は男性ではほぼ10年と計算される(『ライフシフト』)。
人生75年の日本社会では人々はいまどのような老後を送っているのか。見渡してみると、元気で若々しい老人たちの大群が、街中の喫茶店やレストラン、ショッピングモール、公民館、スポーツジム、映画館、美術館、観光スポットに溢れている。巷では男は八掛け、女は七掛けと言われる。つまり、実年齢80歳の女性が56歳にしか見えないという意味だ。これは研究結果からも裏付けられている(鈴木隆雄『超高齢社会の基礎知識』)。
他方、身体の不自由な老人や認知症の老人が目立たない場所で支援や介護を受けている。中には施設をタライ回しされたり、死後かなり経って発見されたりする人も少なくない。徘徊などの問題行動、老老介護、介護離職、8050問題、自殺、介護の暴力、介護殺人といった話題が、毎日のようにメディアで取り上げられている。
このような二極化は、ごく一部の富裕層を除き、老いが深まるにつれてしだいに収斂する。現役で仕事をしたり、ボランティアをしたり、趣味の習い事をしたりと、多忙な日々を送る元気な老人たちも、やがて身体が不自由になるか、認知症を発症する。そして最晩年、介護施設に入るか、在宅介護にこだわるかの選択を迫られる。
最晩年期の老人を単純化して括れば、施設では世話を受けて完全な受動状態になり、在宅では孤独のうちに自己放棄の状態になる。共通するのは生きる意欲の喪失である。なぜか。生き続ける意味が見当たらないからだ。そのため老人たちは早く死ぬことばかりを願うようになる(拙著『新版「生きるに値しない命』とは誰のことか」)。
それでも現在の老人世代は未来の老人世代よりは恵まれているだろう。高齢化がさらに進行すると、年金制度ではもはやカバーできないため、老後の生活資金が決定的に不足する。そこに少子化やデジタルリモート化が重なると、子ども世代にはますます負担がかかり、親世代はいよいよ孤立・孤独に追い込まれる。人生75年を前提にした人生プランと社会のしくみを変えない限り、現在の若者世代の老後ははるかに悲惨となり、生きる意欲の喪失にますます拍車がかかるだろう。
老成学の挑戦

©︎Y.Maezawa
©︎Y.Maezawa

老いには三つのステージがある。第一は元気に活動できるステージ、第二は支援や介護を受けるステージ、第三は死に方を考えるステージの三つだ。「老い」の自覚が生じるのは、身体の節々が痛み出し、どこかしこが不自由になって意図通りに動かなくなるときである。だから、第一のステージは本格的な「老い」とは言えない(松田道雄『安楽に死にたい』)。
長寿化を前向きに受け止める論者は、第一ステージの元気な老人たちの働き方が多様になる点を積極的に評価する(『ライフシフト』や『ライフスパン』)。しかし、その議論からはしばしば格差や環境の観点が抜け落ちている。何よりも問題なのは本格的な「老い」に対する視線が旧態依然としている点だ。
第一のステージでどれほど元気に活動しようと、第二と第三のステージの老人が相も変わらず醜く惨めで役立たずとみなされ、もっぱら「支援」や「介護」の対象とされるなら、人生50年や人生75年に基づく常識と何ら変わるところはない。人生100年の時代になってもその常識が変わらないとすれば、誰も好き好んで老いたいとは思わないだろう。老いそのものに価値と魅力がないのなら、老いを否定するか、老いを通り越して死を願うまでだ。
それにしても、「老い」にはいかなる価値や魅力もないのだろうか。もしもそれを見つけることができたなら、私たちは老いることに一縷の希望を持つことができる。そこでこう問い直してみたい。
「老い」そのものに価値や魅力があるとすれば、それは何か?
「老人」に果たすべき役割があるなら、それはどんなことか?
右の問いは現在の老人世代だけに関わるのではない。むしろ中高年世代や若者世代にとって、これまでの常識に基づく人生プランと社会制度のしくみが変らない限り、いっそう深刻で死活的な問いになるはずである。ここで試されているのは、私たちが人生の時間と社会の空間を根本から変える覚悟と勇気があるかということだ。

©︎Y.Maezawa
老いの持つ価値と魅力を見極め、老人の果たすべき役割を探索するのは、私がかねてから提唱する老成学である。ここで「老成」という言葉には、いわゆる完成とか熟成ではなく、絶えざる生成という意味が込められている。老いを不断に問い直すとき、老いの深まりに応じて成熟のかたちが変容するからだ*。
*ちなみに、儒教では老人はあくまで尊敬の念を持って養われる対象である。伝統的な隠居制度はその見方に基づいている。それに対して穂積陳重は『隠居論』(第二版、1915年)の中で「優老」の視点を打ち出し、文明社会では知恵のある老人を活躍させるべきだと主張した。また、ジェロントロジーを最初に唱えたメチニコフも長寿を全うして自然死することを理想とした。つまり、穂積もメチニコフも老人は役割を果たすべきだと考える。その方が本人の生きがいにつながる。この点は老成学も同意見であるが、老いのステージに応じて役割を捉え直す点で異なる。とりわけ世話を受ける第二ステージでも互助の役割があると捉える点が老成学独自の見方である。
老成学の焦点は「生きがい感」である。老人の場合、生きがい感には二方向に伸びるつながり合いが結びついている。一つは老いの三つのステージのつながり合いである。そしてもう一つは老人世代と異世代のつながり合いだ。異なる世代同士をつなぐために老人世代がどのような老い方、つまり生き方と死に方を統一するのか、これが老成学の核心をなす問いである。
*生きがい(感)に関連するのは幸福感(幸せ意識)と人生満足感である。この三者の関連については拙著『システム倫理学的思考』の第8章で論じている。端的にいうと、生きがい感は現在から未来を志向したときの幸福感であり、人生満足感は現在から過去を振り返ったときの幸福感である。
(編集:前澤 祐貴子)