交流の広場

サイトメガロウイルス胎内感染
と精神疾患の関連の可能性
神経病理学
筒井 祥博
私たちが行った研究
私は 愛知県コロニー(愛知県医療療育総合センターと改称)の発達障害研究所および浜松医科大学第二病理学教室において、先天性サイトメガロウイルス感染症について実験モデルをつくり 約30年間研究した。
この研究の結果は アメリカやヨーロッパの学会誌などに投稿し 掲載されてきたが、分散的で 全体として何をやったのか分かりにくかった。一冊の日本語の本としてまとめることによって 一般の研究者などに全体像を知ってもらい、自分自身にも分かり易くしたいと考えた。
約2年かけて 外国の雑誌に載せた原著論文あるいは日本の学会の英文機関誌誌に載せた総説を日本語に直し、それを基に 『先天性サイトメガロウイルス感染症における中枢神経異常の発生機構』 と題して 本として出版することができた。原著論文から内容を抽出してストーリー性をもたせ、大系化するように努力した。
私は 自分でやりたいと思う研究テーマを見つけるのに随分時間がかかったが、40年以上前にある病院で この病気で亡くなった新生児を臨床・病理検討会(CPC)で発表したことがきっかけで、サイトメガロウイルスの感染が発育期脳にいかに影響を与えるか その機構を研究しようと考えた。運良く愛知県コロニー研究所の形態学部に室長として移ることができた。この研究所は 発生学や遺伝学の研究のレベルが高く 学ぶことが多かった。
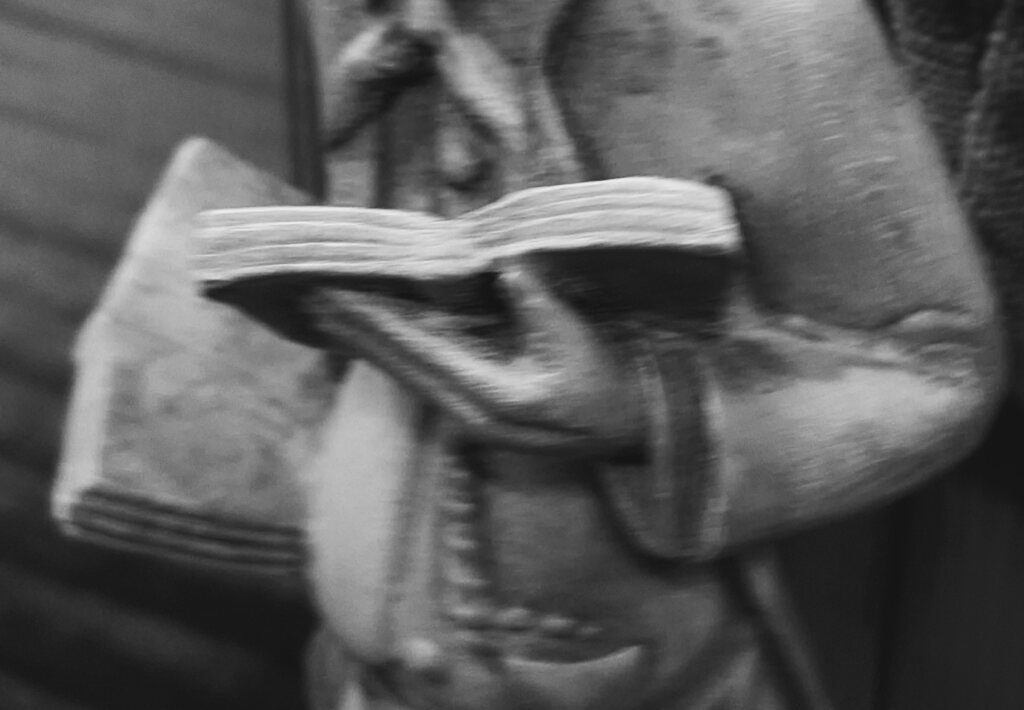
先天性サイトメガロウイルス感染症について
病原体が胎生期あるいは周産期に感染して、胎児に障害を起こす疾患は TORCH症候群 と呼ばれている。
Tはトキソプラズマ、Rは風疹ウイルス、Cはサイトメガロウイルス(CMV)、Hは単純ヘルペスウイルス、Oはその他梅毒など を指している。
トキソプラズマは一種の原虫であり、梅毒はトリポネーマという細菌の一種で ウイルスではない。CMVはヘルペスウイルスに属す大きなDNAウイルスである。CMVに感染した妊娠中の母親から胎児に母子感染し、感染が強い場合は 小頭症を主体とする脳の異常、全身の発育障害が起こり死亡する。
ヒトにおけるCMVの胎生期の感染によって、3つの状態になると考えられる。
第一に、胎生後期に脳室壁に強く感染して 石灰沈着を伴う神経系細胞の壊死を伴って 小頭症などの脳形成障害を生じる。
第二は、出生時は無症状であるが 生後しばらくして、感音性難聴あるいは自閉症スペクトラム精神発達遅滞などの症状が現れる。
第三は、感染した胎児は正常に生まれ成長するが、成人期に何らかの精神疾患 あるいは 認知症の発症に関与する。この第三の状態は推定されるが 確証されていない。
先天性CMV感染症の実験モデル
CMVは種特異性が強く、ヒトのCMVは人に、動物のCMVは その動物だけにしか感染しない。私たちは マウスのCMVを使って マウスの動物感染系を作って 脳形成異常がいかに生ずるかを研究し、ヒトの先天性CMV感染症による脳障害の発生機序を推測してきた。
その結果、マウス胚は胎生初期にはCMVに感染感受性がなく、胎生中期に感受性が主として中胚葉系細胞に現れ、胎生後期の脳形成期に脳室壁に感染感受性が強まることを明らかにした。
正常な脳形成においては 脳室壁の神経幹前駆細胞が分化しながら 皮質に移動し、そこで神経細胞の層状構造を形成し 大脳皮質が形成される。私たちは、神経幹前駆細胞がCMVに感染感受性が高く、急性感染して溶解壊死し、脳形成が障害されて小頭症などの異常が生ずることを明らかにした。
さらに、胎生後期胚の脳室壁にCMV感染すると、感染した神経細胞が皮質へ移動し、神経細胞のみが持続的に感染することを明らかにした。
発育期にCMVを感染したマウスを6カ月飼育し、脳を取り出して大脳スライス培養をすると 感染細胞が出現し、感染性ウイルスが放出することが分かり、ウイルスが再活性化してくる細胞は神経幹前駆細胞であることを その脳内での局在性および免疫染色によって示した。これはCMVが脳内で潜伏感染することを細胞レベルで明らかにした最初の研究である。
ここまでが 私たちが明らかにした主な事実であり、『先天性CMV感染症の中枢神経異常の発生機構』の本で述べた。ここで、胎生期あるいは周産期にCMVが発育期脳に感染して、正常に発育して成熟した個体がどうなるか、という上記第三の可能性について考察する。
サイトメガロウイルスの持続感染・潜伏感染について
30年以上前までは、ウイルス感染した細胞は感染細胞特異的なキラーT細胞の攻撃を受けて感染細胞は溶解して死滅する急性感染が注目され、これがウイルス感染によって病気になる原因である と考えられた。その当時 ある著名なウイルス学者が、「ウイルスが感染しても細胞は殺さずに、その機能を変えることによって病気になるメカニズムを解明していくことが これからのウイルス病態学の方向である」と提唱し、私はこの考えに強く触発されて、発育期脳へのCMVの感染の影響を研究しようと考えた。
かつて 日本ウイルス学会のフォーラム『21世紀のウイルス学の方向性』で、大阪大学微生物学研究所の加藤四郎教授が、「脳に潜むウイルスが個体の行動と思考にいかに影響するかを明らかにすることが、今後の魅力ある課題である」と話されたことが強く印象に残った。
CMVの感染様式について
一般に、CMVの感染の仕方に急性感染と慢性感染(持続感染)がある。急性感染ではウイルスが感染して感染細胞でウイルスゲノムが増えて感染細胞は腫大し、沢山のウイルス粒子が放出されて、感染細胞は死滅する。これに対して ある種の細胞(造血細胞や血管内皮細胞など)の一部では、感染細胞が持続し続けると考えられる。 持続感染は、分子的機序は明らかでないが、ウイルスの遺伝子発現は強く抑えられている。症状を伴わない低いレベルのウイルスを生涯にわたって放出し続けていると考えられている。一方、潜伏感染ではウイルスゲノムが細胞の中で維持されているが、免疫力が正常な個体では、ウイルスゲノムは発現せず静止状態であり、免疫不全状態になると再活性化して感染細胞がウイルスを放出する。
ヒトCMVの持続感染、潜伏感染の研究
既に述べたように CMVは種特異性が強く ヒトのCMVは動物に感染しない、動物のCMVはヒトに感染しない。私たちはマウスのCMVをマウスに感染させて研究してきた。ヒトとマウスでウイルスのゲノムサイズ、主なゲノムの数と構造は類似しており、その感染細胞特異性、病原性も類似している。
ヒトCMVは主として造血細胞で潜伏感染・持続感染すると考えられている。従って、培養細胞や初代培養細胞、あるいはオルガン培養で研究されている。一般にウイルスの感染感受性は、同種の細胞でも培養細胞と個体レベルでは異なっている。
ヒトにおけるCMVは脳以外の臓器で臨床的に注目されている。一部の造血細胞で潜伏感染し、正常免疫状態ではウイルス遺伝子は発現せず静止状態で、免疫不全状態になるとウイルス遺伝子は再活性化する。すなわち臓器幹細胞や臓器の移植、HIV感染、あるいはがんの化学療法などに引き続いて再活性化し、重篤な肺炎などの感染症が起こすことがある。
しかし、ヒトを対象として脳に潜むCMVが 個体の病態にいかに作用するかに関する研究は不可能であり ほとんど分かっていない。動物実験モデルによるアプローチで研究する以外にない と考える。
脳におけるCMV感染の特殊性
脳は免疫学的に 特殊な部位である。脳の毛細血管には脳・血管関門(BBB)があって、正常な状態では基本的に免疫細胞や高分子の免疫グロブリンは通過しない。従って、感染防御は 主として脳に内在するミクログリアやマクロファージが担っている。脳以外の臓器のように免疫を担当する樹状細胞などが自由に臓器内を移動することは困難である。
マウス胚への感染では、脳へのCMVの感染は胎生後期の脳形成期(ヒトでは胎齢2−3週)に脳室壁の神経前駆細胞に感染し、未分化グリア系細胞は脳室壁周辺で急性感染し、未分化神経感染細胞は感染して皮質に移動し、層状構造を形成し持続感染する。私たちはこのようにグリア系細胞と神経細部では感染様式が異なることを明らかにした。
脳におけるCMV感染の特徴は胎生期脳で感染感受性が高いことである。周産期を過ぎると神経細胞は感染しにくくなる。これは一般的にはナチュラル・キラー(NK)細胞が感染を防止するためと、考えられている。しかし、脳では、ミクログリア・マクロファージが感染防御に当たるが、神経細胞はこれらの細胞に攻撃されにくく、また感染神経細胞はアポトーシスが抑制され、持続感染へと移行することを私たちは示した。
胎生期脳へのCMV感染と生後成長して生ずる精神疾患との関連
近年、胎生期あるいは周産期に病原微生物の感染、あるいは脳に炎症やストレスを受けた胎児は、生後成長して成人になって生ずる神経・精神疾患の一因になっている可能性があることが、ヒトの症例の疫学的研究で示唆されている。
CMVの胎生期あるいは周産期の感染が発育後に生ずる統合失調症の発症に関連する可能性があるという研究がある。統合失調症はいくつもの遺伝的要因および環境的要因の複合による多因子遺伝の疾患である。加えて生活習慣などが病気の発症に関与する複雑な疾患である。従って、ひとつの要因がその病気の発症に決定的であるとは言えない。
ヒトにおいて、胎生期のCMVの感染と統合失調症の発症との相関に関する疫学的研究で、わずかに関連があるという研究と、ほとんど関連しないという研究がある。CMVの感染の時期を同定することは 抗体検査だけでは困難である。デンマークのグループは臍帯のCMVの感染と統合失調症に関連するとされている遺伝子の一部の変化にある程度の相関があったと報告している。この疾患の発症に発育期のCMVの感染は必須ではないが 発症を促進するひとつの要因である可能性はある。これはトキソプラズマなどの病原体でも認められる。
私たちの研究の先にある目標
私たちの研究の目標は先天性CMV感染の上記の、第三番目の課題である 胎生期にCMVが感染して全く正常に生まれて、正常に発育した個体が、成熟期に生じてくる神経・精神疾患と何らかの関連があるかどうか 細胞レベルあるいは 遺伝子レベルで明らかにすることである。胎生期にCMVが感染した神経細胞で、個体の成長に伴い いかに持続感染・潜伏感染するか、そのメカニズムを明らかにしていくことである。
CMVの感染細胞に必ずしもウイルス感染の痕跡があるとは限らない。CMVが感染したことによって神経細胞のゲノムに異常を来した状態が持続している可能性もある。当面はウイルスが持続感染している神経細胞をいかにマークして成熟期までフォローすることができるかが問題である。それらの神経細胞の異常が 個体の行動にいかに関わるか、あるいは疾患モデル動物への胎内感染が、神経細胞レベルあるいは遺伝子レベルの異常にいかに関わるか、などを明らかにする必要がある。
トキソプラズマによる脳内感染と宿主の行動異常
ヒトにおける胎生期の感染と、発育・成長して生ずる可能性のある神経・精神疾患との関連は、先に述べたウイルス奇形学の原因とされるTORCH病原体、特にトキソプラズマの胎生期の感染について研究されている。トキソプラズマはウイルスでなく一種の原虫で CMVと全く異なる病原体であるが、CMVと同様に母子感染し、先天性トキソプラズマ感染症として先天性CMV感染症と類似している。トキソプラズマ感染について簡潔に触れる。
トキソプラズマの個体レベルの感染で、個体の行動や思考に影響を与えることが分かってきたので紹介する。2010年代に脳に寄生するパラサイト(病原体)が宿主の行動や人格変え、さらに精神疾患の発症と関連するという記事がニューヨークタイムズに掲載された。脳に潜むパラサイトが宿主の人格と行動を変える可能性があると言うことで、一般的な関心を引いた。
トキソプラズマの感染によってラットやマウスに行動異常が起こった。これらの動物はネコの尿の臭いを避ける習性があり、ネコから身を守っている。トキソプラズマを慢性感染させたこれらのげっ歯類の動物は、ネコの尿の臭いを避けなくなる。またこの病原体は 脳の扁桃体に親和性があり、病原体の嚢胞がこの脳の部位に より多く認められたという。トキソプラズマが脳の特定な部位に作用して宿主の行動を変えたことになる。扁桃体は複数の神経核からなり、人間を含めた高等動物の情動や記憶に関わると考えられている。トキソプラズマがなぜ扁桃体に親和性があるのか、その感染によっていかにその機能が変調するのか 分かっていない。
トキソプラズマの感染が人の精神疾患に関与することが疑われているが、明確な因果関係に関する直接的な証拠は示されていない。精神疾患の代表的な統合失調症や躁うつ病などは遺伝的な要因と環境的な要因が相互に絡み合って成長した個体に発症する。トキソプラズマ感染は環境因子のひとつと見なされている。精神疾患の患者でトキソプラズマ抗体のレベルが上昇していることが報告されている。
ヒトにおけるトキソプラズマ感染と自殺行動とが疫学的な相関があることが知られている。これはパラサイト(寄生体)の、神経指向性、慢性感染のひろがり、そして特異的が、宿主の自殺行動のリスクを高めると考えられている。
精神や感情不安定なコンフォートにおける自殺行動と血清トキソプラズマIgG抗体の上昇に関連性があるという幾つかの報告がある。2021年ヨーロッパの3つのグループでメタアナライズし、上記の結果をサポートするボリュームある総説が発表された。しかし、そのメカニズムは分かっていない。
げっ歯類の研究から、トキソプラズマの原虫が脳の扁桃体に潜み、サイトカインや神経伝達物質を過剰に産生することによって ある種の神経細胞の機能を変調させた結果であろうと考えられる。トキソプラズマが神経細胞や神経幹前駆細胞に直接感染して その機能を変えているとは考えられない。この点において 私たちが考えているCMVによる神経・精神障害との関連は 基本的に異なる現象であると考える。すなわち CMVは直接神経細胞に感染して 持続感染あるいは潜伏感染して 神経細胞の機能を変える可能性があると考える。
〈2025年1月20日 記〉
(編集: 前澤 祐貴子)
* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。