活動の実績
老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学事始 > 【老成学事始】 Ⅱ 老いのかたち、老い方のモデル 森下直貴
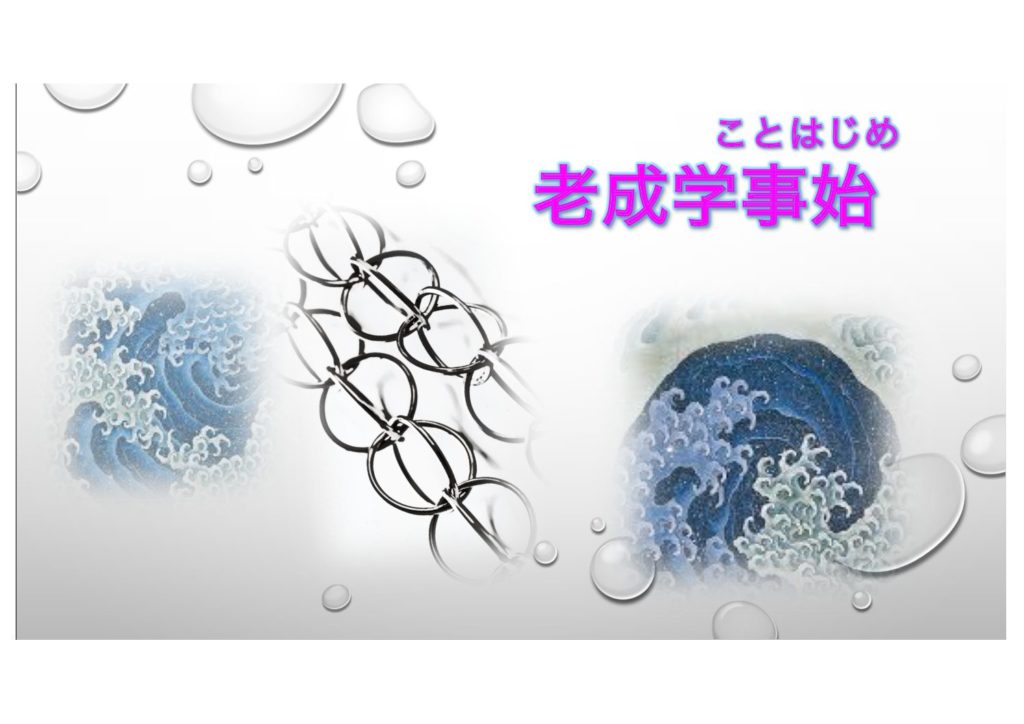
【老成学事始め】
二
老いのかたち、
老い方のモデル
森下直貴
はじめに
超高齢社会の中で現在、「老いのかたち」あるいは「老いの文化」が見えない。これを鷲田清一は「老いの空白」と呼ぶ。私なりに言い換えると、老いの生き方、つまり老い方のモデルがない。鷲田はまた「老」と「幼」は対照的だと言う。育児と介護は人間にとって「あたりまえ」の営みだ。私なりに言えば、どちらも世代継承のコミュニケーションである。
介護や社会保障はたしかに問題ではあるが、それはあくまで表面的である。根本にある問題は生き方のモデルなのだ。
しかも、老いの世話はあたりまえの営みであり、世代継承のコミュニケーションである。ここまではわたしは鷲田に基本的に賛成する。しかし、鷲田が推奨する老いのかたちには賛成できない。なぜか。空白をもたらす背景である社会の捉え方が異なるし、この捉え方を導く思考法がそもそも違うからだ。
老いにも段階がある。近年では元気な老人の大群がいたるところに溢れている。WHOからは「アクティヴ・エイジング」という、老人の自己実現を追求するモデルが推奨されている。しかし問題は、もはや「アクティヴ」ではなくなる最晩年期だ。この段階になると、在宅であろうと施設であろうと老いのモデルがない。ひたすら死ぬのを待つだけだ。そこには生きる目標がない。
わたしが提唱する「老成学」は、老いの深まりに応じた生き方のモデルを探求する。探求には対話の相手が必要だ。できれはふわさしい相手がいい。その相手が哲学者の鷲田清一の『老いの空白』である(岩波現代文庫2015年)。この章では、鷲田の考え方と対比する中で、老成学の立場を明確にしながら、これを肉付けしていくことにしたい。なお、論述の全体を導くのは、第一章でたどり着いた「コミュニケーションにおける役割」の視点である。
1 『老いの空白』の見解
まずは鷲田の考え方の大意を私なりにまとめてみる。
⑴ 鷲田にとって、老いの空白をもたらす根源は、産業社会の「生産力主義」に求められる。そこでは効率性や有用性といった機能が重視される。そのかぎり生産(力)と再生産(生殖)が尊ばれ、それに役立つ「若さ」に価値が置かれる。それに対して「老い」は役に立たないが故に価値はない。老いは老廃・老残・老害でしかなく、老人は余計者・厄介者なのだ。
⑵ 生産力主義はまた、時間の観点からみれば前望的(プロスペクティヴ)である。未来から現在を捉える。未来の目的に向かう手段としての現在を見る。だから目的論とも言える。これに生命=植物のメタファーを重ねると、歴史=時間がリニア(一直線)になる。さらにこのリニアな時間を人々の人生に重ねてみると、若さは人生の上り坂、老いは人生における下り坂になる。老いは衰退・下降・退行という時間イメージで捉えられる。
⑶ 老人介護の場面の背景にあるのが、上述のような老いをめぐる価値と時間である。そのかぎり、介護する人と介護される人の関係性には、種々の歪みがともない、福祉イデオロギーに根ざした暴力性が生じる。この点は介護が家族の自助から社会の公助に移されても変わらない。老人はあくまで受動的存在であり、他律的な扱いを受ける。その結果、「老いのかたち」が見えなくなっている。
⑷「老いのかたち」を見つけ出す手がかりはどこにあるのか。生産力主義では「できる」ことが評価される。できることを増やすことが「成長」である。産業社会以前には老人の経験や知恵は成熟を意味したが、産業社会ではむしろ邪魔なのだ。だから、産業社会には成長はあっても「成熟」はない。しかし、成熟は人生にとって不要だろうか。ここで鷲田が着目するのは「できない」ことである。
⑸ できないということは、不自由、支障、限界があるということだ。この観点から人生を見回してみると、「できない」ことの方があたりまえであることが浮かび上がる。幼児がそうである。障害者も、病人もそうである。とりわけ老人がそうである。であるなら、成熟の中身は、「できない」ことの経験をどれだけ深く内に湛えられるかにかかっている。
⑹ この「できない」経験を湛えた成熟の観点から、鷲田は一挙に、産業社会の外へと飛翔する。できないという限界の意識を跳躍台にして、生産力主義で貫かれた意味の世界の外に超出する。そこに生じる「反世界のまなざし」は、翻って意味世界に向かい合い、そこを縦横に区切る境界線、したがって能力差別=人物差別の区分線を流動化する。それは一種の超越の視線なのだ。
⑺「できる」ことを評価する世界は、より抽象度を高めて言えば、「する」世界である。「できる」「できない」は「する」世界の分布である。超越の視線は「できる」世界や「する」世界を通り抜け、その彼方に「しない」世界を想像する。ここでは、ありのままの特異な存在が特異な存在として認められる。「ある」ことの世界なのだ。こうして「ともにする」コミュニティではなく、「ともにある」コミュニティが構想される。
⑻ それまでできていたことができにくくなる、あるいはできなくなる。そのとき人は不意に老いを意識する。生きる目標がなくなり意欲が萎えるとき、人は身体の衰えを感じ、生き疲れを覚える。生産力主義の産業社会では。老いは「できない」ことの象徴である。超高齢社会では元気だが、徐々にできなくなる老人が大量にいる。しかも「できない」ことや「しない」ことを日常的に自覚できる。これは幼児にはできない。障害者は少数である。傷病者は動けない。とすれば、老人世代にこそ「ともにある」コミュニティを実現する役割を期待できるのではないか。そこに「老いのかたち」がある。
2 老成学の見解
以上が鷲田の考えの大意の要約である。最初に、語り方にとって前提となる思考法に注目して、鷲田とわたしの違いを浮き彫りにしたい。
鷲田の考えを貫いているのは二元論的な類型的思考法である。たとえば、生産力主義の産業社会に対して幼児と老人が親密は共同体、換言すれば近代に対して前近代、リニアな時間に対してポリフォニックな時間、世界に対して反世界、できることに対してできないこと、することに対してあること、以上である。そのような類型的で二元論的な類型の織物の上に鷲田の考えが座っている。本人はそうは考えていないかもしれないが、それは秩序をカオスによって活性化するという一九八〇年代に流行した発想と親和性がある。この発想では近代を批判するための拠点が(意に反して)共同体に傾斜する(文中に中村雄二郎、井上ひさし、栗原彬らは当時の知的リーダーである)。
わたしが採用するのは類型的思考法ではなく、四次元相関の思考法である。類型とは四次元相関のうちの一面的が偏って強調された表現である。類型的思考法は二元的な対立構図をとりがちになる。また、類型同士の対立を生じるが、それを解きほぐすことができにない。そのためには類型の元にある四次元の相関(セット)に立ち戻り、そこから類型的な固定化を緩め、偏りを正してバランスを回復させることが必要なのだ。以上については『システム倫理学的思考』を見られたい。
続いて、主要な論点に沿って批判と積極的な提案を試みる。
主たる論点をあらかじめ列挙する。
・老いの空白の背景が産業社会の生産力主義であるという枠組みの問題点
・障害や病気や死の経験とは異なる老いの経験
・老人の時間経験
・自己言及の高次化としての成熟という捉え方
・若者世代の成熟の独自性
・反世界のまなざしと老人的超越の考え方との類似性
・人生のリニアではない時間の捉え方
・老人の時間の新しい見方
・世代的コミュニケーションと連帯的コミュニケーション
以上を順次論じていこう。
《次回に続く》
(編集:前澤 祐貴子)