交流の広場

©︎Y.Maezawa
❷
【読書ノート】
意識があるとはどのようなことか
浜松医科大学名誉教授
医師(神経病理学)
筒井 祥博

十年以上前、茂木健一郎『脳と仮想』(新潮文庫、2004年)を読んで感動した。このことは前回の「高齢期を生きるということ」で触れた。2012年Natureの書評にChristof Koch,”Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist”が載った。この本は英語で読むにはかなり難解であったが、メモをとりながら何とか概略を知ることができた。
この本のことを常葉大学の紀要で少し触れたところ、浜松医科大学の教授であった寺川進先生(神経生理学)が興味を持たれた。
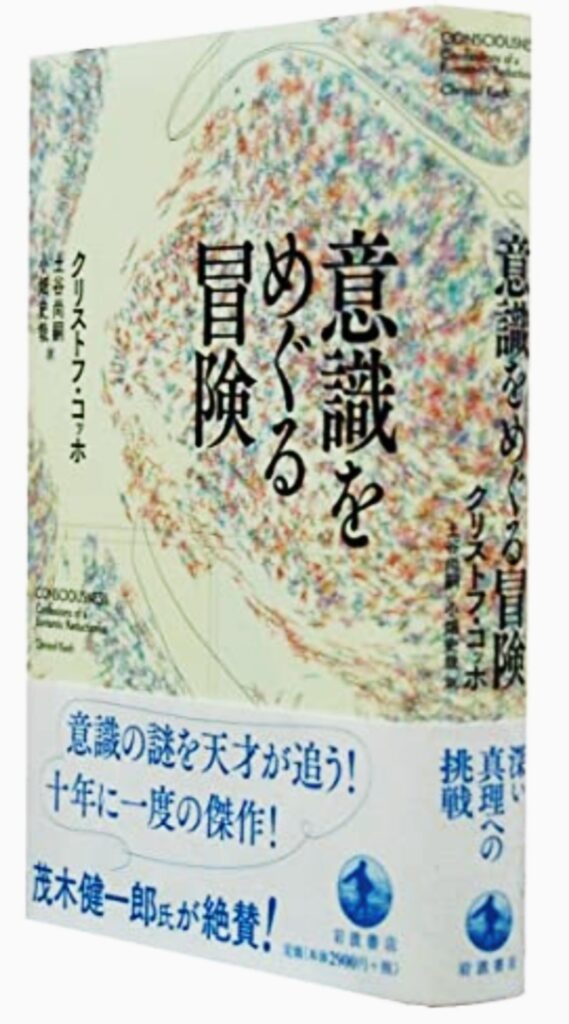
その後、この本はクリストフ・コッホ『意識をめぐる冒険』(岩波書店、2014年)として出版された。意識に関する訳本としては、2013年アントニオ・ダマシオ『自己が心にやってくる』(早川書房)、2015年ジュリオ・トノーニ『意識はいつ生まれるか』(亜紀書房)も出版された。これらの本を寺川進先生とメールで意見を交換しながら1年ほどかけて読んだことがある。
寺川先生から多くを学んだが、独自の論理をたてながら読まれているのに感心した。私は理解が曖昧でよく理解できない点もあった。意識はデカルトの「我思う故に我あり」から出発していると言われているが、脳科学との関連の学問としては始まったばかりの領域で多くは仮説で話しが進められていると聞く。
今回は意識について学問的視点は分からないので、
主として脳科学的視点で感じたことを感覚的に書かせて頂いた。
意識について
意識という言葉はよく聞くが漠然としている。化学工場の事故や、冬山などの遭難にあった犠牲者の状態について、最初に「意識」があるかどうかについて報じられる。この場合の意識とは、呼びかけに対して応じるかどうかであろう。
今回私は意識とは何かについて学問的というより感覚的に考えてみた。朝起きると意識が覚醒し、私の前に周りの世界が広がる。朝日が庭の花々や木々の葉に当たっている時は明るく爽快な気分になる。意識のない状態とは深い睡眠の時、全身麻酔にかけられた時などだ。私は何度か全身麻酔で手術を受けたことがあるが、意識がなくなって行く時のことは覚えていない。麻酔から覚めた時は、眠りから覚めたときと同じである。私が認識する周りの世界は視覚・聴覚から私の脳に入ってくる感覚によって形成される。この主観的な感覚をクオリアと呼んでいる。主観的感覚によって引き出される今までの経験、記憶、知識などによって意識が生じると考えられる。私たちは意識を通じて周りの世界を認識している(クリストフ・コッホ『意識をめぐる冒険』、43-44ページ)。
意識はあいまいな概念で、明確に記述された教科書はないとされている。しかし、私たちが周りの世界の中で生きてゆく上で、私たち自身の状況を認識し、対処していく最も中核的な脳と心の状態である。「心」もよくつかう言葉であるがその概念は曖昧である。生物進化の最も高度の段階として心の世界が生じたと考えられている。心は脳の神経活動の機能的表現であるというだけでは説明できない。「心で分かること」と「頭で分かること」は必ずしも一致せず、心は決して脳の神経機能で表れた現象だけではない。平和、幸福感など抽象的概念を心がなくて感じることは難しい。自責の念、感極まった状態などは脳の機能だけでは説明できないと思う。意識には心がともなっている。心は共感とか同情として他者へ移り、個人が死んでも心は近親者の心の中にその一部が残る。
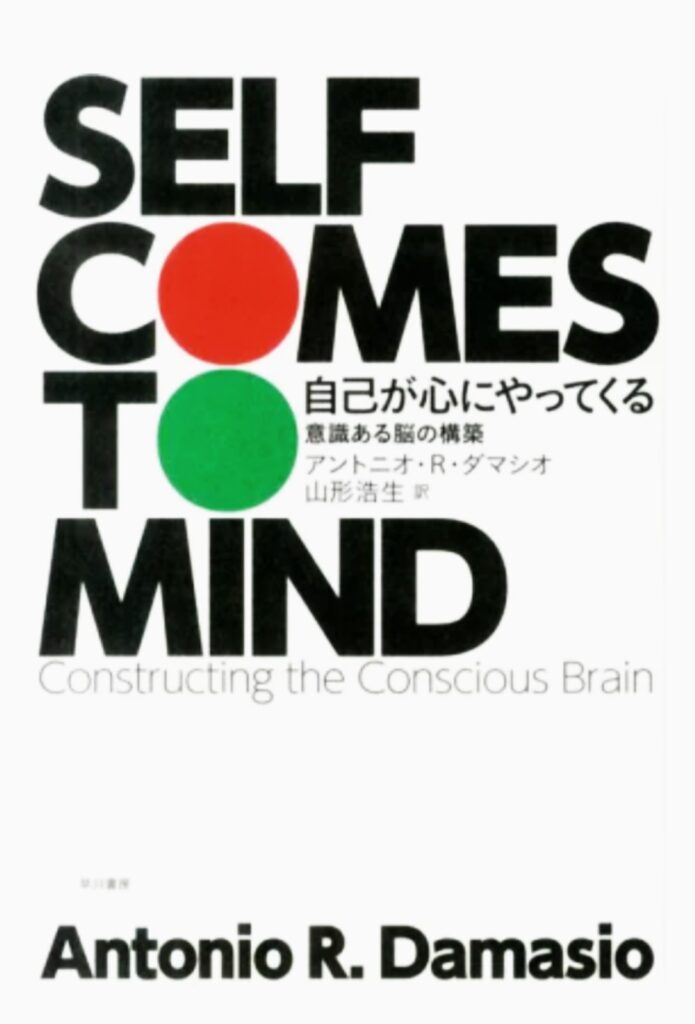
もうひとつ意識にとって、重要な特徴は、意識することが「なぜ他人でなく私なのか」、つまり私たち人間にとって意識には私(自己)を伴っている(アントニオ・ダマシオ『自己が心にやってくる:意識ある脳の構築』、19-22ページ)。抽象的あるいは一般的な現象ではなく私たちひとり1人の中に生じてくる独自の現象である。私が怪我などして痛いという感覚も意識の一部だとしたら、痛いのは私であって他の人の意識ではない。ダマシオは意識ある心に自己が生じてくると表現している。意識の中で何かに注目するのは自己があるから起こる。動物にも大なり小なり意識と心はあるがが生じていないという(コッホ73-74)。
「無意識」とはどのような状態であろうか。ピアノなど楽器の演奏を習うとき、始めは意識して四苦八苦して弾くが練習を積むと無意識に演奏できるようになる。これは楽器だけでなくスポーツや車の運転なども同じである。記憶の種類でいうと「手続き記憶」ということになる。精神分析で有名なフロイトは無意識を重視したが、彼の言う無意識とは意識下に蓄積していて通常は意識していないマグマのようなものが感覚的刺激でクオリアとして脳に立ち上がってくることである。
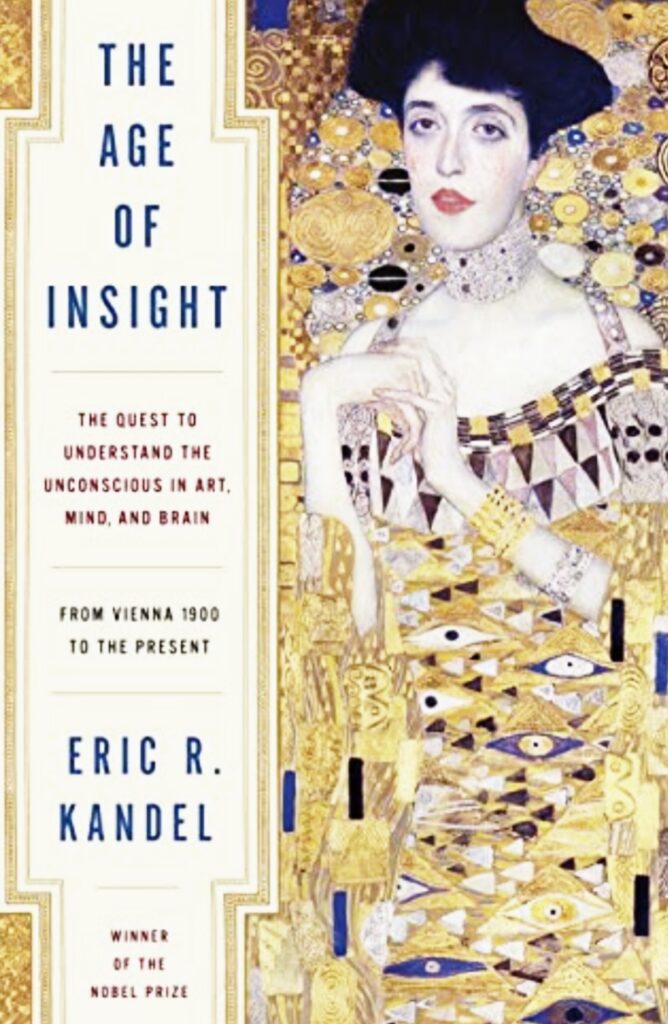
20世紀の初頭にこの無意識を基盤としてクリムトを筆頭とするウィーンモダニズムの芸術が開花する様子を読んだことがある(by Eric R. Kandel,The Age of Insight)。無意識の中に蓄積された感動などが、何らかの切掛けやクオリアによって浮かび上がってくる。そのメカニズムは分かっていない。
意識の喪失
意識があるかどうかを、臨床的にどうして見極めているか。声をかける、手を握る、痛覚刺激を与える。反応しなければ意識がないと考えられる。最近まで事故などによって植物人間状態になった人はただ生きているだけで意識がないと思われていた。機能的MRI (fMRI)やPETなどの脳画像で調べてみると脳が活動していることがあると報じられた。私はこのような状態があることを知って強い衝撃を受けた。意識があるのに封じ込められた状態(ロックイン)があるのだ。この様な状態には意識レベルに程度の幅があるだろう。脳が意識のない植物状態から意識のあるロックイン状態まで種々の段階があり最小意識状態と呼ばれている。意識がない植物状態であると見なされている患者の半数以上に意識がないと誤診されているという。ALS(筋萎縮性側索硬化症)の患者もある段階で意識があっても表現できない状態があると予想される。
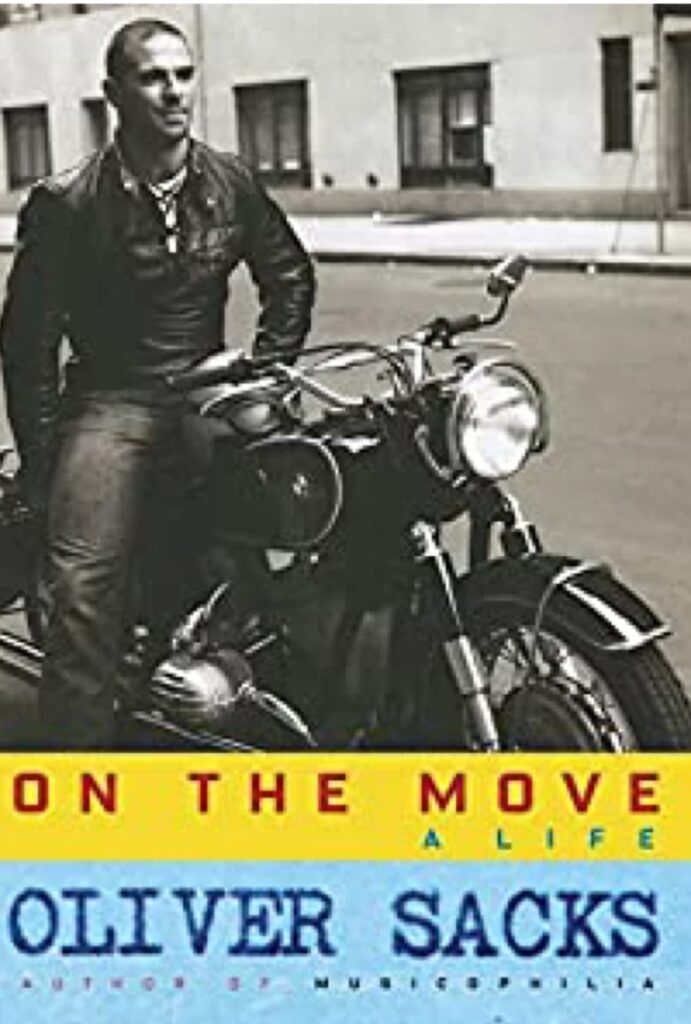
Oliver Sacksというオックスフォード出身の臨床医で世界的に知られた著述家がいた。Sacksの”On the Move”という自伝を読んだことがある。その中で “Awakenings”(覚醒)という項目がある。ニューヨークで1930年代に奇妙な脳炎が流行して意識を失った患者が集められた病院で、Sacks医師は1950-60年代に若い医師として勤めた。その当時パーキンソン病患者の脳を賦活化する薬があった(今でも使われている)。L-dopaを脳炎後30年以上意識がない患者に使うことを提案した。L-dopaを投与された患者は目覚めて記憶を取り戻し、脳活動がほとんど正常になった。Sacks医師はこのことをドキュメンタリーとして発表し世界的に衝撃が広がった。しかし、目覚めた患者もこの覚醒は長続きせず、再び意識のない元の状態に戻っていった。30年ぶりに一時的に覚醒させた患者にとって、このことがよかったのかかえって不幸であったのか賞賛と批判が交錯した。
意識の脳科学
脳幹上部(中脳と延髄の間だ)が意識と関連していることが以前から知られている。その部分が損傷すると失神あるいは意識に重大な障害を生じることが分かっている。しかし、意識に関する脳の部位はそこだけでなく、情報は視床—大脳系を通じて大脳に伝えられ、大脳皮質の広範な神経細胞が意識に関与していると考えられている(コッホ、116ページ)。意識は特定の部位の神経細胞だけから生ずるのではなく、小さな神経ネットワークが集合して、大きな神経ネットワークになってはたらくと考えられる。脳には860億個の神経細胞があり、そこから出る神経突起と樹状突起が形成するシナプスは1千兆個にもなると考えられている。
かつて情報は神経細胞の中に蓄積すると考えて、訓練させたネズミ何千頭から記憶に関連した物質を分離したとする研究者がいたが追試できなかった。情報は神経細胞に蓄積されるのではなく、神経細胞と神経細胞を繋ぐ新たな神経ネットワークとして蓄積される。これをニューロンのマッピングと言い、知識は新たなマッピングの形で蓄積される(ダマシオ、27-28ページ)。これらのネットワークが統合されていなければ意識として機能しないとされている。小脳は大脳の80%ほど神経細胞があるにもかかわらず意識を形成するネットワークでなく、運動の調整、体の平衡を保つためのネットワークとして構成されているので、意識と無関係である。小脳が無くても意識は保持される。大脳は左右の大脳を分割しても意識は保たれることが、分離脳の手術の結果で分かっている。意識に関して大脳皮質のニューロンがどれであっても同じというのでなく、ニューロンが大脳皮質のそれぞれの部位において生ずるクオリアが異なり、大脳の部位とその機能は強い特異的な関係性があることが特徴であるという(コッホ、31-32ページ)。
トノーニらは、意識の「統合情報理論」を提唱した。彼らによれば「ある身体システムは情報を統合する能力があれば、意識が生じる」と考えた。意識のレベルは、情報の量とその複雑性を測定することによってΦという単位で数値として定量的に表わすことができるという(トノーニ『意識はいつ生まれるのか』、129ページ)。しかし、その測定方法は曖昧でよく理解できない。しかし、意識は情報量とそのネットワークの複雑さで表すことができるという考えは納得できる。コンピューターにいくら多くの情報を蓄積しても、お互いの情報が統合されていないので意識にはならない。トノーニらは、TMS脳波計(経頭蓋磁気刺激法)で頭蓋骨の外から脳を刺激して脳波図と対応させる方法で、特定のニューロンを刺激し、活性化させることができる方法を開発し、この方法は意識状態が低下した脳を賦活化させることに応用される可能性がある。
意識にとって最も分からないことは、私たちは意識があるときに漠然と身の回りの世界を感じているのでなく、何かに注目している。そのサインを出すのが花の色であったり、鳥の鳴き声であったりする感覚をクオリアと呼んでいる。問題は無数にあるシステムの中で、なぜひとつの特定のことを意識するのか。脳は同時に幾つかのことに焦点を与えることができない。また何かを見ていても他のことを考えていることがある。この何かに焦点を当てる機能は明らかでない。何かひとつのサインによって無意識の中にあったものが数珠繋がりのように思い出されてくる。そのメカニズムが分からない。
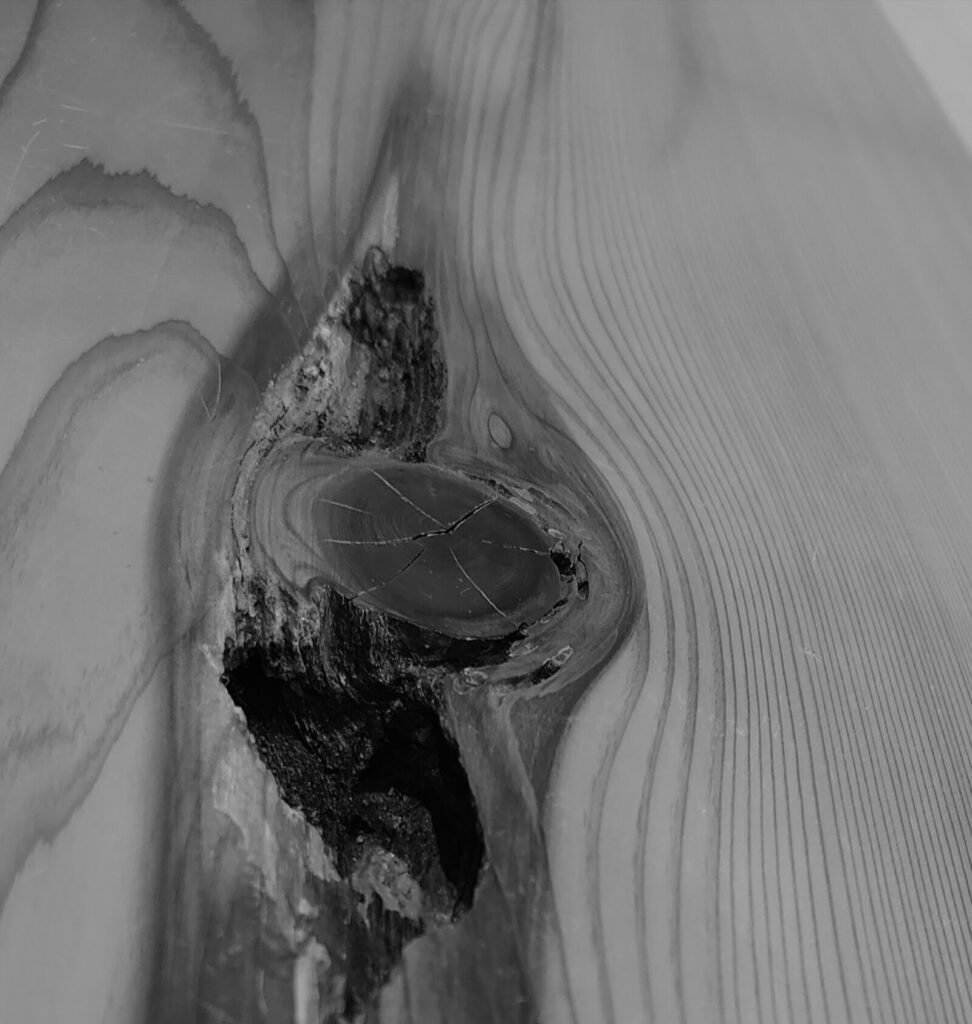
©︎Y.Maezawa
意識と恒常性
生きもの(生命体)の特徴は複製と恒常性である。複製とは増殖して増えていくことであり、鉱物などでは絶対にありえない。恒常性とは生体の生成と分解およびその機能の均衡が保たれていることである。病院に入院すると毎朝血圧、体温、脈搏などのバイタルサインを測られる、それらが正常の範囲内にあることを確かめられる。人間が生きてゆくためには、沢山の身体内部のパラメータ、例えば血液や体液のpH、代謝に関わる化学反応などが正常範囲であることを恒常性が保たれているという。脳であれば、感覚・運動・記憶などに関わる神経機能がその基盤にある神経細胞などの化学的パラメータにおいて平衡が保たれていることが必要である。
意識に関して神経ネットワークの恒常性は自然選択によって進化してきた。生命体の快・不快、報酬と処罰によって効率よい生命制御の行える範囲が選択されてきた。構築されてきたシステムの中で恒常性に範囲があり、その辺縁近くであれば、不快な状態であり病的な意識状態になり、恒常性の辺縁から外に出てしまえば死に至ると考えられる。恒常性の範囲の中の最適なポイントに調節されていれば、健康な生き方を可能にする(ダマシオ、60-63ページ)。沢山のファクターが統合的に調節されて脳機能だけでなく身体システムが調和的に働くことによって、最高の意識状態になれば、wellbeingの状態であり幸福だと感じられる。
身体の恒常性を最高の状態に近づけるには、適切な運動、やる気(意欲)あるいは果てしない好奇心であり、これは人間の進化の過程を推進してきた原動力であろうと考えられている。問題は恒常性に関わる多くの遺伝子を正の方向に発現させる統合的制御がどのように起こっているかということである。これはエピジェネティック的な遺伝子制御が統合的に働くと考えられるが、脳機能研究の今後の課題である。
意識と未来
意識は複雑な神経ネットワークから創発的に生まれるという考え方がある。創発的とは、「全体は部分の総和以上の何ものかである」という考え方に基づいている。コッホは以前この考え方を支持していたが、この考えでは意識がどのようにしてある種の脳活動から出てくるか説明できないという。一方、純粋な還元主義の立場から、脳活動をニューロンの集団レベル、個々のニューロンレベル、分子レベルとさかのぼっていっても、どこかのレベルで意識が突然生まれてくるとは思えない。コッホは、汎心論 (panpsychism) 的な考え方が一番納得いくと考えている。汎心論では、非常に低いレベルの意識が、非常に単純なシステムにも宿る。その単純なシステムが集まって高度の意識が生じてくるという。意識は構成成分の構造的特殊性(複雑性)から生じると考える。脳が意識を生み出す決定的な要因は、脳を構成する物質の特殊性にあるのではなく、システムの構成要素どうしがどの様に繋がりお互いに影響しあっているか、という構造レベルの特殊性にあるという。

茂木健一郎は昨年久しぶりに意識に関して、『クオリアと人工意識』(講談社現代新書、2020年)を刊行した。
最近のAIの発達は驚異的である。従来の方法での計算で何千年もかかることが、スーパーコンピューターなら数秒で解けるようになった。チェスや将棋、囲碁の名人がつぎつぎとAIに負ける時代になった。何十万手ある次の一手をAIは瞬時にして読み解く。しかし、AIには人間の特徴である意識が伴っていない。AIが進歩して将来意識を生じるコンピューターロボットができる可能性があると考える人が多い。
しかし、茂木は「人工知能に対する人間の関心は、やがては人間の知性を超えた人工知能をつくってしまおうとしている。それ以上に「人工意識」を生み出したいという衝動も、すべて私という存在の謎、「自己意識」の根源を理解したいという人間の切ない願望に起因しているように見える」と述べている(茂木健一郎『クオリアと人工意識』、291ページ)。
AIで人工意識を生じさせることが可能かどうかにかかっているが、私はAIに意識ある自己を与えることは直感的に不可能であると考える。人類のみが地球を圧倒的に支配し、開発と廃棄、地球温暖化、核戦争の危機、少子高齢化を考慮すれば、あと数千年もしないで人類は滅びると思う。しかし、コンピューターに人工意識が宿り人類がいなくても進化していく可能性があると考える研究者が多い。私は地層を見るのが好きであるが、ある種の驚異を感ずる。地層が傾きあるいは縦になったりしているとその途方もない時間と変動に衝撃を覚える。数千年すれば人類の時代(Anthropocone :Age of Human)は終わり、数百万年するとアントロポセンの地層(人類の時代の地層)が認められるであろう。
意識と宇宙
トノーニが医学生の時、手のひらに乗せた脳に感動した印象を述べている。脳は宇宙と対比される。無数の神経細胞と神経ネットワークにあるシナプスは宇宙に散らばる無数の星に類似している、どちらもその全貌はつかめない。
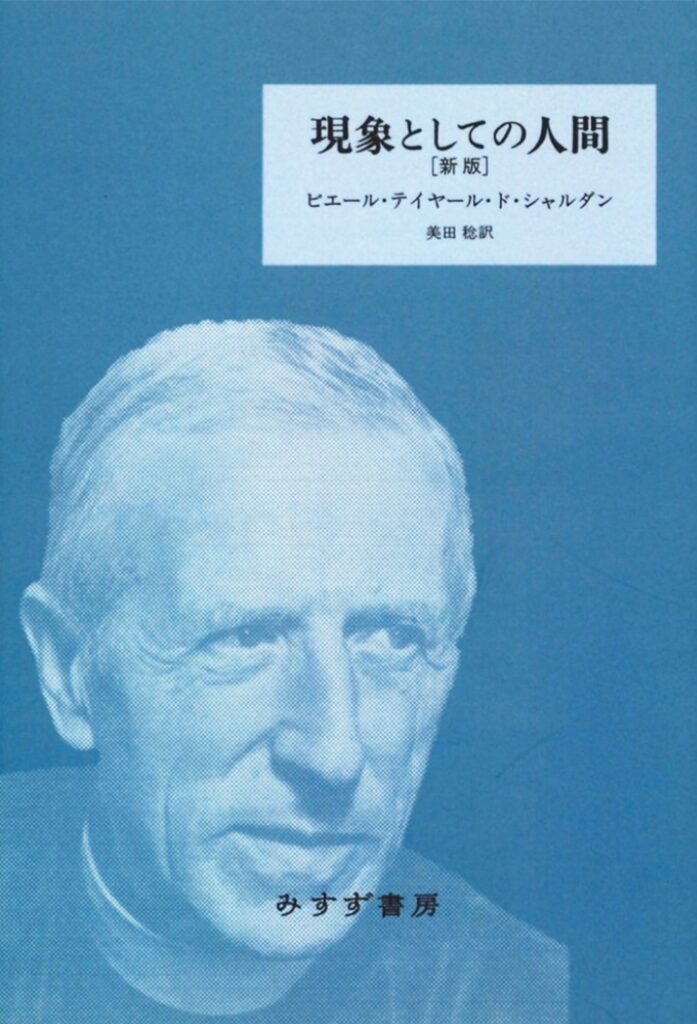
コッホによれば、イエズス会の司祭であったテイヤール・ド・シャルダンの主著『現象としての人間』によれば、ダーウィンの進化論を宇宙にまで広げて解釈し、宇宙レベルでの精神が出現する可能性についての刺激的な考えを記しているという(277ページ)。
宇宙はある方向に向かって生きているように複雑化している。アインシュタインも、宇宙は混沌としたカオスであってもよいはずなのに、なぜ美しい法則に乗って動いているのかと問い、宇宙に絶対者の存在を感じていたように思える。しかし、最大の謎は、なにも無い代わりになぜ何かがあるのかだ。そもそも時間、空間、エネルギーはなぜあるのか。これらは科学的では答えを出せない問いであると考える。
宇宙の無限の広がり、永遠の時間の流れを思うと、私は耐えられないような寒々としたものを感ずる。地球において単にアントロポセンの地層の中に痕跡として人類の時代が残るだけだとしたら、文明を築いてきた人類がこの地球にいたことに何の意味があったのだろう。

『生きがいについて』(みすず書房、1966年)を書いた神谷美恵子は死について、「人間が宇宙の中に調和し、宇宙の一部として帰っていく、人間を越えた大きな生命の河の流れに運ばれてゆくと感じると安らぎを感じる」と書いている(250-251ページ)。

『奇蹟の脳』(新潮文庫、2012年)を書いた脳科学者ジル・ボルト・テイラーは、自らの脳動静脈異常に悩んでいたが「自分が宇宙と一体であること、永遠の流れの一部であることを思い出して心の安らぎを感じた」と書いている(95-196ページ)。
私は宇宙に意識があってほしいと思い、死んだらそのほんの一部として合流したいと思う。
私の友人の寺川進氏は、人の意識の延長としての宇宙はないという。宇宙は意識を容れる容器としての脳を生みだした。その脳は、今や、全宇宙を記録(写像)する作業に取り掛かっている。そうさせているのは宇宙のおぼろげな意志かも知れないという。
私は宇宙に意識があってほしいと思う、しかし、意識に意志が伴っていたら怖くも感じられる。
(2021年5月30日)

(編集:前澤 祐貴子)

* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。
尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。
筆者
私の書いた読書ノートに関心をもって頂きありがとうございました。汎心論と意識については、コッホの記載を簡単に紹介しただけです。その後の英文の論争はフォローしていません。私自身は生命のないところには意識はないと感じています。宇宙に意識があるかどうか全く分からないし、証明のしようもないと思います。究極的には神を信ずるかどうかにかかっているように思えます。他のことで忙しいのでまだ本棚にありますが、ピエール・シャルダン「現象としての人間」美田稔訳(みすす書房)を精読したいと思っています。
遠藤 幸英
老化と意識をめぐる一連のエッセーを興味深く読ませていただきました。
KochやBononiが新規に定義しようとするpansychismあるいは ITT に関心が湧き(原著に当たらないままズルをして)ネット情報を探しました。最初に目に入ったTam Huntによる “The Romantic Reductionist: A Conversation with Christoph Koch” は短いながら読み応えがあります。https://www.independent.com/2013/03/13/romantic-reductionist/
これとは別に、2013年The New York Review誌上で展開されたKoch と Bononi 対(言語哲学を専門にする) J. Searle の論争がネット公開されているので読んでみました。Searleの反論は説得力があるように思えます。生命の有無にかかわらず個々の存在に意識があるのか、また宇宙意思があるのかどうか、Searle は否定的な姿勢を崩しません。https://www.nybooks.com/articles/2013/03/07/can-photodiode-be-conscious/
Searle は現在89歳。その後この論争がどう展開したのか気になるところです。